この記事でわかること
- 民事信託は3種類の事業承継に使えることがわかる
- 事業承継信託のメリット・デメリットがわかる
- 事業承継信託の実例がわかる
事業承継には、経営者の望み通りに契約が可能な民事信託を使うのが便利です。
今は元気に事業をしていても、いつまでも第一線で経営し続けることはできず、後継者に引継ぐ時期が訪れるでしょう。
近年は相続や遺言では不可能な「事業承継信託」で後継ぎ後継ぎを設定する経営者が増えています。
信託契約では、遺言を代用とした信託から、複数世代の後継者を指定する遺贈型受益者連続信託など、希望するスタイルで承継対策が実現可能です。
こちらでは、民事信託を事業承継として利用したメリット・デメリットや実例について解説します。
事業承継信託とは?
事業承継信託とは、経営者が後継ぎに事業承継する趣旨で自社株を信託し、会社の経営権を渡すことです。
後継者対策が必要となるのは、現経営者が永遠に事業継続はできず、いずれ引退する日が訪れるからです。
急な病気や認知症・死亡などにより判断が難しい状況に備えて、元気なときに後継ぎへ引き渡す条件を決めて信託しておくことが重要です。
認知症や病気などで正常な判断が難しくなると、信託契約を結ぶことは難しくなるでしょう。
株式会社には、会社経営に関する経営権と配当や財産を受け取る財産権の2つがあります。
信託契約により現経営者が自社株を後継ぎに引き渡し、現経営者の理想に基づいた形で保全運用を実施できます。
これからの事業承継は、相続や遺言では難しい機動的な契約が実現できる事業承継信託が定着していくと言えるでしょう。
事業承継信託は3種類の契約がある
事業承継信託には、遺言代用信託・他益信託・受益者連続信託という3種類の契約があります。
この中で、他益信託は現経営者(委託者)以外の人が受益者となる契約です。
こちらでは、3種類の方法について説明します。
遺言代用信託は遺言の代用になる
遺言代用信託とは、まさしく遺言の代用として信託を活用することを指します。
受託者を信託銀行とし、委託者兼受益者である現経営者(父)亡きあとは、特定の後継ぎに財産を残す契約をします。
何も対策していない場合、現経営者が亡くなると相続手続き終了まで空白期間ができ経営が不安定な状況になるでしょう。
委託者兼受益者である現経営者の二次受益者を後継ぎに設定しておくと、父亡きあとも財産は凍結されずに使えます。
信託契約を活用すると、相続につきものである空白期間がなく円滑に自社株を渡せるのです。
また、事業承継では後継ぎに全株式を渡す必要があるでしょう。
もし、バラバラに株が保持されていると議決権が分散してしまい、経営が不安定になりかねません。
たとえば、現経営者(委託者兼受益者)が後継ぎ(受益者)に経営を任せたいがまだ若いため、信頼できる他の人に経営者(受託者)に就任してもらいます。
現経営者が生存中は、受益者である現経営者が自社株を保有します。
信頼できる人を経営者(受託者)として経営を譲りますが、現経営者が亡きあと自社株の権利は後継ぎに移るように設定します。
信託契約は生前利用が不可能なため、亡くなったあと遺言の代用として効力を発揮するでしょう。
もし、遺言と遺言代用信託契約の2つが存在する場合、信託契約が優先されます。
遺言は意思を示す有効な手段ですが書き換えが簡単であるため、公正証書として作られた遺言代用信託の方が強い効力を持ちます。
遺言と遺言代用信託どちらの作成順位に関係なく、遺言代用信託が優先され信託契約通りに相続が行われるのです。
他益信託は財産権を渡しつつ経営にも携われる
他益信託は、現経営者が経営権を保有しながら財産権は後継ぎに譲り、自社株を第3者である信託銀行(受託者)に信託する契約です。
自社株の財産権は後継ぎに渡しながら、経営には携わるというケースに適しています。
他益信託の特徴として、現経営者(委託者)が経営権を保有しながら信託銀行(受託者)が保全・運用し、後継ぎ(受益者)が利益を確保します。
相続では、自社株の財産権を渡しながら経営権を持つことはできません。
相続は、現経営者が亡きあとに発生し財産権と経営権を一度に承継するからです。
他益信託を利用すると、自社株である財産権を後継ぎに渡し、現経営者が元気な間は経営権を持ちます。
つまり、現経営者が亡くなってから後継ぎに経営権を渡す契約です。
遺贈型受益者連続信託なら複数世代へ継承
遺贈型受益者連続信託では、事業を承継する2代目(受益者)も高齢などのケースもあり、さらに次の世代である3代目(受益者)を明示して信託できます。
もし、2代目しか決めていないと、2代目亡きあとは後継ぎの配偶者や家族に自社株が相続されてしまいます。
この場合、今まで会社経営に携わっていない人が経営権を持つこともあるので、会社経営の先行きが不透明になるケースも生じます。
遺贈型受益者連続信託を利用し、あらかじめ複数世代の後継ぎを決めておくことで、円滑に事業承継可能です。
ただし、信託期間は30年と規定があるため、30年を過ぎると受益権が1回しか引き継げなくなります。
遺言では、亡きあとにしか効力はなく次世代までの相続となり、孫の世代まで指定はできません。
遺贈型受益者連続信託でしたら、複数世代への事業承継が具体化します。
事業承継信託のメリット5つ
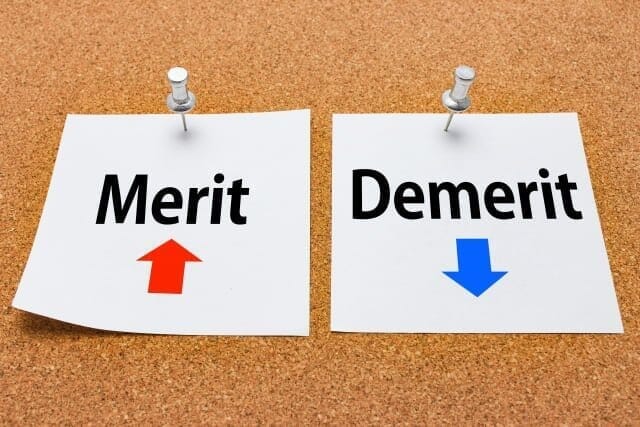
事業承継信託のメリットは5つあります。
こちらでは、事業承継信託のメリットについて説明します。
経営者が自由に設計して事業承継できる
事業承継信託は、現経営者の自由設計で契約を作り後継ぎに事業承継できます。
株式では経営権と財産権に分かれており、信託契約を使うと、現経営者が経営権を保有しながら後継ぎに財産権を引き渡すことが可能です。
たとえば、2代目の後継ぎである3代目の設定など、複数世代に渡り指定できるでしょう。
もし、2代目しか決めていない場合、2代目が亡くなると後継ぎの相続人に自社株は相続されます。
事前に信託契約しておくことで、思いもよらない人が経営者となるケースを未然に防げるのです。
事業承継信託は後戻りもできる
事業承継信託は、一度契約を結んでからでも後戻りが可能でしょう。
信託契約では、決めた内容通りに進まなかった場合、契約を白紙に戻せるのです。
たとえば、後継ぎには長男が適していれば長男、適さない場合は契約を解除して次男に承継するなども可能です。
あらかじめ信託契約時に設定しておくことで、機動的な契約が実現できます。
解除した場合は、経営権も現経営者に戻り、贈与税もかからず自社株を買い戻す資金もいりません。
信託契約は、想定するさまざまなパターンで設計と後戻りができる便利な契約です。
後継ぎの地位確立ができる
事業承継信託は、事業を引き継がせたい後継ぎの地位確立が可能でしょう。
相続では、後継ぎ以外に兄弟などがいた場合、遺産分割によって均等に相続する権利が発生します。
後継ぎ1人に承継する契約は不可能なため、信託契約によって定めておく必要があります。
通常の会社経営は、後継ぎ1人に株式を集約し経営の安定を図るので、信託契約による経営権の承継が重要です。
贈与や遺言では困難でも事業承継信託なら可能
事業承継するには、事業承継信託で決め事をするのが円滑で便利な方法です。
会社の実権を引き渡す方法として、贈与や遺言、後継ぎが株式を買い取ることでも可能です。
ただし、贈与や遺言などは制約も多く、フレキシブルな事業承継は難しいでしょう。
たとえば、贈与で自社株を渡した場合は後継ぎに贈与税がかかります。
後継ぎが自社株を買い取るケースなら、後継ぎは買い取り資金が必要となり、現経営者には所得税が発生します。
また、遺言で記した場合なら後継ぎに実権が渡せるのは現経営者が亡くなったあとでしょう。
父が亡くなったあと、自社株が後継ぎに渡った際に相続税が発生します。
信託契約では、遺言や贈与で承継が困難なケースでも円滑な設計により対応できるのです。
信託には原則として税金がかからない
信託契約は基本的に課税がなく、事業承継信託も原則税金はパススルーです。
自益信託の場合は、委託者=受益者となり、利益を受ける人の移動がないため贈与税の対象にならないからです。
ただし、自益信託により、現経営者(委託者)が亡くなり後継ぎ(受益者)に自社株が渡ったときに、後継ぎには相続税がかかります。
また、他益信託の場合でも現経営者(委託者 )から(受託者)への財産移転は、第3者は利益を得ないことから対象外でしょう。
他益信託で、現経営者(委託者)から後継ぎ(受益者 )に財産が移転すると、後継ぎには贈与税と今後得る利益には所得税が発生します。
事業承継信託のデメリット3つ
事業承継信託はメリットが多い制度ですが、注意が必要なデメリットもあります。
こちらでは、事業承継信託のデメリットについて説明します。
事業承継は経営者の死亡が原則となっている
事業承継信託は、現経営者が亡くなってからの事業承継が原則となっています。
信託契約の方法は3種類ありますが、いずれの場合でも現経営者亡きあとからの承継です。
たとえば、まだ元気なうちにと早めの退任を希望しても、それを理由に承継は不可能でしょう。
生きている間に事業承継したい場合は、贈与など他の方法を取る必要があります。
信託制度自体が知られておらず理解が得づらい
事業承継信託の仕組みが一般的には知られておらず、家族や周りの人の理解を得づらい側面があります。
民事信託は、平成19年の改正信託法により財産管理や財産承継の手段として整備された、新しい仕組みです。
家族に信託への理解を得て活用するには、司法書士など専門家の知識と力を借りましょう。
信託契約に関わる人たちが、納得して役目を全うできるよう、契約の中身についてしっかりと理解することが大切です。
遺留分減殺請求への見解が確定されていない
相続時の遺留分減殺請求の取り扱いは確定されていません。
遺留分減殺請求とは、特定の人に有利な分配がされた場合、他の相続人が最低限の取り分を確保できる権利です。
たとえば、現経営者に自社株しか相続するものがなかった場合、後継ぎ以外の兄弟や配偶者は、何も相続する財産がなく揉めるケースがあるでしょう。
相続では、配偶者や後継ぎ以外の兄弟は遺留分を請求できるのですが、信託法の解釈は定まっていないのが実情です。
民事信託を利用した事業承継の例

民事信託は事業承継に使われていますが、どのようなケースで活用されているのでしょうか。
こちらの章では、事業承継の実例について説明します。
経営権の確保に使える
現経営者が保持しているすべての自社株について、経営権を後継ぎに引き渡せます。
自社株に価値があるケースでは、信託契約していないと会社の経営権を持たない配偶者や子供にも遺産分割により自社株を渡すことになり、経営権が分散する恐れがあります。
この場合、自社株の経営権は後継ぎに渡し、株の財産権は会社を継がない子供や配偶者に渡すことで、遺留分の補完ができるでしょう。
また、経営者が病気や認知症で職務を遂行できなくなったときには、後継ぎが経営権を発動します。
後継ぎの地位を確立できる
事業承継信託では、現経営者が特定の後継ぎに自社株を引き渡し承継します。
後継ぎを決める際には、融資を受けていた金融機関の思惑が影響するケースもあるでしょう。
取引先にも後継ぎであることを周知させるために、信託契約以外に後継ぎの育成をするなど前準備は必要です。
もし、信託契約ではなく遺言書で後継ぎを設定した場合は、容易に書き換えられるため、会社の経営が不安定になる恐れもあるのです。
遺言代用信託を使い後継ぎ対策しておくと、自動的に特定の後継ぎに自社株の承継ができます。
各自が所有している経営権を取りまとめたい
株式会社を立ち上げる際に、発起人である株主たちが自社株(経営権)を持つケースがあります。
株主総会で大切な話し合いをするときに、経営権がバラバラだと決議するのが難しくなります。
たとえば、名前だけ関与している親族などは、当初から経営権を保有していることがあるでしょう。
事業承継信託では、複数の株主から株を信託してもらい経営権をまとめられるのです。
相続順位に影響のない事業承継がしたい
2代目3代目と後継ぎを決めていても、相続に関しては順番が違うケースがあります。
たとえば、次期後継ぎは長男ですが長男夫婦には子供がいないので、次は次男、そして次男の子供に継いでもらいたいなど。
信託契約では、長男が亡くなったあとは次男の子供に継がせるなどフレキシブルな対応ができます。
相続で承継する場合は長男の遺言が必要になりますが、信託契約なら現経営者が順番を自由に決めることが可能です。
まとめ
民事信託を事業承継信託として活用する事例やメリットなどについておわかりいただけたでしょうか。
信託は、相続や遺言では対応が難しい柔軟な内容を織り込める新しい制度です。
信託契約で実現することにはメリットが多くありますが、課税されるタイミングや遺留分の見解など注意すべき点もあります。
現経営者が元気な間に、会社の未来を託す後継者対策に備えることは必要不可欠と言えるでしょう。

























