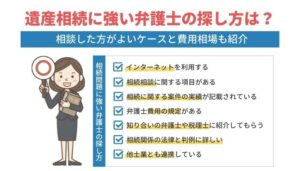この記事でわかること
- 宝石や貴金属などの物品の生前贈与に贈与税がかかるか
- いくらまでの生前贈与であれば贈与税がかからないか
- 手渡しの生前贈与が税務署にバレるか
- 手渡しの生前贈与が税務署にバレた場合のペナルティ
大切な人に、宝石や貴金属を生前贈与で渡したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、贈与税がかかるのか、手渡しなら税務署にバレずに済むのかなど、気になる点も多いはずです。
この記事では、宝石や貴金属などの物品を生前贈与した場合に、贈与税が発生する条件や注意点について詳しく解説します。
さらに、贈与が税務署にバレる理由や、バレた際のペナルティについても説明します。
生前贈与を適切に行いたい方は、ぜひこの記事を参考にして、安心して大切な人に宝石などを渡しましょう。
目次
生前贈与で贈与税がかかる物品とは
生前贈与で贈与税がかかる物品には、どのようなものがあるでしょうか。
答えは、金額に関係なく贈与されたすべての物品が贈与税の対象です。
ただし、年間110万円以内の贈与であれば非課税のため、多くの贈与は非課税です。
贈与税の仕組みについては後述します。
ここでは、贈与税が課税される物品について解説します。
時価110万円以内の物品でも贈与税が課税される場合がある
贈与税を算出する課税金額は、時価で計算します。
時価110万円以内の物品であれば、貴金属や宝石でも贈与税が課税されないように思うかもしれません。
しかし、贈与税はその人が1年間(1月1日~12月31日まで)で贈与された合計金額で判断されます。
金地金(インゴッド)
金地金は生前贈与として手軽に渡せますが、売却時に利益が出ていると譲渡所得税を支払う義務が発生します。
そのため、金地金は贈与税・譲渡所得税の2つの面から税務署にチェックされています。
子どもや孫に、いざという時の資産として金地金を生前贈与する場合、110万円を超えるようであれば贈与税の申告をしておきましょう。
宝石・貴金属
宝石・貴金属についても、時価110万円を超えれば贈与税の申告が必要です。
高価なダイヤの指輪をプレゼントしてもらったものの、翌年贈与税の申告をしなければならないのは、せっかくの贈り物なのに残念な気持ちがしてしまいますね。
しかし、婚約指輪など「社会通念上相当と認められるもの」であれば、贈与税が免除される可能性があります。
ただ、いくらの婚約指輪までなら大丈夫という具体的な基準がないため、何百万円もするような婚約指輪の場合には、税理士に相談した方がよいかもしれません。
生存贈与を手渡しでもらってもバレる
婚約指輪はほぼ間違いなく手渡しですが、手渡しなら税務署にバレないように思うかもしれません。
しかし実際には、手渡しの生前贈与がバレてしまうケースが多くあります。
ここでは、手渡しの生前贈与がバレる原因と、バレた時のペナルティについて解説します。
手渡しでもバレる原因
次のような経緯で、手渡しの生前贈与が税務署にバレてしまいます。
高額な買い物でバレる
マンションなどの不動産、株式で高額な投資をした場合は、税務署に通知が届きます。
このため、収入に見合わない高額な買い物をすると、お金の出所が調べられ、手渡しの生前贈与がバレてしまうかもしれません。
相続時にバレる
相続時には、被相続人の預貯金通帳の履歴だけでなく、過去の高額な買い物の履歴なども調べられます。
金地金を沢山購入していたのに、数本しか残っていないといった状況であれば、金地金の行き先が調べられます。
手渡しの生前贈与がバレた場合のペナルティ
手渡しの生前贈与がバレると、延滞税や無申告加算税、悪質な場合には重加算税・懲役刑を受ける可能性があります。
高額な生前贈与を受けた場合は、手渡しでもバレると思って、贈与税の申告を行いましょう、
生前贈与で非課税になる限度額

生前贈与には、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの制度があります。
それぞれ一定の限度額(基礎控除額)があり、その限度額以内であれば非課税になります。
ここでは、各制度の概要を解説します。
暦年課税制度では、年間110万円までの生前贈与が非課税
暦年課税制度は、1年間(1月1日~12月31日)で誰からいくら贈与を受けたかを基準に、贈与税額を計算します。
年間110万円以内の生前贈与は申告不要
1年間で生前贈与を受けた金額が110万円以内であれば、贈与税の申告は不要です。
現金は額面がそのまま課税金額となりますが、貴金属、宝石、金地金は時価が課税金額となります。
そのため、生前贈与を受けた日と内容はメモに残しておき、鑑定や金相場などで課税金額の合計を把握しておきましょう。
生前贈与が年間110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要
生前贈与で受け取った総額が年間110万円を超えた場合は、翌年の2月15日~3月15日までの間に、贈与税の申告が必要です。
なお、親や祖父母から18歳以上の子または孫が生前贈与を受ける場合、贈与された財産は特例贈与財産として、税率などが優遇されます。
相続時精算課税制度は生前贈与の非課税枠が2,500万円
相続時精算課税制度は、2,500万円までの生前贈与が非課税となる特例です。
この制度を使えば、宝石・貴金属や不動産などの高価な財産の贈与にかかる贈与税を大幅に抑えられます。
制度の条件、注意点は次のとおりです。
非課税枠は2,500万円+年間110万円
特別控除は2,500万円で、制度の利用開始時から贈与者が死亡するまでの贈与を累計します。
相続時には、この贈与額を加算して相続税を計算します。
また、令和6年1月1日からは新たな非課税枠として年間110万円の基礎控除が設けられました。
この基礎控除は2,500万円の特別控除の累計には加算されないため、贈与税の節税効果があります。
対象となる贈与
対象となる贈与は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与です。
申告期限
申告期限は贈与を受けた翌年の2月15日から3月15日です。
注意点
一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者・受贈者の関係では暦年課税制度に戻れません。
また、翌年の申告を忘れると相続時精算課税制度が利用できず、高額の贈与税が発生する恐れがあります。
相続時精算課税制度の申告は忘れないように注意しましょう。
相続時精算課税制度はメリット・デメリットが多く、特に相続税対策が必要な財産状況の贈与者であれば、すべての財産を精査した上で、慎重に選択する必要があります。
非常に魅力的な制度ですが、相続時精算課税制度の利用を検討する方は、必ず税理士に相談されるようおすすめします。
まとめ
宝石・貴金属の生前贈与は、年間110万円を超えると贈与税の申告と納税が必要です。
そして、手渡しの生前贈与ならバレないと考えがちですが、税務署にバレる可能性がある上、バレた時には最悪の場合、懲役刑が科せられるかもしれません。
手渡しならどうにかなると思わず、高額な生前贈与を受けた場合は必ず贈与税の申告を行いましょう。
申告手続き、評価方法、税務署とのやり取りが不安で心配な方は、税金の専門家である税理士に相談しましょう。