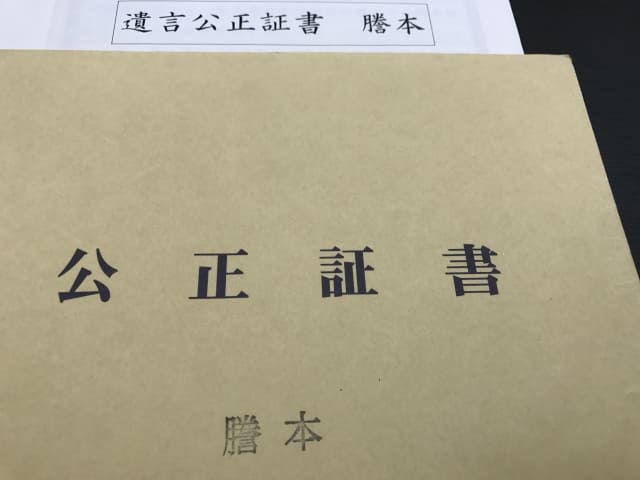この記事でわかること
- 公正証書遺言と遺留分について理解できる
- 遺留分侵害額請求の優先順位がわかる
- 公正証書遺言による相続トラブルを回避する方法がわかる
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言の場合は、偽造や強制が疑われて相続トラブルになることがありますが、公正証書遺言はそのようなトラブルにほとんどならないのが特徴といえます。
しかし、公正証書遺言であっても、遺留分についてはトラブルになる場合があります。
この記事では、公正証書遺言と遺留分について解説をしながら、遺留分をめぐってのトラブルを回避する方法もご紹介していきます。
ご自分の財産について、後々のご希望がある場合などに、参考にしてください。
目次
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公正証書の形で作成された遺言書のことをいいます。
公正証書は、証人2名の立会いのもと、公証役場で公証人によって作成されます。
作成後の原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失を防ぐことができます。
ですから、法的に信頼性が高く、強力な効果があります。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が相続財産に対して持っている最低限の取り分のことで、民法が法定相続人に対して保障しているものです。
しかし、法定相続人の中でも、遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。
遺留分が認められる法定相続人
遺留分が認められる人は、配偶者・直系卑属(子ども、孫、ひ孫など)・直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など)に限られています。
遺留分のない法定相続人
被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合には、遺留分は認められていません。
兄弟姉妹の代襲相続人も同様です。
また、相続人欠格になった相続人や廃除された相続人にも、認められません。
遺留分の割合
相続人が配偶者の場合は、本来の法定相続分(遺言がなかった場合の法定相続分)の2分の1となります。
子どもや孫など直系卑属の場合も、本来の法定相続分の2分の1です。
親や祖父母など直系尊属の場合は、本来の相続分の3分の1となります。
公正証書遺言があっても侵害分の遺留分請求は可能
公正証書遺言は信頼性が高い遺言書ですが、それでも遺留分を侵害することはできません。
遺留分を侵害された相続人が、遺言で遺贈を受けた人に対して遺留分を請求した場合には、その請求を拒否することはできないとされています。
つまり、遺留分の侵害があった場合は、侵害された遺留分の請求をすることが可能です。
遺留分請求先が請求に応じない場合
もしも相手が請求に応じない場合には、弁護士を通じての交渉や、裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺留分の侵害があっても遺言どおりに執行される場合
遺言の内容に遺留分の侵害があるからといって、ただちに遺言が無効になるわけではありません。
たとえ他の相続人の遺留分を侵害する内容であっても、遺留分の請求がなければ、遺言どおりに執行されます。
遺留分の請求には時効があり、相続発生と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実を知ってから1年が経過すると、請求ができなくなります。
また、相続発生後10年が経過すると、相続発生と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実を知らなくても、請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求先の優先順位
遺留分侵害額請求をする相手方は、遺言により遺産を譲り受けた人及び生前贈与を受けた人となります。
しかし、遺産を譲り受けた人や生前贈与を受けた人が複数名いた場合は、その中の誰にでも請求をできるわけではありません。
このような場合は、原則として、民法の定めに従って請求対象者が決まります。
ただし、遺言者が遺言の中で、民法の定めとは異なる意思を表示していたときは、遺言者の意思に従って遺留分侵害額請求を受ける順序が決められます。
民法の定めによる請求先の優先順位
遺言書の内容には、遺贈と贈与の両方がある場合もあります。
遺言によって遺贈を受けた人を受遺者といい、遺言によって贈与を受けた人を受贈者といいます。
民法の定めによれば、受遺者と受贈者がいる場合の遺留分侵害請求先は、受遺者が先になります。
受遺者の場合
受遺者が複数名いた場合は、複数名に対して、遺贈を受けた財産の価額に応じて、同じ割合で請求をします。
遺贈の価額が少額であった場合など、受遺者に請求してもまだ不足があるときは、受贈者に不足分を請求します。
受贈者の場合
受贈者は、死因贈与を受けた人と生前贈与を受けた人がいる場合、死因贈与を受けた人の方が、優先順位は先になります。
死因贈与を受けた人が複数いた場合は、受遺者と同様に、贈与を受けた財産の価額に応じて請求し、なお不足のある場合は、生前贈与を受けた人に対して請求をします。
生前贈与を受けた人が複数名いるときは、生前贈与の時期によって優先順位が決まります。
この場合、生前贈与を後(より死亡時に近い時期)に受けた人に対して、先に請求をすることになります。
公正証書遺言による遺留分トラブルの対策例

公正証書遺言において、遺留分を侵害してしまう恐れのあるものは以下のような行為です。
- ・遺言による遺贈
- ・遺言による相続分の指定
- ・遺言による寄付
- ・死因贈与
- ・相続発生前1年間における生前贈与
- ・遺留分を侵害すると知っていて行われた生前贈与
- ・特別受益が成立する場合の生前贈与
このうち、遺言によって第三者に遺産が遺贈されたり、相続人の相続分が指定されたり、第三者に寄付をされた場合が、多く見受けられます。
公正証書遺言によって特定の人に遺産を譲りたい場合に、どうすれば遺留分トラブルが起こらないようにできるか、その対策例をご紹介しますので参考にしてください。
遺留分に相当する財産を遺留分請求権者に残す内容で遺言書を作成する
あらかじめ、遺言書を作成する際に、遺留分請求権者に対して遺留分相当額の財産を遺す内容にしておく方法です。
遺留分請求権者は、法定相続分よりは少ないものの、遺留分相当額の遺贈を受けるため、遺留分トラブルは発生しません。
生前に遺留分請求権者に遺留分放棄をしてもらう
遺留分は、遺留分請求権者の意思により、被相続人の生前であっても放棄することができます。
生前に遺留分放棄をしてもらえれば、死後に遺留分を請求することができなくなるため、遺留分トラブルを防ぐことができます。
ただし、遺留分放棄は必要な要件を満たしていなければならず、遺言者の都合で一方的に放棄させることはできません。
遺留分放棄の要件
遺留分放棄は、遺留分請求権者が自ら家庭裁判所に対して、遺留分放棄の許可を申し立てる必要があります。
また、申立が認められるには「遺留分を放棄する合理的な理由がある」ことと「遺留分請求権者に相当な対価が与えられている」ことが要件とされています。
付言事項を利用する
付言事項とは、遺言書に記載する内容のうち、法的効力が認められる「法定遺言事項」以外の部分のことです。
法的な効力はありませんが、遺言者がなぜこのような遺言をしたのかという真意を知ることができます。
また、遺言の内容の趣旨を説明することで、遺留分の請求を思いとどまってもらえる可能性があります。
付言事項に記載された内容が、遺留分請求権者から理解され、円満な遺言執行ができるように、生前からよく話をしておくことも大切といえるでしょう。
多くの財産を特定の人に遺贈する場合
多くの割合の財産を特定の人に遺贈する際には、その理由を記載しておきます。
例えば、障害があって収入を得るのが難しいからとか、家業を継ぐからとか、介護をよくしてくれたからとか、具体的にわかりやすくしておきましょう。
他の相続人(遺留分請求権者)も、事情を理解して、遺留分請求を思いとどまってくれるかもしれません。
生前贈与をしていた場合
昔のことであっても、遺留分請求権者に生前贈与をしていた場合には、その旨を記載しておくとよいでしょう。
請求権者が生前贈与のことを忘れてしまっていると、遺留分請求をしてしまうことも考えられますが、付言事項として記載しておけば思い出すことができるため、遺留分請求を思いとどまることがあり得ます。
遺留分減殺請求に関わる法改正
2019年7月1日施行の改正法により、これまでの遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求に変わりました。
従って、施行日以降に開始された相続は、改正法である遺留分侵害額請求が適用されます。
法改正前は、遺留分を侵害された場合は、侵害額ではなく減殺を請求できたので、財産そのものを返還する現物返還が原則でした。
これが、法改正後は、現物返還ではなく、侵害額(金銭)を請求することになりました。
遺言による対象財産の指定について
これまでは、遺留分トラブルを防ぐ方法として、遺留分の請求をされたときに対象となる財産を指定しておくことがよくありました。
対象財産を預貯金などの金銭にしておくことで、不動産の分割を避けるなどの効果があったのです。
ですから、法改正前に作成された遺言書には、対象財産が指定されている場合があります。
法改正後の対象財産の指定の取り扱い
法改正前に作成された遺言書の相続が法改正後に発生した場合、その遺言書に対象財産の指定があっても、現物返還ではなく侵害額(金銭)請求になってしまったため、意味がなくなりました。
しかし、これによって、遺言自体が無効になることはありません。
遺言自体は有効で、対象財産の指定が無意味になっただけです。
まとめ
公正証書遺言は、ご自身で考えた内容を公証役場で公証人に書面にしてもらえば、とにかく作成することはできます。
しかし、その内容が後々の遺留分トラブルになってしまうこともあり得ます。
遺留分トラブルは、相続人の方たちが、つらい気持ちになってしまいます。
公正証書遺言を作成する際には、専門家である弁護士にまず相談して、トラブルにならないような内容にしたうえで、公証役場に行くことをおすすめします。