この記事でわかること
- 負担付贈与が住宅ローン控除を適用できない理由
- 負担付贈与と売買の違い
- お得に贈与する方法
負担付贈与は一見すると贈与税を節約できる魅力的な贈与方法に思えるかもしれません。
しかし、負担付贈与には住宅ローン控除が適用されないという大きな落とし穴があります。
この記事では、負担付贈与が住宅ローン控除の対象外となる理由を詳しく解説します。
また、どのように行えばよりお得に贈与できるのかを紹介します。
この記事を読めば、税金面での不利を避けつつ、賢く贈与を活用するための知識が得られるでしょう。
負担付贈与とは
負担付贈与の概要、負担付贈与のメリット・デメリット、売買との違いについて詳しく解説します。
負担付き贈与の概要
負担付贈与とは、不動産や現金を贈与する条件として、受贈者(財産を受け取る側)に一定の負担を負ってもらう贈与契約の一形態です。
負担付贈与のメリット
負担付贈与には、次のようなメリットがあります。
契約書なしでも成立する
負担付贈与の契約に契約書は不要なため、口頭でも成立します。
しかし、負担内容が曖昧だとお互いの認識にズレが生じてしまい、後々のトラブルにつながる可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、契約書を作成しておきましょう。
一定の条件で撤回できる
一般的な贈与の場合、贈与が終わった後に贈与の撤回はできませんが、負担付贈与は、受贈者が負担(債務)を履行しない場合に贈与を撤回できます。
手間のかかる内容でもお願いしやすい
家事の手伝いや送迎、ペットの世話など手間のかかる内容でも、贈与とセットにすればお願いしやすく、受贈者も気持ちよく負担を履行できるでしょう。
負担付贈与のデメリット
負担付贈与には、デメリットもあります。
贈与物の欠陥があると責任の所在で揉める可能性がある
負担付贈与を行う場合、贈与者は負担の限度において、売買の際の売主と同じレベルの責任を負うため、贈与物の欠陥に対する責任が問われます。
揉めないためには、贈与物に欠陥がないか、欠陥があれば事前に受贈者に伝えて契約書に盛り込むなどの対応が必要です。
贈与物と負担の価値によっては贈与税・譲渡所得税等が課税される
負担する価値より贈与物の価値が高ければ受贈者に贈与税、贈与物の価値より負担する価値が高ければ贈与者に譲渡所得税等が課税される可能性があります。
負担付贈与と売買の違い
負担付贈与は贈与者・受贈者の両者が債務を負う「双務契約」のため、買主がお金を支払い売主が物品を渡す売買と負担付贈与は近い概念と言えます。
なお、通常の贈与は贈与者のみが債務を負う「片務契約」といいます。
負担付贈与と売買の違いをまとめました。
(贈与者・売主を譲渡人、受贈者・買主を譲受人とします)
| 負担付贈与 | 売買 | |
|---|---|---|
| 譲渡するもの 売買商品 |
不動産、物品、現金 | 不動産、物品、サービスなど (現金以外) |
| 対価 | 家事手伝い、ペットの世話、 住宅ローンの返済など (現金以外※現金が対価だと、「売買」になる) |
原則は現金 (対価が物品だと「交換」になる) |
| 契約の履行 | 贈与後も、受贈者の負担が続くケースがほとんど | 同時履行(モノとお金を渡して終わり) |
契約の履行が一度で終わるかどうか、対価が現金か現金以外かといった点で区別されます。
負担付贈与は住宅ローン控除が適用できない
子が親から、親名義のマンションを贈与してもらう代わりに住宅ローンを引き受けるようなケースは、負担付贈与の代表例です。
しかし、負担付贈与でもらったマンション・戸建ての住宅には、住宅ローン控除が適用できません。
住宅ローン控除が適用できない理由、住宅ローン控除以外のメリットについて解説します。
負担付贈与後の住宅ローン債務者が贈与者の場合
負担付贈与後、住宅ローンの債務者が贈与者名義のままであれば、子はあくまで負担付贈与の対価として親(贈与者)に代わって住宅ローンを返済していることになります。
子本人が金融機関から借り入れたお金を返済しているわけではないため、住宅ローン控除は受けられません。
負担付贈与を使う場合
前述したように住宅ローンが残った不動産の負担付贈与は、住宅ローン控除が使えません。
不動産の負担付き贈与は住宅ローンの残債、利息、受贈者の収入・支払い能力、家族構成などを総合的に考えてから行う必要があるでしょう。
負担付贈与と住宅ローン控除に関するよくある質問
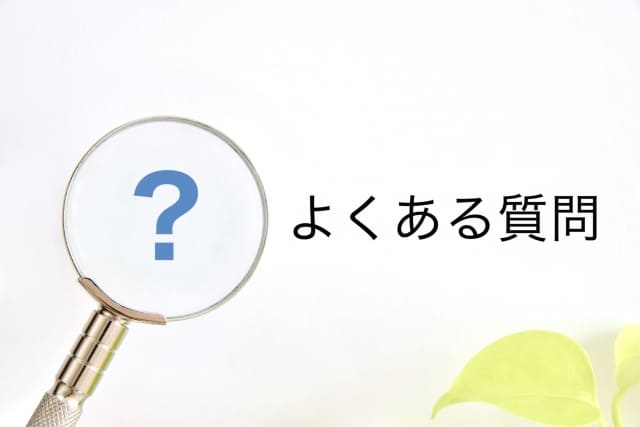
負担付贈与と住宅ローン控除に関するよくある質問と回答は次のとおりです。
2024年に住宅購入のための贈与を受ける場合、いくらまで非課税ですか?
2024年の住宅取得等資金は、省エネ等住宅が1,000万円、省エネ等住宅以外の住宅が500万円まで非課税となっています。
また、暦年課税制度の基礎控除(年間110万円)も併用できます。
住宅ローン控除と住宅資金等資金贈与を併用できますか?
住宅取得等資金贈与と住宅ローン控除は併用可能です。
贈与税がかからずに住宅を贈与する方法は?
現存している住宅について、贈与税がかからず贈与するには、相続時精算課税制度がおすすめです。
60歳以上の父母または祖父母から子・孫への贈与の場合、相続時精算課税制度を使えば2,500万円までは非課税のため、大幅に贈与税を減らせるでしょう。
住宅ローン控除は住んでいなくても適用されますか?
転居して住民票を異動すると、原則として住宅ローン控除は受けられません。
しかし、単身赴任で一時的な引っ越しなどの事情があれば、住宅ローン控除が受けられる場合もあります。
それぞれの事情によって判断されるため、引っ越し前に税理士・税務署に相談しましょう。
まとめ
負担付贈与を使うと、住宅ローン控除が適用されないなど不利益な面もありますが、上手に活用すれば、節税した上で、贈与を受けられる可能性があります。
負担付贈与は贈与物、負担内容の価値によって贈与税・譲渡所得税等が課税されます。
贈与物も負担内容も現金以外については評価方法が複雑であり、負担内容については贈与後も継続する場合が多いため、税理士などの専門家に相談しながら、自分に合った方法を見つけましょう。

























