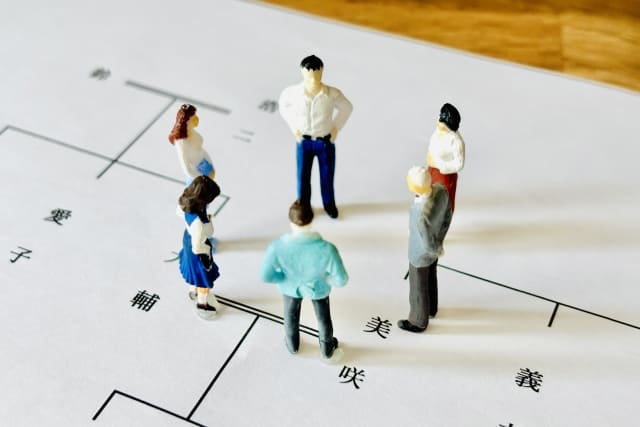この記事でわかること
- 遺言代用信託について
- 遺言代用信託にかかる費用
- 遺言代用信託のメリット、デメリット
相続対策や財産管理の方法の一つに、遺言代用信託というしくみがあります。
生存中の財産管理から、死後の財産の受け渡しまでスムーズに行うことのできる便利なサービスです。
ただし、しくみが少し複雑なため、ポイントを押さえて理解しておくことが大切です。
今回は遺言代用信託のしくみについて、メリット・デメリットや費用などをわかりやすく解説します。
目次
遺言代用信託とは
遺言代用信託は文字通り、遺言の代用となる信託制度で、信託銀行などが行っているサービスです。
あまり馴染みがないという人も多いでしょう。
遺言代用信託は、生前に契約を行い、死後に効力が発生するしくみのため、生前にしっかり準備ができるという特徴があります。
ここでは遺言代用信託の概要と、遺言信託との違いなどについて解説します。
遺言代用信託の概要
まず遺言代用信託とはどういうものか、基本的な特徴を見ていきましょう。
- 信託銀行と生前に契約を結ぶ
- 死後、財産を特定の人へ渡すことができる
- 生存中の資産の管理も依頼できる
本人を委託者、金融機関を受託者として、信託銀行などの金融機関と契約を結びます。
生存中は本人を受益者とし、本人の死後は指定した家族が受益者となり、財産を引き継ぐことができるしくみです。
通常、相続が発生すると、相続手続きが終了するまで財産を引き出すことはできません。
しかし遺言代用信託を利用すれば本人の死後、相続手続きを経ることなく、スムーズに財産を引き継ぎ活用できます。
生存中の運用・管理は信託銀行が行うため、安心感と信頼性が高いという点が魅力です。
万が一、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、成年後見に代わって財産の管理をしてもらえます。
遺言を作成しなくても、確実に財産を引き継げる制度です。
不動産は信託できない
遺言代用信託では不動産は信託できません。
不動産以外に株も信託不可とされており、信託できる財産は預貯金のみとされています。
一部の信託銀行では、遺言代用信託と組み合わせて不動産管理信託を提供している場合もあります。
不動産を所有している場合や特定の人へ確実に引き継ぎたい場合には、取扱いのある信託銀行に相談しましょう。
遺言信託との違いとは
遺言代用信託と混同されやすいのが遺言信託です。
遺言信託は、遺言書の作成から保管、遺言執行までの相続手続きを、信託銀行などが主体となって一貫してサポートするサービスのことを言います。
また、法律用語の遺言信託とは、遺言の中で特定の人を指定し、特定の財産の管理や処分を信託することを言います。
一般的に遺言信託と言えば、信託銀行の商品を指すことが多いでしょう。
遺言代用信託は、遺言の代わりに信託を利用するものですが、遺言信託は遺言自体を信託するものです。
言葉は似ていますが内容は大きく異なり、まったく別のサービスです。
利用を検討する場合は、専門家に相談しましょう。
家族信託との違いとは
そもそも信託とは、受託者が委託者に代わって財産の管理・運用・処分を行い、受益者が利益を受け取るというしくみです。
家族信託も遺言代用信託も、信託契約の一種です。
家族信託は、受託者を子どもや孫など、信頼できる家族を指定するのに対し、遺言代用信託の受託者は信託銀行などの金融機関となります。
家族信託は家族間で契約が完了するため、信託報酬などの手数料がかからず、基本的には管理費なども不要です。
遺言代用信託は、契約時の手数料や利用している間のランニングコストが必要になります。
遺言代用信託のメリット
相続対策を検討する場合に「家族同士で揉めてほしくない」と思う人は多いでしょう。
遺言代用信託は死後の手続きのスムーズさに加え、相続人の間のトラブルを防ぐこともできます。
ここでは、遺言代用信託のメリットを詳しく解説します。
死後すぐに財産が渡せる
遺言書がある場合、検認手続きや内容の確認などに時間がかかることがあります。
また、遺言の内容に相続人が納得しない場合や、そもそも遺言がない場合は、遺産分割協議を行う必要があり、相続手続きが完了するまで財産を動かすことができません。
遺言代用信託を利用すると、生前のうちに信託契約を結ぶため、被相続人の死後すぐに指定された人へ財産を移すことができます。
たとえば被相続人に扶養されていた配偶者や子どもが、生活費をすぐに引き出したいという場合などに非常に有効な方法と言えます。
トラブルを未然に防ぎやすい
遺言代用信託では生前に、誰に何をどれほど渡すのか具体的に決めておくため、相続時のもめごとを避けやすくなります。
信託銀行などの第三者機関が関与するため、公平な立場での管理が行われるのも安心できるポイントです。
たとえば、家族構成が複雑なケースや、特定の子どもに財産を相続させたい場合でも、明確な形で意志を残すことができ、残された相続人が手続きで戸惑うこともありません。
財産の管理を専門家に任せられる
遺言代用信託では、生前から信託銀行などの専門機関が、財産の管理・運用を行い、判断能力が低下した場合には、成年後見制度に代わって管理をしてもらえます。
「高齢になって財産管理が難しい」「万が一認知症になった場合が心配」といった不安も軽減できるでしょう。
また、独身や子どもがいない人など、受託者となってくれる家族や親族がいない場合も有効です。
家族信託では、財産の管理をする受託者を自分で見つけなければいけませんが、信託では金融機関が受託者となります。
財産の管理・運用・処分には一定の負担が必要ですが、遺言代用信託では金融機関が受託者となるため、受託者の負担を考える必要もありません。
遺言代用信託のデメリット
メリットがある一方で、デメリットも存在します。
ここでは、遺言代用信託を実際に利用する前に理解しておきたいデメリットについて解説します。
一度契約すると内容の変更が難しい
遺言代用信託の大きなデメリットとして、柔軟な対応ができないということがあげられます。
遺言代用信託は契約型の制度であり、一度締結したら原則、解約できません。
解約できる場合でも、解約手数料など追加の費用がかかる場合があります。
たとえば相続先を変更したくなった場合や、資産を追加したい場合は、基本的には再契約が必要です。
遺言代用信託は長い場合は20~30年の信託期間となるため、契約時には将来の可能性も見越して、慎重に相続計画を設計する必要があります。
手数料が割高に感じられることも
遺言代用信託は、信託銀行などの専門機関が関与するため、費用面で一定の負担が発生します。
契約時の初期費用に加え、管理報酬や実行時の手数料がかかる場合があります。
特に預ける財産が少額の場合、管理される内容に対して費用が割高に感じられることも少なくありません。
反対に、財産が高額になると、財産額に応じて手数料も上がるため、家族信託など他の方法の方が費用を抑えられることもあります。
相続対策の一つとして考える場合、複数の遺言方法や依頼先などと比較検討する必要があるでしょう。
家族信託に比べて自由度が低い
遺言代用信託は、あくまで信託銀行の定めたスキームに沿って設計されるため、家族信託のように自由な設計ができません。
たとえば財産を段階的に渡すことや、子どもによって異なる条件を設けるといった柔軟な対応は難しい場合があります。
また、不動産や株などが信託できないという点もデメリットでしょう。
家族信託であれば財産の管理を家族に委託するため、内容を自由に変えることが可能です。
自分で細かく設計したい場合や、家族と話し合って決めたいという人には、遺言代用信託が合わないと感じるかもしれません。
銀行で遺言代用信託手続きをする流れ
「遺言代用信託を検討してみたいけれど、実際にどのような手続きなのかよくわからない」という方は少なくありません。
全体像が見えなければ、なかなか手続きに踏み切ることは難しいでしょう。
ここでは初回相談から契約、実行までの一般的な流れを解説します。
相談予約をする
まずは信託業務を取り扱っている銀行に連絡し、事前相談の予約を取ります。
オンライン相談を受け付けている金融機関も増えているため、忙しい人でも相談しやすいでしょう。
この時点では費用はかからない場合が多く、気軽に相談してみるのがおすすめです。
面談・ヒアリングを受ける
予約当日には、信託専門の担当者との面談が行われます。
信託したい財産の内容や相続人の状況、希望する分配方法などを詳しくヒアリングされます。
財産に関する資料があると、より具体的に話ができるでしょう。
銀行側から当日必要な資料の案内があれば、できるだけ準備して持参しましょう。
信託内容を設計・確認する
ヒアリング内容をもとに、信託の設計案を作成してもらいます。
「どの財産を、誰に、どれほど渡すのか」といった内容を明文化し、契約内容として作り上げます。
信託する内容は一人で決めず、家族とよく話し合いながら進めると、のちのトラブル防止にもつながります。
契約書を締結する
信託内容を十分検討し、設計案が出来上がれば正式な契約書を作成し、署名・押印して契約を締結します。
必要に応じて印鑑証明書や本人確認書類、財産関連の資料なども合わせて提出します。
銀行の指示に従いましょう。
一般的に契約時点で手数料が発生するため、金額や支払い方法についても確認しておきましょう。
死後、指定された人に財産が引き渡される
本人が亡くなった後、あらかじめ契約で定めた内容に基づいて、信託された財産が指定の受取人に引き渡されます。
遺言とは異なり、財産分配までの手続きが少なく、すぐに実行されるため、遺族の負担が軽いことがメリットです。
手続きにかかる期間
手続きは信託内容にもよりますが、相談から契約締結まで3週間~1カ月ほどで完了します。
契約が実行されるまでは数日から1週間程度と、スムーズに手続きが進みます。
| 手続きの段階 | 期間の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相談~面談 | 1週間~10日程度 | 対応できる銀行が限られるため、事前に確認が必要 |
| 設計~契約締結 | 1~3週間程度 | 一度作成すると、内容変更が難しいため慎重に確認する |
| 実行 | 数日~1週間程度 | 相続人が速やかに手続きを行う |
遺言代用信託にかかる手数料

信託契約を結ぶ際には、様々な手数料がかかります。
一般的に必要な費用は下記の通りです。
- 初期費用(契約時の一時金)
- 年間の管理費用(信託報酬)
- 解約時、実行時の費用
初期費用は信託する財産の内容や金額、契約の複雑さによって異なりますが、一般的には20万円~50万円前後が目安です。
金融機関によっては、財産評価額の0.5~1%を基準にしているところもあります。
信託財産を管理するための費用として、年間の報酬が発生し、これを信託報酬と言います。
信託報酬は数万円~10万円前後が一般的で、特別な契約内容があると増えることがあります。
信託期間が長期に渡る場合は、信託報酬が積み重なることを念頭に置いておきましょう。
信託契約が終了し、実際に受取人へ財産が引き渡される際には、所定の実行手数料がかかる場合があります。
また、途中で解約したい場合にも、手続きが複雑な場合は追加費用が発生することもあります。
解約は原則として難しいため、費用面も含めて契約は慎重に行いましょう。
遺言信託や家族信託と費用を比較すると、以下のようになります。
| 制度 | 初期費用の目安 | 年間の管理費 | その他 |
|---|---|---|---|
| 遺言代用信託 | 20~50万円 | 5000円~10万円 | 実行には別途手数料が必要 |
| 遺言信託 | 30~100万円 | 管理費が必要な場合も | 遺言執行が高額になる傾向 |
| 家族信託 | 10~30万円 | 不要 | 登記など専門家の助けも必要 |
まとめ
財産や相続に関することは「いつかやらなければ」と思いながらも、つい後回しにしてしまいがちです。
いざというときに慌てることや、家族が困ることのないように準備しておきましょう。
遺言代用信託は、準備さえしておけば、もしものときも落ち着いて対応できる安心のしくみです。
信託銀行や専門家に無料で相談できる機会も増えています。
あまりよくわからない、自分に合っているのか判断できない、といった場合もまずは一度相談してみましょう。