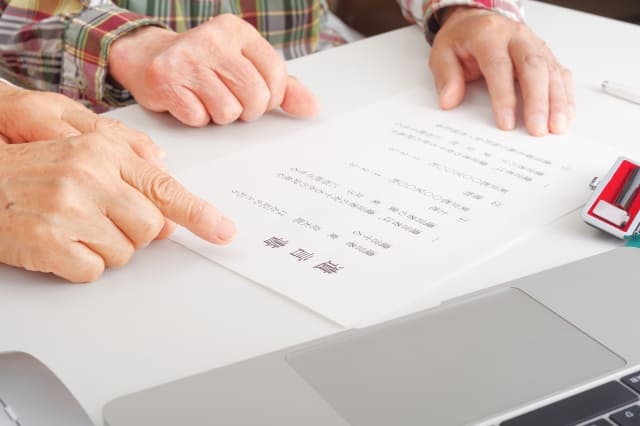この記事でわかること
- 代襲相続するケースと代襲相続しないケース
- 代襲相続によって起こりうるトラブル
代襲相続は、亡くなった親の代わりに孫や甥・姪が財産を受け取る制度です。
しかし、代襲相続を避けたい場合には、遺言書を作成して対策を取る必要があります。
本記事では、代襲相続の基本から遺言の具体的な書き方、よくあるトラブルについて解説します。
代襲相続するケース・しないケース
孫や甥・姪が代襲相続するケースと、しないケースがあります。
ここでは代襲相続とは何か、代表的な代襲相続するケース・代襲相続しないケースを紹介します。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人よりに先に死亡・相続欠格・廃除された場合に、その相続人の子が代襲して財産を相続する制度です。
代襲相続が発生した場合、相続分は親が受け取るはずだった相続分をそのまま相続し、代襲相続人が複数いれば、親が受け取るはずだった相続分を均分して相続します。
代襲相続するケース
代襲相続する代表的なケースを解説します。
相続人が先に死亡しているケース
相続人が被相続人よりも先に死亡していると、本来相続すべきだった相続人の財産を相続人の子が代襲相続します。
たとえば、被相続人の子が被相続人より先に亡くなった場合、被相続人の孫が代襲相続します。
孫も先に亡くなっていてひ孫がいれば、再代襲します。
更に先の代も同様に、再代襲は無限に続きます。
被相続人の妹が相続人というケースで、妹が先に死亡していると妹の子が代襲相続しますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りと決められています。
このため、被相続人よりも先に甥・姪も亡くなっていると、甥・姪の子には再代襲がないため、代襲相続できません。
相続人が相続欠格のケース
相続人が被相続人を殺害していた、遺言書の作成を妨げていた、あるいは遺言書を破棄・隠匿した場合は、相続欠格といい、相続人である権利をはく奪されます。
しかし、相続欠格の元相続人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続します。
相続人が廃除されたケース
推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしていた場合、被相続人は生前に、もしくは遺言書で家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求できます。
こちらも、廃除された元相続人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続します。
ただし、相続人廃除は遺留分を持つ推定相続人にのみ適用される制度のため、遺留分のない兄弟姉妹には適用されません。
相続人廃除で代襲相続が発生するのは、子・孫などの直系卑属に限られる点に注意が必要です。
代襲相続しないケース
一方、代襲相続しないケースもあります。
少しの違いで代襲相続する・しないが決まるため、要件を正確に理解しましょう。
被相続人の後に相続人が死亡したケース
相続人が被相続人より後に死亡したケースでは、相続人の相続人が相続し、この状態を「数次相続」と言い、代襲相続とは区別されます。
相続人が相続放棄したケース
相続人が相続放棄すると、すべての権利義務を放棄するため、相続開始時に遡って相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続は発生しません。
遺言書で指定された受遺者(遺贈を受ける人)が先に死亡しているケース
遺言書で指定された受遺者が被相続人(亡くなった方)より先に死亡していると、該当部分の遺言書は無効になるため、代襲相続は発生しません。
養子縁組前に生まれた養子の子ども
養親と養子の関係ができる前に生まれた養子の子どもは、養親との間に法律上の関係がないため、代襲相続する権利がありません。
一方、養子縁組後の養子の子どもは養親との法律上の関係が存在するため、代襲相続できます。
また、養子と実子の兄弟姉妹の関係も養子縁組によって発生するため、代襲相続については同様に判断がされます。
したがって、養子縁組前の甥・姪は代襲相続できず、養子縁組後の甥・姪は代襲相続できます。
代襲相続できない養子縁組前の養子の子ども(孫、甥、姪)に財産を残したい場合は、遺言書を作成して遺贈する、養子縁組するといった対策が必要です。
代襲相続のよくあるトラブル
代襲相続の遺産分割では、違う世代の相続人で話し合うために、遺産分割協議がうまくいかないことがあります。
ここでは、代襲相続の遺産分割でよくあるトラブルを紹介します。
世代の違う代襲相続人がないがしろにされる
被相続人の子どもと孫が相続人の場合、子ども世代同士では対等な立場で話していても、孫世代は子ども世代からすると甥・姪であり、軽く扱われて、ないがしろにされる場合があります。
縁遠くなった代襲相続人が遺産分割協議に参加しない
甥・姪・おじ・おばの関係で縁遠くなっており、連絡が取れない、遺産分割協議自体に参加したくないというケースもあります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、参加しない相続人がいると遺産分割協議そのものが止まってしまいます。
遺産分割協議に無理矢理参加させることはできないため、どうしても参加してくれない相続人がいる場合には遺産分割調停を申し立てるしかなく、遺産分割が長期化する恐れがあります。
代襲相続させない遺言書の書き方
ここでは、代襲相続させない遺言書の書き方を解説します。
「孫に代襲相続させたくない」遺言書は有効か無効か
亡くなった子どもとの関係が悪く、孫とは疎遠になっていると、孫に代襲相続させたくないというケースも考えられます。
孫に代襲相続させないという趣旨の遺言書は作成できませんが、他の相続人に財産をすべて相続させる遺言書を作成すれば、孫が代襲相続できなくなります。
ただし、孫には遺留分があるため、すべての財産を相続した相続人(受遺者)は遺留分減殺請求をされる恐れがあります。
遺言書で指定した対象者の代襲相続にも対応する遺言書
受遺者が、自分よりも先に亡くなる可能性も考える必要があります。
もし自分より先に亡くなっていると、該当部分の遺言書が無効になってしまい、無効部分については遺産分割協議が必要になるため、できれば避けたいところです。
このようなトラブルを避けるためには、自分よりも先に受遺者が死亡した時には受遺者の子どもが相続する、といった予備的内容を遺言書に盛り込んでおくと安心です。
代襲相続と遺言に関する注意点
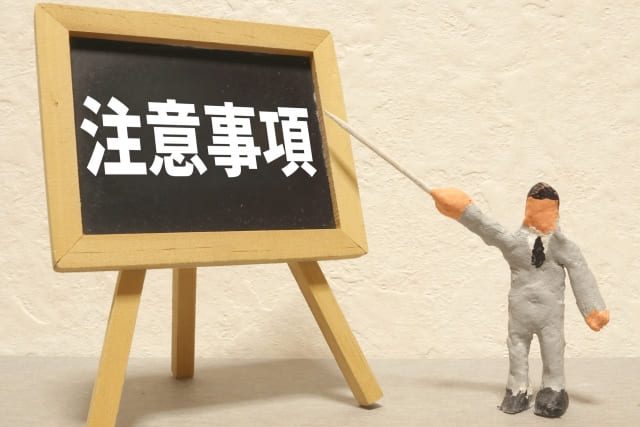
代襲相続の可能性がある場合の遺言には、注意点があります。
遺言書を公正証書で作成する
遺言書の効力、遺言書の内容について争いが起こる恐れがあるため、遺言書は信頼性の高い公正証書で遺す必要があります。
遺留分に注意して遺言を作成する
特定の誰かにすべての遺産を相続させるような遺言書を書く場合、推定相続人に遺留分を持つ相続人(配偶者、子・孫など)がいると遺留分減殺請求される可能性があるため、遺留分に見合う現金を遺贈する等、対策が必要です。
まとめ
孫や甥・姪に代襲相続させないためには、遺言書の作成が必要です。
相続人の中に代襲相続が発生していると、世代の差が原因でトラブルになったり、疎遠で連絡が取れずに遺産分割協議が進まなかったりと、問題が起こるかもしれません。
代襲相続が考えられる場合には、遺留分や特別受益などの問題にも対処できるように、弁護士など法律の専門家に相談した上で公正証書遺言を作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。