この記事でわかること
- 代表相続人の概要
- 代表相続人が行う手続き
- 代表相続人によるトラブル
家族の死亡で遺産相続が始まると、預貯金解約などの相続手続きも発生します。
相続手続きには不動産の名義変更や相続税申告なども含まれるため、代表相続人が手続きを進めるケースが一般的です。
代表相続人を決めると相続手続きは効率化されますが、「誰が代表相続人になる?」「どんな役割がある?」などの疑問も生じるでしょう。
難易度の高い相続手続きが発生したときや、相続財産の種類が多い場合は、代表相続人を複数選んだ方がよいかもしれません。
今回は、代表相続人になれる人や選び方、役割などをわかりやすく解説します。
目次
代表相続人とは
代表相続人とは、相続人が複数いるときの代表者となり、遺産の分配や相続手続きに対応する人です。
相続人代表とも呼ばれますが、法律に規定された地位ではないため、成人している相続人は誰でも代表相続人になれます。
複数の相続手続きが発生する場合は、各自が個別に対応するのではなく、代表相続人に手続きを任せた方がスムーズです。
なお、個別に相続手続きを進めたいときや、書類の収集・作成などを役割分担できれば、代表相続人を決めなくても問題はありません。
代表相続人の選び方
代表相続人を選ぶときは、以下の条件に該当する人がよいでしょう。
- 時間に余裕がある人
- 責任感がある人
- 信頼できる人
- 専門知識のある人
相続手続きは金融機関や行政機関などに出向くケースが多く、平日しか利用できません。
平日に仕事などで拘束されると相続手続きに対応できないため、代表相続人は時間に余裕のある人が適しています。
代表相続人は遺産の配分が完了するまで財産を預かるため、責任感や信頼感も求められます。
相続税が発生する場合は、財産評価や税額計算などの専門知識も必要でしょう。
弁護士や税理士などに相続手続きを依頼するときは、専門家とスムーズにやりとりできるかどうかも代表相続人を選ぶ基準となります。
なお、相続手続きが多くなると代表相続人に負担がかかるため、比較的年齢が若く、健康な人が適任です。
代表相続人が行う手続き
代表相続人になると、預貯金解約や相続登記などの手続きを行います。
遺言書があれば遺言内容に従って財産を分配しますが、なかったときは遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。
相続人同士の話し合いで代表相続人を決めたら、以下の相続手続きをスタートしましょう。
固定資産税の納税通知書の受け取り
相続財産に不動産がある場合、代表相続人が固定資産税の納税通知書を受け取ります。
固定資産税は1月1日~12月31日までが課税期間になっており、翌年の5月頃に納税通知書が登記名義人あてに送付されます。
被相続人(亡くなられた人)が一人暮らしだった場合、納税通知書が放置される恐れがあるため、固定資産税の未納につながりかねません。
代表相続人は自分の住所あてに納税通知書が届くよう、不動産を管轄する市町村役場に「相続人代表者指定届」を提出しておきましょう。
なお、相続開始と同時に不動産は共有状態になるため、各相続人は共有持分に応じて固定資産税を負担します。
代表相続人の役割は納税通知書の受け取りと、各相続人への通知のみです。
預貯金口座の解約と分配
代表相続人には被相続人の預貯金口座を解約し、解約金を分配する役割もあります。
各相続人が個別に手続きを進めても構いませんが、代表相続人が取りまとめると効率的です。
預貯金解約には以下の書類が必要になるため、金融機関の窓口やホームページから入手しましょう。
- 金融機関指定の相続手続依頼書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 解約する口座の通帳とキャッシュカード
解約金は振込みで受け取るケースが多いため、ひとまず代表相続人の口座で受け取り、各相続人への分配方法も振込みを利用するとよいでしょう。
各相続人へ解約金を分配しても、代表相続人の個人財産を渡すわけではないため、贈与税はかかりません。
相続税の申告
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税申告書は連名で提出できますが、相続人全員の同意があれば、代表相続人の名前で提出しても構いません。
代表相続人が一括して相続税を申告すると、手続きがスピーディになるため、申告期限にも十分間に合うでしょう。
相続税申告書の作成方法や税額計算がわからないときは、税理士に手続きの代行を依頼できます。
代表相続人が預金通帳や残高証明書、株式の取引残高報告書などをまとめておくと、税理士とのやりとりがスムーズになります。
不動産の相続登記
代表相続人になると、不動産の相続登記も一括申請する場合があります。
相続登記の申請先は不動産の住所地を管轄する法務局になっており、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続した人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 収入印紙(登録免許税の納付用)
相続財産が不動産に偏っており、公平な遺産分割ができない場合は、換価分割や代償分割などの解決方法もあります。
相続放棄などの手続き
相続放棄は基本的に個別対応ですが、代表相続人が家庭裁判所への申立てをまとめても構いません。
株式の名義変更や売却、自動車の名義変更や廃車手続きなども、代表相続人に手続を任せるケースがあります。
上場株式は証券会社が手続きを案内してくれますが、非上場株式があるときは、発行会社に問い合わせてみましょう。
事業承継による自社株相続であれば、顧問の税理士や会計士が相談に乗ってくれます。
代表相続人によるトラブル
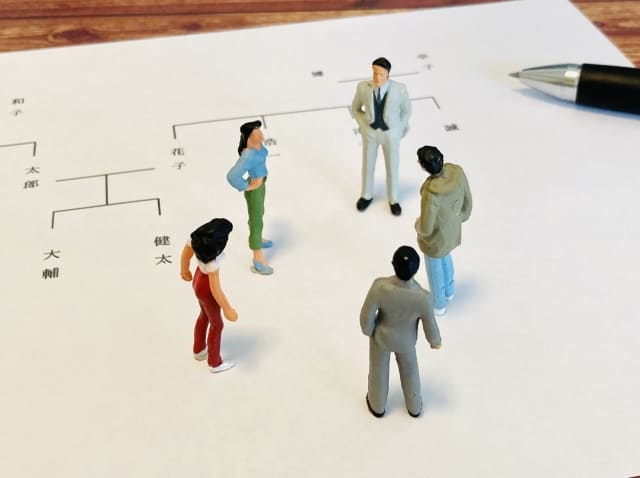
前述したように、代表相続人がいると相続手続きはスムーズになりますが、誰を選ぶかが重要です。
「被相続人と同居していたから」などの理由だけで代表相続人を選ぶと、以下のトラブルが発生するかもしれません。
相続トラブルは長期化しやすいため、安易な理由で代表相続人を決めないように注意してください。
代表相続人が相続財産を分配しない
相続人同士に対立関係が生じていると、感情的な理由から、代表相続人が財産を分配しないケースがあります。
財産が分配されないときは話し合いで解決を目指しますが、決裂した場合は遺産分割調停を検討しましょう。
遺産分割調停も話し合いによる解決手段ですが、調停委員が当事者の間に入ってくれるため、和解できる可能性があります。
なお、調停は裁判官による判決が出ないため、不成立になったときは訴訟が必要です。
訴訟の手続きは難易度が高く、口頭弁論にも対応しなければならないため、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
代表相続人が勝手に財産を処分する
代表相続人の倫理観や責任感が欠如している場合、勝手に相続財産を処分したり、自分の名義に書き換えたりする可能性があります。
相続人全員の同意がない手続きは無効になるため、勝手な財産処分などがあるときは、以下の方法で対処してください。
- 勝手に遺産分割された場合:遺産分割協議無効確認訴訟
- 預貯金や株式を勝手に処分した場合:不当利得返還請求または損害賠償請求
- 不動産を勝手に処分した場合:抹消登記の請求訴訟
勝手に相続放棄されたケースについては、本人の委任状がない限り家庭裁判所が申述を受理しても効力がないため、訴訟などの手続きは不要です。
まとめ
代表相続人を選任した場合、相続手続きが1人に集約されるため、預貯金の分配などがスムーズになるでしょう。
相続財産の預貯金を生活費に充てたいときや、不動産を早く売却したい場合は、代表相続人の選任をおすすめします。
なお、代表相続人になっても、相続財産を多めにもらえるわけではありません。
無償で相続手続きを進めなければならないため、責任感や信頼感が重視されます。
相続トラブルが発生している場合など、代表相続人の負担が重いときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。

























