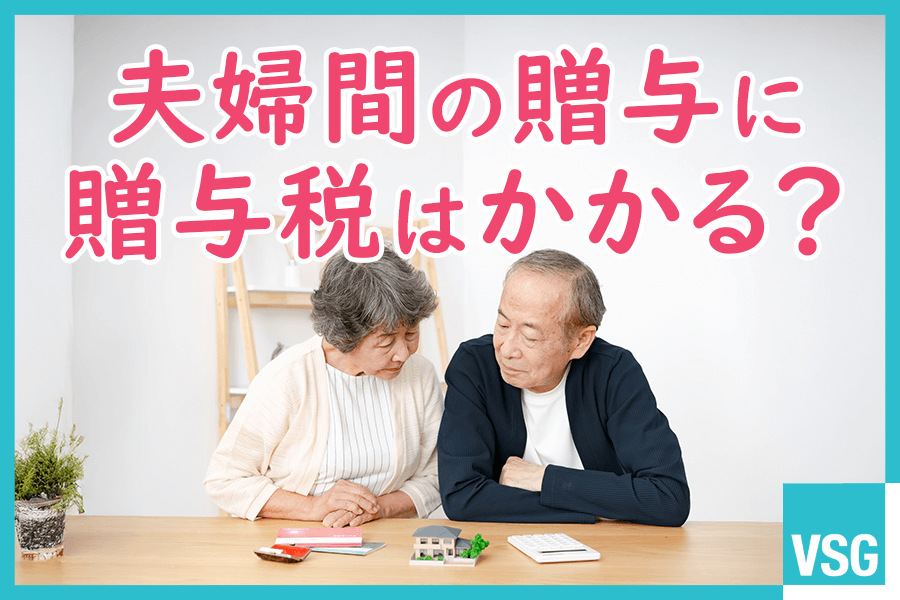この記事でわかること
- 夫婦間贈与の基本ルールと贈与税の仕組み
- 贈与税が非課税になる3つのケース(生活費・暦年贈与・おしどり贈与)
- 税務署に指摘されやすい2つの注意点(生前贈与加算・名義預金)
- 贈与税の申告手続きと贈与契約書の作り方
「相続が発生する前に自宅の所有権を配偶者に移しておきたい」
「将来のために、今のうちに預金の一部を渡しておきたい」
人生のさまざまな場面で、夫婦間のお金のやり取りは発生します。
そのたびに「これって『贈与』になるの?」「夫婦の間でも贈与税ってかかるんだろうか?」と不安に思ったことはありませんか?
普段の生活費のやり取りから、高価なプレゼント、そして不動産の名義変更まで。どこからが贈与税の対象で、どうすれば税金の負担を軽くできるのでしょうか。
ご安心ください。この記事が、あなたのそんな疑問や不安をすべて解消します。
この記事では、夫婦間の贈与税の基本原則から、贈与税がかからない3つの非課税ケースを具体例とともに徹底解説。
さらに、多くの人が知らないうちに陥ってしまう「名義預金」などの思わぬ落とし穴や、いざという時のための具体的な申告手続きまで、専門的な知識を誰にでもわかるように噛み砕いてお伝えします。
読み終えるころには、あなたの状況に最適な方法がわかり、安心して次の一歩を踏み出せるようになっているはずです。
目次
夫婦間の贈与でも原則、贈与税はかかる
結論から申し上げると、たとえ夫婦であっても、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合には原則として贈与税がかかります。
「家族なのにどうして?」と思われるかもしれませんが、贈与税は、財産を渡す人ともらう人の関係性にかかわらず、個人間の財産の無償のやり取りすべてを対象とする税金です。
法律上、「夫婦だから自動的に税金が免除される」という仕組みにはなっていないのです。
この年間110万円という金額は「基礎控除額」と呼ばれ、贈与税がかかるかどうかの一つのボーダーラインになります。
| 贈与された金額(年間) | 贈与税 | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 110万円以下 | かからない | 不要 |
| 110万円超 | 超えた部分にかかる | 必要 |
例えば、夫から妻へ年間で200万円の贈与があった場合、基礎控除額110万円を差し引いた90万円(200万円 – 110万円)に対して贈与税が課税されます。
このように、夫婦間であっても、基本的なルールは他人間の贈与と変わりません。
しかし、がっかりする必要はありません。
税制には、夫婦という特別な関係性を考慮した、大きな非課税の特例が用意されています。
次の章では、この原則を知った上で、賢く贈与をするための具体的な3つのケースを見ていきましょう。
夫婦間贈与で贈与税がかからない3つのケース
夫婦間の贈与には原則として贈与税がかかりますが、私たちの生活実態に合わせて、税金がかからないケースがあります。特に重要なのが、以下の3つのケースです。
ケース①:生活費や教育費の都度の支払い
夫婦や親子、兄弟姉妹など、お互いに扶養する義務がある者同士で、生活や教育のために必要なお金をその都度渡す場合は、贈与税の対象になりません。
これは「贈与」ではなく、「扶養義務の履行」とみなされるためです。
- 食費、家賃、光熱費など、日々の生活に必要なお金
- 配偶者や子の医療費、保険料
- 子の学費、塾や習い事の月謝、教材費
- 結婚式や出産にかかる費用
ここでのポイントは「その都度、必要な分だけ」という点です。
例えば、「子どもに大学4年間の学費や生活費として、まとめて1,000万円を渡す」といったケースは、扶養義務の範囲を超えているとみなされ、1,000万円を渡した年の末日の残額が贈与税の対象になります。
また、生活費として渡されたお金で配偶者が自分の名義で株式や不動産を購入したり、預金として貯め続けたりした場合も、その資金は贈与と判断される可能性があるため注意が必要です。
ケース②:年間110万円以下の「暦年贈与」
前の章で解説した年間110万円の基礎控除は、夫婦間の贈与でももちろん適用されます。これは「暦年贈与」と呼ばれ、最もシンプルで活用しやすい非課税の仕組みです。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、税務署への申告も不要です。
注意点:毎年繰り返す場合の「連年贈与」
毎年贈与をすることを「連年贈与」と言います。
毎年110万円ずつ贈与を繰り返すこと自体は問題ありません。
しかし、「10年間、毎年110万円ずつ、合計1,100万円を贈与する」という約束を最初から交わしていると、税務署から「定期金に関する権利の贈与(定期贈与)」とみなされ、初年度に1,100万円全額に対して贈与税が課せられるリスクがあります。
これを避けるためには、以下のような対策が有効です。
- 毎年、贈与の都度「贈与契約書」を作成する
- 贈与の金額を毎年少し変える(例:110万円、108万円、111万円など)
- 贈与の時期を毎年変える
ケース③:最大2,110万円まで非課税になる「おしどり贈与」
これは、長年連れ添った夫婦のための、非常に大きな非課税制度です。
「贈与税の配偶者控除」といいますが、「おしどり贈与」ともいわれます。以下の条件を満たせば、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円までの贈与が非課税になります。
つまり、最大で合計2,110万円までの財産を、税金なしで配偶者に贈与できる強力な制度です。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与される財産が、居住用の不動産(マイホーム)そのもの、または居住用不動産を取得するための資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に実際に居住しており、その後も住み続ける見込みであること
- 同じ配偶者からの贈与でこの制度を利用するのは、一生に一度であること
最重要:申告が必須です!
この特例の最大の注意点は、贈与税がゼロになる場合でも、必ず税務署へ贈与税の申告をしなければならない点です。
また、贈与税はかからなくても、不動産を贈与する場合、不動産の名義変更に伴う「登録免許税」や「不動産取得税」は別途かかります。
【要注意】夫婦間贈与で必ず知っておきたい2つの落とし穴
贈与税の非課税制度を理解していても、相続税の対象となってしまい税務署から指摘を受ける可能性のある、特に注意したい2つのポイントを解説します。
相続発生前7年以内の夫婦間贈与は生前贈与加算の対象になる
「毎年110万円ずつ贈与すれば、相続税対策も万全」と考えている方も多いかもしれませんが、注意が必要です。
もし贈与した側(贈与者)が亡くなった場合、亡くなる前7年以内に行われた贈与については、その金額を相続財産に足し戻して相続税を計算するというルールがあります。
これを「生前贈与加算」といいます。
これは「持ち戻し」と呼ばれますが、持ち戻しは贈与税の非課税額110万円以下の贈与であっても対象となります。
具体例
・この場合、亡くなる前7年間分の贈与、つまり合計770万円(110万円×7年)は、夫の本来の相続財産に加算されて、相続税が計算されることになります。
この制度は、亡くなる直前に財産を駆け込みで贈与して相続財産を減らすことで、不当に相続税を免れることを防ぐために設けられています。
せっかくの贈与が相続税対策としては無駄になってしまう可能性があるため、「相続税対策としての生前贈与はなるべく早くから計画的に始める」という視点が大切です。
ちなみに、前章で解説した「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」を利用した部分の金額は、この生前贈与加算の対象にはなりません。
専業主婦(主夫)のへそくりは「名義預金」として税務署に狙われる
これは夫婦間の贈与で最も税務調査の対象になりやすいケースの一つです。
「名義預金」とは、口座の名義人(例:妻)と、その預金を実質的に管理・所有している人(例:夫)が異なる預金のことを指します。
税務署は口座の名義だけで判断せず、「そのお金は本当は誰のものか?」という実態を見て判断します。
よくある「へそくり」のケース
・その後、夫が亡くなり相続が発生した際、税務署はこの1,000万円を「名義は妻だが、実質的な所有者は亡くなった夫の財産(名義預金)」と判断します。
・その結果、この1,000万円は妻のへそくりではなく、夫の相続財産として扱われ、相続税の対象となってしまいます。
夫から妻へ渡したお金を、税務署に正しく「妻固有の財産」と認めてもらうためには、「贈与が成立した」という証拠を残すことが重要です。
- 贈与契約書を作成する:年間110万円以下の贈与でも、お互いの意思確認として贈与契約書を交わしておくと非常に有効な証拠になります。
- 銀行振込で証拠を残す:手渡しではなく、夫の口座から妻の口座へ振り込むことで、お金の流れが明確な記録として残ります。
- 通帳や印鑑は妻が管理する:もらったお金が入っている口座の通帳や印鑑は、必ず妻自身が管理しましょう。夫が管理していると、夫のお金と判断される一因になります。
贈与税申告の手続き方法
贈与税の申告が必要になった場合でも、手順を理解していれば慌てる必要はありません。
ここでは、申告が必要なケースから、具体的な手続き方法、そして将来のための重要な備えまでを解説します。
贈与税の申告が必要なケースと申告期間
まず、どのような場合に申告が必要になるかを確認しましょう。
- 1年間(1月1日~12月31日)に、一人または複数人から合計110万円を超える財産の贈与を受けた場合
- 「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」の特例を適用する場合(納税額がゼロでも申告は必須です)
申告と納税を行うのは、財産をもらった側(受贈者)です。財産をあげた側(贈与者)ではないので注意しましょう。
申告と納税の期間
この期間内に、贈与税の申告書の提出と納税の両方を完了させる必要があります。
例えば、2025年5月10日に贈与を受けた場合は、2026年2月1日から3月15日の間に申告と納税を行います。
提出先は、財産をもらった人(受贈者)の住所地を管轄する税務署です。
申告書の書き方と提出方法
贈与税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。
最も便利なのは、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。画面の案内に従って入力するだけで、税額が自動計算され、申告書を印刷したり、そのまま電子申告(e-Tax)したりすることができます。
- e-Taxで電子申告:マイナンバーカードと対応スマートフォン(またはICカードリーダライタ)があれば、自宅からオンラインで提出できます。
- 郵便または信書便で送付:管轄の税務署宛に郵送します。
- 税務署の窓口へ持参:管轄の税務署に直接持っていき、窓口で提出します。
なお、「おしどり贈与」を利用する場合は、申告書に加えて、受贈者の戸籍謄本、戸籍の附票の写し、贈与された不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書(金銭贈与を受けた場合は売買契約書、領収書などの写し)など、いくつかの添付書類が必要になります。
不動産の贈与の場合、家屋や土地の評価をする必要があります。
評価方法は相続税を計算するときと同様に、財産評価基本通達に基づいて評価します。
家屋は固定資産評価額、土地は路線価地域と倍率地域で評価の仕方が異なります。評価方法がわからない場合は税理士に相談しましょう。
【重要】申告が不要な贈与でも贈与契約書などの証拠を残す
年間110万円以下の贈与で申告が不要な場合でも、「贈与契約書」という形で、贈与があったことの証拠を必ず残しておくことを強く推奨します。
「なぜ申告が要らないのに、わざわざ契約書を?」と思うかもしれませんが、これには2つの重要な意味があります。
- 「名義預金」を否定する証拠になる:将来、相続が発生した際に、税務署から「これは名義預金ではないか」と疑われた場合、「これは正式に贈与された私の財産です」と証明する客観的な証拠になります。
- 「定期贈与」を否定する証拠になる:毎年贈与を繰り返す場合、それぞれの贈与が独立したものであることを証明し、「最初からまとまった金額を贈与する約束だった」とみなされるリスクを回避できます。
贈与契約書に決まった形式はありませんが、以下の項目を記載した書面を2部作成し、夫婦それぞれが保管しておきましょう。
- 誰が(贈与者)、誰に(受贈者)
- いつ
- 何を(例:現金100万円)
- どのようにして(例:〇〇銀行の口座へ振り込む)
- 贈与したこと
お互いの署名と捺印があれば、法的に有効な証拠となります。押印は認め印でもかまいませんが、署名は本人の意思であることを明確に残すために自筆にしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1:専業主婦(主夫)のへそくりは贈与税の対象になる?
「へそくり」そのものが贈与税の対象になることは稀です。問題となるのは、贈与税ではなく、将来の相続税です。
稼ぎ手である夫の収入から生活費を受け取り、それを節約して貯めた「へそくり」は、税務上、妻固有の財産ではなく「夫の財産を、妻名義の口座で管理していたもの(名義預金)」と判断される可能性が高いです。
その場合、夫の相続が発生した際に、そのへそくりは夫の相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。これを避けるには、贈与契約書を作成するなど、財産が正式に「贈与」されたものである証拠を残しておくことが重要です。
Q2:自宅マンションの名義を配偶者にした場合、贈与に該当しますか?
はい、原則として贈与に該当します。
自宅マンションの購入代金を夫が全額支払ったにもかかわらず、所有者の名義を妻として登記した場合、夫から妻へ「自宅マンションそのもの」の贈与があったとみなされます。
6,000万円の自宅マンションを購入し、住宅ローン負担額が夫が5,000万円、妻が1,000万円の場合、登記するときの夫の持ち分が6分の5、妻の持ち分が6分の1と、住宅ローン負担額と一致していれば贈与とはなりません。ここで、すべてを夫の持ち分として登記すると、夫が妻から1,000万円の贈与を受けたことになります。
おしどり贈与を適用したい場合、自宅マンション購入資金を贈与するか、自宅マンションを夫名義で購入後、後日妻へ持ち分の贈与をする方法が考えられます。
Q3:住宅は生前贈与と相続どちらがお得?
一概には言えませんが、税金の負担だけを考えると、多くの場合で「相続」のほうが有利になる傾向があります。
生前贈与の場合、「おしどり贈与」を使えば、基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税を非課税にできますが、相続による取得では課税されない不動産取得税が課税され、登録免許税は相続よりも高い税率が課されます。
一方、相続の場合は、配偶者が取得する財産額が法定相続分または1億6,000万円までであれば相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という非常に大きな特例があります。
さらに、相続による不動産の取得に不動産取得税はかからず、登録免許税の税率も贈与より低く設定されています。
ただし、ご家庭の資産状況や将来の計画によって最適な選択は異なります。どちらが良いか迷った場合は、税理士などの専門家に相談し、シミュレーションをしてもらうことをお勧めします。
Q4:夫婦間で相続時精算課税制度は利用できますか?
いいえ、利用できません。
相続時精算課税制度は、原則として贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫という、直系の親族間での贈与に限定された制度です。
夫婦はこれに該当しないため、この制度を利用することはできません。
まとめ
この記事では、夫婦間の贈与税に関する基本ルールから、3つの非課税ケース、そして思わぬ落とし穴とその対策までを網羅的に解説しました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 原則、夫婦間でも年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる
- 「①生活費・教育費」「②暦年贈与」「③おしどり贈与」の非課税枠を賢く活用しよう
- 税務署に「名義預金」とみなされないために「贈与契約書」で証拠を残すのが最重要
- 贈与は相続とも密接に関係するため、長期的な視点で計画することが大切
少しでも不安や疑問が残る場合、または高額な不動産贈与などを検討している場合は、ご自身だけで判断せず、財産を動かす前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家はあなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。当事務所は初回相談無料となっています。お気軽にご相談ください。
この記事が、あなたの大切なご夫婦の資産形成の一助となれば幸いです。