

東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。
労働問題は、一歩対応を誤れば損害賠償だけでなく、企業の信用失墜や従業員の士気低下、ひいては経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。
私は、野村證券をはじめとする金融機関で10年以上にわたり、リテール営業からコンサルティング、金融庁との折衝やリスク管理まで、多方面の業務に従事してまいりました。これらの経験から、企業の数字と法務は密接にリンクしており、労働問題を「点」ではなく「経営の一部」として捉えることの重要性を痛感しております。
経営者側の立場に立ち、財務分析や資金調達の観点も含めた戦略的なアドバイスを行うことが私の強みです。単に紛争を解決するだけでなく、組織の持続的な発展を見据えた強固なガバナンス構築のお手伝いをいたします。経営者の皆様の良き相談相手として、誠実かつ論理的にサポートさせていただきます。
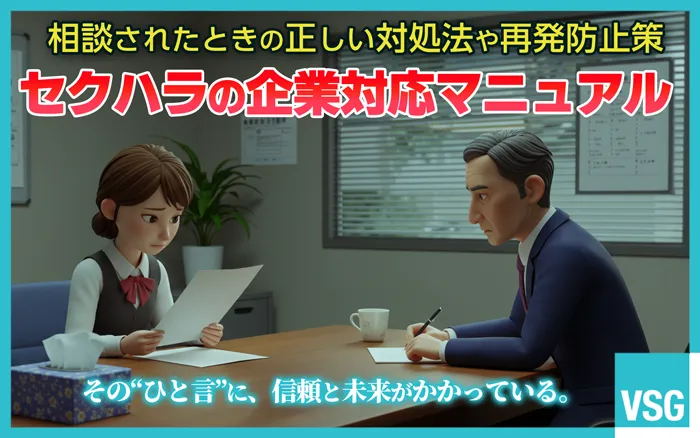
この記事でわかること
セクシャルハラスメント(セクハラ)は、従業員の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても法的責任や社会的信用の失墜といった重大なリスクをもたらします。近年では、職場における人権意識の高まりやSNSによる情報拡散の影響もあり、企業の対応姿勢が厳しく問われるようになっています。
セクハラの相談を受けた企業には、迅速かつ公正な対応が求められます。しかし実際の現場では、「どこまで調査すべきか」「被害者や加害者への対応はどうするべきか」など、判断に迷う場面も少なくありません。対応を誤れば、被害の深刻化や再発、ひいては訴訟リスクにもつながりかねません。
この記事では、セクハラ発生時の初動対応から、再発防止策、企業が負う法的責任までを弁護士がわかりやすく解説します。従業員が安心して働ける職場環境を整えるために、企業として今できることを確認しておきましょう。
目次
セクハラとは、職場での性的な言動により、相手に不快感や不利益を与える行為を指します。受け手が不快と感じれば、加害者の意図に関係なく問題となり、企業には速やかな対応と再発防止策が求められます。
セクハラは、その内容や影響に応じて「環境型セクハラ」と「対価型セクハラ」の2つに分類されます。企業が適切に対応するためには、それぞれの特徴を正しく理解することが不可欠です。
環境型セクハラとは、性的な言動によって職場の雰囲気が悪化し、働きづらくなる状況を指します。相手に直接的な不利益を与えていなくても、就業環境が損なわれればセクハラと判断されることがあります。
たとえば、以下のような行為が該当します。
こうした行動が続くと、被害者だけでなく周囲の従業員にとっても職場が不快な場所になり、生産性やチームワークに悪影響を及ぼします。
対価型セクハラは、性的な要求と引き換えに、昇進・人事異動・業務上の評価などを絡めて利益や不利益を与える行為です。とくに上司などの地位を利用した圧力が伴うことが多く、深刻な人権侵害につながります。
以下のような行為が代表例です。
このような事例では、加害者個人だけでなく、対応を怠った企業にも責任が問われる可能性があります。被害者は心理的にも立場的にも拒否しづらいため、周囲が気づいた時点で介入することが重要です。
企業が対応する際には、客観的な視点も含めて、総合的にセクハラかどうかを判断する必要があります。判断基準としては、主に以下の4つが挙げられます。
最も重要なのは、被害を受けた本人がその言動に対して精神的に苦痛や不安、不快感を覚えたかという点です。行為者が「軽い気持ちだった」「悪気はなかった」と言っても、被害者が嫌だったと感じていれば、それだけで問題となります。
言動の内容が、社会一般の常識から見て明らかに不適切であるかどうかも判断の材料になります。職場という公的な場では、性的な冗談や身体的接触は容認されないと考えるのが通常です。たとえば、「女性なんだからお茶を出してよ」といった発言や、プライベートな身体的特徴に関するコメントは、社会的にも不適切とされる傾向があります。
単発の言動であっても、内容が悪質であればセクハラと認定されることはありますが、同様の行為が繰り返されている場合、より深刻に受け止められます。とくに、被害者がやめてほしいと意思表示しているにもかかわらず継続されている場合は、明確なハラスメントと判断されます。
セクハラによって被害者が出勤をためらったり、職場で孤立したり、業務に集中できなくなるなど、就労環境が損なわれている場合は、企業としても見過ごせません。放置すれば、メンタル不調や退職といった深刻な事態につながる可能性もあります。
以上の基準を踏まえ、企業としては一方の言い分だけを鵜呑みにせず、事実関係を丁寧に確認する姿勢が求められます。対応を誤ると、被害の拡大や企業の法的責任につながるリスクもあるため、慎重かつ迅速な対応が重要です。
セクハラの申し出があった際、企業は迅速かつ適切な対応をとる義務があります。まずは事実確認と環境整備を行い、被害者の安全と尊厳を守る姿勢を示すことが重要です。以下では、初動から対応の各ステップについて解説します。
被害を申し出た本人と加害者の双方から個別に事実確認を行います。このとき、誰かを一方的に信じるのではなく、中立な立場で聞き取りを進めるのが基本です。発言の真偽に偏りがある場合もあるため、感情的にならず、冷静に情報を整理する必要があります。
また、聞き取りはプライバシーに配慮した場所で行い、相手に安心感を与える配慮も欠かせません。事実関係の把握はその後の対応方針を決めるうえで極めて重要です。
事実確認とあわせて、やり取りの記録や証拠を保存しておくことが重要です。証拠となるのは、被害者のメモ、メール、チャットのスクリーンショット、防犯カメラ映像、周囲の証言など多岐にわたります。
これらの資料は、社内での懲戒処分の判断や、万が一の法的トラブル時の根拠として機能します。聞き取りの内容も、日付や発言を明確にした調書として残しておくことで、後の対応において曖昧な記憶に頼るリスクを避けられます。
被害者は、申し出を行うだけでも大きな精神的エネルギーを使っています。企業としては、事実確認だけでなく、その後のメンタルケアにも配慮する必要があります。産業医や社内外のカウンセラーを紹介したり、必要に応じて一時的な業務負担の軽減を検討したりすることも有効です。
また、被害者が報復を恐れて黙ってしまわないよう、相談内容の秘密を守り、今後も安心して働ける環境を約束する姿勢が求められます。
セクハラの調査中や調査後に、被害者と加害者が顔を合わせる状況が続くと、被害者のストレスが強くなり、二次被害につながるおそれがあります。そのため、可能な限り早急に配置転換や勤務時間の調整などを行い、当事者の接触を回避する工夫が必要です。
加害者を一時的に別部署に異動させる、あるいは在宅勤務を導入するなどの措置も有効です。企業は被害者の安全確保と働きやすい環境の再構築を優先すべきです。
セクハラが原因で、被害者が異動・降格・仕事からの排除といった不利益な取り扱いを受けている場合、企業は直ちにその対応を見直す必要があります。こうした行為は「二次被害」にあたり、企業の責任がより厳しく問われることになります。
過去の人事記録や処遇の経緯を確認し、正当性のない処分であれば速やかに撤回・是正することが求められます。また、今後同様のことが起きないよう、社内への周知や仕組みの見直しも必要です。
セクハラの対応を誤ると、被害者の精神的ダメージが増すだけでなく、企業自身が法的責任や社会的批判を受けるリスクが高まります。以下では、企業が避けるべきNG対応について具体的に解説します。
被害の申し出に対して「気にしすぎ」「冗談だろう」などと軽視する対応は絶対に避けるべきです。このような対応は、被害者に二重の傷を与えるだけでなく、ほかの従業員にも「相談しても無駄だ」というメッセージを与えてしまいます。
企業としては、被害を申し出た事実そのものを重く受け止め、真摯に対応する姿勢を示す必要があります。否定や無視ではなく話を丁寧に聞く姿勢こそが、従業員から信頼される企業の第一歩です。
セクハラの訴えを受けても十分な調査を行わず、曖昧なまま済ませてしまう対応は、企業としての責任を果たしていません。「大ごとにしたくない」「面倒だから」といった理由で調査を避けると、問題は表面化せず、被害者だけが苦しむ結果になります。
たとえ加害者が否定していても、客観的な事実に基づいた丁寧な聞き取りや証拠の確認が不可欠です。適切な調査体制を整えておくことが、企業リスクを防ぐカギとなります。
加害者が上司や経営陣などの立場にある場合、社内の力関係によって被害の調査や対応が不公正になるケースがあります。「上司だから波風を立てたくない」といった理由で加害者に甘い処分を下すことは、被害者の信頼を大きく損ねるだけでなく、社内の公平性そのものを揺るがします。
誰が当事者であっても、企業は中立・公平な立場で判断しなければなりません。公正な対応こそが組織全体の信頼を支えます。
問題が表面化することを恐れて、セクハラを見て見ぬふりしたり、「他言無用」と被害者に口止めしたりする行為は、企業にとって最悪の対応です。このような隠蔽体質は被害の拡大を招くだけでなく、企業の責任を重大化させます。
実際、セクハラの二次被害として「相談したら怒られた」「異動させられた」といった事例も少なくありません。企業は真摯に向き合い、問題を正面から受け止める姿勢が求められます。

セクハラ問題は一度の発生で従業員の信頼を損ない、企業の社会的評価を大きく下げるリスクがあります。そのため、事後対応だけでなく、事前の防止策が不可欠です。就業規則や相談体制の整備、社員教育など、継続的な取り組みを通じて、セクハラを起こさない職場づくりを目指しましょう。以下に具体的な対策項目を紹介します。
セクハラを防止するには、就業規則や社内規程に明確なルールを定めることが基本です。「どのような行為がセクハラに該当するのか」「違反した場合の懲戒処分」などを明文化し、全従業員が確認できるようにします。
規程は定期的に見直し、社会的な動向や法改正に対応させることが重要です。就業規則への明記は、企業としての姿勢を示すだけでなく、万一の際の説明責任にもつながります。
また、経営層がセクハラを許容しない方針を明言し、トップダウンでメッセージを発信することも再発防止につながります。
セクハラの早期発見と適切な対応には、社内に相談窓口を設けることが不可欠です。人事部門とは別の独立性のある窓口を設置することで、被害者にとって相談のしやすさが高まります。
相談に対しては、迅速かつ丁寧な対応が求められるので、専任担当者の教育やフローの整備も必要です。また、相談件数や傾向を定期的に集計・分析することで、予防施策にも活かすことができます。
相談者が安心して声を上げられるよう、相談内容や当事者のプライバシーが厳格に保護される体制を整えることが求められます。第三者への情報漏えいや、当事者の特定につながる情報の扱いには特に注意が必要です。
関係者以外には一切情報を開示しない旨を事前に伝えることで、相談のハードルを下げる効果があります。プライバシーへの配慮は、職場全体の信頼醸成にもつながります。
一度きりの研修では、セクハラに対する意識は定着しません。企業は、管理職と一般従業員の両方に向けて、定期的な研修を行う必要があります。
管理職向けには相談対応や初動の判断を中心に、従業員向けには日常業務での注意点やマナーの再確認を行います。動画教材やケーススタディを用いると理解が深まりやすくなります。
繰り返しの教育を通じて、ハラスメントを許容しない職場文化が育まれます。
従業員の本音を把握する手段として、匿名でのハラスメント調査やパルスサーベイ(意識調査)が有効です。相談が上がらない職場でも、問題が潜在化しているケースは少なくありません。定期的なアンケートにより、問題の兆候を早期に把握し、未然に対応できます。
調査結果は集計し、必要に応じて改善策を講じることで、職場の安全性と透明性が高まります。
リモートワークが浸透した現在、オンライン上のセクハラ(リモートハラスメント=リモハラ)にも注意が必要です。Web会議中の不適切な発言、私的な連絡ツールの強要、業務時間外の連絡によるストレスなどが問題となり得ます。
これらの行為を未然に防ぐため、オンライン業務におけるルールを明文化し、従業員への教育を行いましょう。テレワークでも安心して働ける環境整備が不可欠です。
セクハラが発生した際、加害者だけでなく、対応を怠った企業にも法的責任が問われる可能性があります。ここでは、被害者・加害者それぞれに対する責任、さらに企業自体が負う社会的リスクについて解説します。
企業には、職場での安全と安心を確保する「使用者責任」があります。これは、従業員が働くうえで不利益を被らないよう配慮する法的義務です。セクハラの被害者が精神的苦痛を受けた場合、企業が適切な対応を取らなければ、安全配慮義務違反として損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、被害申告後の報復や不利益な取り扱いがあった場合には、二次被害として企業責任がさらに重く評価されます。初動の誤りが深刻な結果を招くこともあるため、丁寧な対応が不可欠です。
企業が加害者を処分する際には、就業規則に基づいた適正な手続と慎重な判断が必要です。セクハラを理由に即座に解雇することは、状況によっては「解雇権の濫用」とされ、後に解雇無効と判断されるリスクがあります。その場合、加害者を職場に復帰させるだけでなく、解雇期間中の未払い賃金を補償しなければならない可能性もあります。
また、セクハラを理由に氏名や内容を過度に公表すると、名誉毀損として加害者から損害賠償請求を受けるおそれもあります。
企業は懲戒処分の必要性を慎重に検討しつつ、手続の公正性と秘密保持を徹底することが求められます。
セクハラ問題が報道やSNSで拡散されると、企業のブランドや信用に深刻なダメージを与える可能性があります。「ハラスメントに甘い企業」という印象が定着すれば、顧客離れや採用難、人材の流出につながります。
また、労働局からの是正勧告や公表処分を受けるケースもあります。こうしたリスクは一度表面化すると長期にわたり影響を残すため、平時から社内体制を整備し、トラブルの未然防止と早期対応が重要です。
セクハラが発生した場合、企業が適切に対応するには法的観点からの判断が欠かせません。対応を誤ると、損害賠償請求や名誉毀損、解雇無効といったトラブルに発展する可能性があるため、早い段階で弁護士に相談することが有効です。
弁護士は、聞き取りや処分の妥当性、公表範囲、被害者保護のあり方などを法的に助言でき、企業のリスクを最小限に抑えるサポートをしてくれます。第三者である専門家の視点を取り入れることで、公正かつ適切な対応が可能になります。
はい。企業には職場環境を整える義務があり、セクハラの相談があった場合、調査を行わなければなりません。たとえ被害者が「大ごとにしたくない」と話しても、事実確認を怠れば、企業の安全配慮義務違反とされる可能性があります。
加害者が否定している場合でも、企業は中立的な立場で事実関係を調査しなければなりません。一方の主張だけを信じて判断するのではなく、メールや会話の記録、周囲の証言など客観的な証拠をもとに対応を検討することが重要です。
調査の結果、違反の事実が確認できれば、就業規則に沿って適切な処分を行う必要があります。
処分の内容は、行為の内容・悪質性・継続性などを踏まえて判断します。注意・減給・出勤停止・降格など段階的な対応が考えられますが、重大な違反であれば懲戒解雇も可能です。
ただし、手続きや証拠が不十分なまま懲戒処分を行うと「解雇無効」と判断されるリスクがあるため、慎重な判断と公正な手続きを行うことが不可欠です。
被害者の同意があれば、異動は選択肢の一つですが、本人の意思に反して異動を命じるのは適切とはいえません。本来は、加害者側に対して配置転換や勤務時間の調整を行うなど、被害者が安心して働ける環境を整えることが優先です。被害者を「問題のある側」として扱うような対応は二次被害につながるため、慎重に対応する必要があります。
被害者が「調査は不要」と話す場合でも、企業には事実確認を行う責任があります。被害が潜在化したままだと、再発や職場全体への影響が広がる可能性があるため、最低限の事実確認と再発防止策の検討は欠かせません。被害者の意思は尊重しつつも、安全配慮義務を果たすために、適切な形で調査や対応を進める必要があります。
セクハラ問題は、個人だけでなく組織全体に深刻な影響を与える問題です。被害を申し出た従業員が安心して働き続けられる環境を守るためには、迅速で公正な対応が不可欠です。対応を誤れば、二次被害や法的トラブル、社会的信用の失墜にもつながります。
企業には、相談体制の整備、就業規則の見直し、継続的な研修といった再発防止策が強く求められます。表面的な処理で済ませず、真摯に向き合う姿勢こそが、信頼される組織をつくる土台となります。
「VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。