

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務
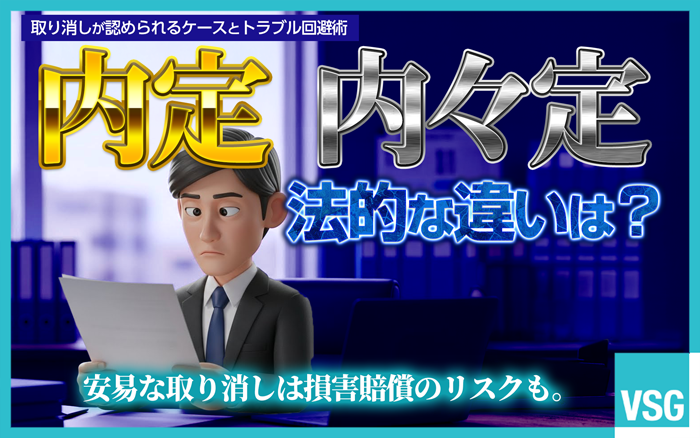
企業の採用活動では、優秀な人材を確保するために「内々定」や「内定」を出すことが一般的です。これらは同じように扱われがちですが、法的な位置づけや取り消しの可否には大きな違いがあります。対応を誤れば、不当な内定取り消しと判断され、企業が損害賠償請求を受けたり、社会的信用を失うリスクが生じかねません。
特に、内定は労働契約が成立しているとみなされる場合が多いため、簡単に取り消すことはできません。一方で内々定は比較的柔軟な運用が可能ですが、学生に過度な拘束を課したり、曖昧な対応をしたりすると、やはりトラブルにつながります。
本記事では、内定と内々定の違いを整理したうえで、取り消しが認められるケースと問題になりやすい場面を具体的に解説します。
目次
採用活動では「内定」と「内々定」という言葉が頻繁に使われますが、両者は法的な意味合いや企業に課される責任に大きな違いがあります。ここでは、企業が知っておくべき両者の定義と実務上の扱いについて整理します。
内定とは、企業と応募者が入社に向けて最終的に合意した段階を指します。法的には「始期付解約権留保付労働契約」にあたり、入社日という始期が定められ、その日までに特別な事情があれば契約を解約できる余地を残した契約形態です。
内定が出た時点で労働契約は成立しているとみなされる場合があるため、企業は基本的に応募者を労働者として受け入れる義務が生じます。
内々定とは、企業が応募者に対して採用の意思を非公式に示した段階を指します。労働条件や入社日が明確に定まっていないことが多く、一般的には労働契約の成立とはみなされません。
ただし、応募者が他社への応募を取りやめるなどの行動を取った場合や、企業が代表者名義で通知書を交付するなど内定に近い対応を行った場合には、信義則上、企業に一定の責任が生じることもあります。
内々定は企業にとって柔軟に運用できる一方で、応募者に過度な期待を抱かせたり拘束を課したりすると不当な取り消しと判断されるおそれがあります。そのため、通知書や説明会の段階で位置づけを明確に伝え、正式な内定との違いを説明することがトラブル防止につながります。
採用活動の現場では、やむを得ず内定や内々定を取り消さざるを得ない場面が出てくることがありますが、その法的な扱いは両者で大きく異なります。企業が違いを正しく理解していなければ、不当な取り消しとされるリスクがあります。
内定は、企業と応募者との間で労働契約が成立していると評価される場合があるため、取り消しは「解雇」と同じ扱いとして慎重に判断されます。そのため、企業が一方的に取り消すことはできず、客観的に合理的な理由が存在し、さらに社会通念上も相当とみなされる場合に限って許されます。
客観的に合理的な理由としては、応募書類に重大な虚偽があった場合、卒業要件を満たせず入社できなくなった場合、あるいは健康上の問題によって職務遂行が著しく困難と判断される場合などが典型です。これらの事情は、入社を前提とした関係を根本から覆すものと考えられるため、内定取り消しが認められる可能性があります。
一方で、業績不振や人員調整といった企業都合での取り消しは、客観的合理性を欠くと判断されやすく、不当解雇と同様に違法とされるリスクが高いです。実際の裁判例でも、経営悪化を理由に内定を取り消したケースでは正当性が否定され、損害賠償を命じられた例があります。
内々定は、一般的に労働契約の成立とまでは評価されない場合が多いため、企業側が取り消す自由度は比較的高いといえます。入社日や労働条件が正式に確定していない段階であることから、内定ほど厳格な制約は課されません。
ただし、応募者が内々定を信頼して他社への応募を控えたり、進路を固定してしまった場合には、信義則上の保護が働くと判断される可能性もあります。そのような場合、安易な取り消しが不法行為と評価されるリスクがあるため注意が必要です。
内定や内々定を取り消す場合、その妥当性が法的に問題となることがあります。
内定は条件付きながらも労働契約が成立していると評価される場合があるため、取り消しには厳格な要件が求められます。最高裁も大日本印刷事件(最判昭和54年7月20日)において、内定取消が有効とされるためには「採用内定当時に知ることができず、また知ることも期待できなかった事実」であり、かつ「それを理由とした取消しが客観的に合理的で、社会通念上も相当である」必要があると示しています。
具体的には、長期間にわたる無断欠席や連絡の途絶、提出書類の継続的な遅延、さらには行事を欠席して私的旅行に行っていたなど正当な理由のない行動が判明した場合などは、内定取り消しが合理的な理由として認められる可能性があります。とくに、こうした事由が内定通知書や誓約書に「取消事由」として明示されていれば、取り消しの正当性は一層高まります。
一方で、企業の経営悪化を理由に内定を取り消す場合には注意が必要です。判例・学説上は、いわゆる「整理解雇の法理」に準じた検討が求められるとされています。
【整理解雇の4要件】
① 人員削減の必要性
② 解雇を回避する努力
③ 人員選定の合理性
④ 解雇手続の妥当性
既存の従業員と比べれば内定者は企業との結びつきが弱いため、内定取消が比較的優先されやすい立場にはありますが、それでも安易な取り消しは許されないことに注意が必要です。
内々定の取り消しが問題になるかどうかは、内々定が労働契約として成立していると評価できるかに左右されます。
判断の基準は、最終的に企業と応募者の意思表示の内容に依拠します。企業が通知を行った時点で労働契約を締結する意思を持っていたか、あるいは応募者が通知を信頼して他社への応募を辞退するなど進路を固定する行動を取っていたか、といった事情が重要な判断材料となります。これらの事実関係が積み重なることで、裁判所が「実質的に労働契約が成立している」と認定する可能性もあります。
もっとも、一般的には内々定の段階ではまだ労働契約は成立していないと解釈されることが多く、そのため企業側は比較的自由に取り消すことができます。たとえば、学生からの連絡が途絶えている場合や、求められた書類の提出がないといったケースでは、内定取り消しと比べて法的リスクは低いと考えられます。
内定や内々定を出したあとの対応次第で、後にトラブルへ発展するかどうかが大きく変わります。企業側が一方的に義務を課したり、不適切な理由で取消しを行ったりすれば、法的責任や企業の信用失墜リスクを負うことになりかねません。ここでは、採用活動を円滑に進めるために注意すべきポイントを確認します。
企業は、内々定者や内定者に対して最低限の対応義務を求めることができます。たとえば「一定期間内に連絡すること」や「提出期限までに必要書類を提出すること」といったルールを明示し、従わない場合には内々定の見直し対象となることを事前に伝えておけば、一定の拘束力を持たせることが可能です。
また、労働契約の効力が入社日前に生じていると解される場合であっても、「就労を前提としない準備行為」に限って義務付けを行うことが適切です。具体的には、履歴書や卒業見込証明書などの書類提出、研修や施設見学への参加、定期的な近況報告や連絡対応などが含まれます。これらに正当な理由なく応じない場合は、内定取消の事由として評価される余地があります。
ただし、義務付けが過度になると「労働契約がすでに成立している」と判断されるリスクを高めたり、学生に過大な負担を与えたりする可能性があります。たとえば、就業前に長期間の拘束を伴う研修や、大量の課題提出を強制するような対応は、合理性を欠くと見なされかねません。
企業としては、採用活動を円滑に進めるために最低限必要な範囲にとどめ、義務の目的や内容を明確に説明することが重要です。
内定者や内々定者が必要書類を期限までに提出しなかったり、説明会や研修を無断で欠席したりすることは、企業にとって不安材料となります。しかし、これを直ちに内定取消の理由とするのはリスクが高く、慎重な判断が求められます。
たとえば、書類提出の遅れが一時的なものに過ぎない場合や、欠席に合理的な理由(学業や体調不良など)がある場合には、取り消しの正当性は認められにくいです。一方で、長期間にわたって連絡が途絶えている、正当な理由なく何度も提出物を無視している、あるいは私的な理由で繰り返し行事を欠席しているといった場合には、取消事由として評価される可能性が出てきます。
企業としては、まず状況を確認し、本人に説明や改善の機会を与えることが望ましい対応です。そのうえで、合理的な理由がなく改善も見込めない場合に限って、取り消しを検討するのが適切といえます。
内定によって労働契約の効力がいつ発生するかは、企業の対応を大きく左右する重要なポイントです。一般的には「入社日から効力が発生する場合」と「内定通知の時点で効力が発生するとされる場合」の2つに分けて考えられます。
効力が入社日から生じるとされる場合には、その時点までは労働契約上の義務は発生しません。そのため、研修参加や提出物などの義務付けは強制できず、従わなかったことを理由に内定を取り消すのは難しいといえます。
一方で、内定通知の時点で効力が発生していると評価される場合には、就労準備に必要な範囲に限り、一定の義務付けが認められます。具体的には、履歴書や卒業見込証明書などの書類提出、施設見学や研修への参加、近況報告などが該当します。こうした義務に正当な理由なく応じない場合には、取り消しの正当化につながる可能性があります。
どちらの扱いになるかは、内定通知書や誓約書の記載内容、企業がどのように説明したか、学生がどのように同意したかといった「合意の具体的内容」によって判断されます。したがって、企業は通知書の内容を明確にし、効力の発生時期について誤解を与えないよう説明しておくことが重要です。
内定や内々定の段階で発生するトラブルの多くは、事前のルール設定や情報共有によって回避できます。企業が一方的に対応すると、不当な取り消しや信頼関係の破綻につながりかねません。採用プロセスの早い段階から透明性を確保し、書面や説明会で条件やルールを明示しておくことは、法的リスクを下げ、応募者との信頼を守るために不可欠です。
内々定は法的拘束力が弱いとされますが、応募者にとっては大きな影響を持つため、早い段階でルールを示すことが重要です。書類提出の期限や連絡方法、無断欠席が続いた場合の対応などを通知書や説明会で明確に伝えておけば、後の誤解や不満を防ぐことができます。
内定通知書では、内定が労働契約を前提とした意思表示であることを明確化し、労働条件をできる限り具体的に記載しておくことが望まれます。勤務開始日、勤務地、給与、勤務時間などを明示することで、応募者の安心感を高め、不要なトラブルを防ぐことができます。
内定取消の可否をめぐる争いを避けるためには、どのような場合に取り消しが行われるかをあらかじめ規定しておくことが効果的です。たとえば、卒業できなかった場合、重大な虚偽申告が判明した場合、長期間の無断欠席が続いた場合などを取り消しの具体例として明記しておけば、いざというときに正当性を説明しやすくなります。
バスケット条項とは、具体的に列挙されていない場合でも「その他企業が入社を不適当と判断した場合」といった包括的な条件を加えることを指します。これを盛り込んでおけば、想定外のトラブルにも柔軟に対応できます。ただし、乱用すると不当な取り消しと評価されかねないため、運用には注意が必要です。
書面だけでなく、説明会や配布資料を通じてルールを応募者全員に周知することが大切です。文書と口頭説明を組み合わせて情報を伝えることで、理解不足や誤解を減らすことができ、後々のトラブル防止につながります。
連絡が取れない内定者や、必要な対応を怠っている内定者に対しては、企業がどのように連絡を試みたかを記録として残しておくことが重要です。メールや電話の履歴、書面での通知などを保存しておけば、後にトラブルになった際に企業の誠実な対応を裏付ける証拠となります。
採用に関するリスクは目に見えにくいものですが、企業経営に直結する重要な課題です。法務担当者・経営者が意識すべきリスク回避のポイントは、以下の3つです。
採用活動は人材を確保するための手続きにとどまらず、労働契約の始まりという側面を持ちます。内定や内々定を出す時点から契約の成立・内容・解除に関わる問題が発生するため、企業は初期段階からリスクマネジメントを意識することが重要です。
企業には採用する人材を自由に決める権限がありますが、一度内定が成立すると、その取り消しは解雇に準じた厳しい制約を受けます。この両者のバランスをどう取るかは、経営判断と法務的な視点の両面から検討し、慎重に設計する必要があります。
トラブルを防ぐためには、採用プロセスごとの法務チェック体制を整えることが欠かせません。内定通知書や誓約書の雛形を定期的に見直す、採用担当者向けに法務研修を行って判断基準を統一する、さらに万一のトラブルに備えて対応フローや記録管理のルールを策定しておくことが有効です。
採用は企業の将来を左右すると同時に、ブランドや信用にも直結します。法務担当者と経営層が連携し、リスクを見える化したうえで、実効性のある対策を講じていくことが、安定した人材確保と法的リスクの回避につながります。
内々定は、通常は労働契約の成立とはみなされず、法的効力は弱いと考えられます。しかし、企業が内定に近い形で通知を行った場合や、学生が内々定を前提に他社の選考を辞退するなど進路を固定していた場合には、実質的に労働契約が成立していると判断される可能性があります。
企業が「取り消しには合理的な理由がある」と主張しても、それが客観的に正当といえるか、社会通念上妥当といえるかは、最終的には裁判で判断されます。裁判に至らなくても、労働局のあっせんや労働審判を通じて問題となることもあります。独自に判断するとトラブルにつながる可能性が高いため、不安がある場合は弁護士に相談してから対応することが望ましいです。
内定辞退への対応策としては、誓約書に「正当な理由なく入社を拒否しないこと」といった項目を盛り込むことが有効です。また、説明会や内定式で「承諾後の辞退には誠実な対応が求められる」と周知すれば、モラル面からの抑止効果も期待できます。
内定や内々定は採用活動において重要ですが、その法的な位置づけや取り消しの可否がわかりにくく、誤解が生まれやすい部分でもあります。
内定は条件付きでも労働契約が成立すると見なされることがあり、取り消しには厳しい制約があります。一方で内々定は柔軟に対応できる面もありますが、応募者の行動や期待によっては企業に責任が及ぶ場合もあります。
こうしたトラブルを防ぐには、通知書や誓約書で条件を明示し、ルールを丁寧に共有しておくことが大切です。それでも対応に迷ったときは、弁護士に相談して正しい判断を確認することが、不要な紛争や信用低下を避けるうえで有効です。
「VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。