

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務
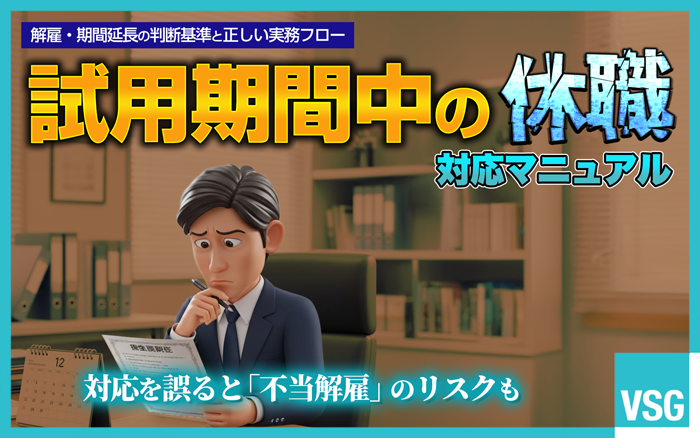
新入社員を受け入れる企業にとって、試用期間は本採用の可否を見極める重要な時間です。しかし、その最中に社員から「休職」を申し出られると、対応を誤って思わぬトラブルへつながることがあります。
たとえば、病気やメンタル不調で休職を希望されたときに、休職制度を適用するべきか、解雇や試用期間の延長が可能かなど、判断に迷う人事担当者も多いでしょう。もし法的に不適切な対応をすれば、不当解雇や労務トラブルとして争われ、企業の信用やリスク管理に大きな影響を与えるおそれがあります。
本記事では「試用期間中の休職」について、企業が押さえておくべき基本知識や実務上の対応を整理し、トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
試用期間は社員の能力や勤務態度を見極めるために設けられた制度ですが、この時期は雇用契約や就業規則の解釈があいまいになりやすく、トラブルに発展することがあります。
近年は、入社直後からの体調不良やメンタル不調、早期離職といった問題が目立ちます。こうした事態は、雇用が安定していない試用期間に起こりやすく、対応を誤れば企業は大きな負担を抱えることになります。
特にスタートアップや中小企業では人事体制が十分でないことも多く、その結果、予想外のコストや風評被害を受ける危険もあります。つまり試用期間は「社員を見極めるための期間」であると同時に、「トラブルが生じやすいリスク期間」でもあるのです。
試用期間中でも、休職制度が就業規則に定められている場合は、原則として対象に含まれます。休職制度は、社員が病気やケガ、メンタル不調などで長期間勤務できなくなったときに雇用関係を維持する仕組みであり、労働契約上「正社員」として雇用されている以上、試用期間中も適用されることが多いのです。
ただし、企業によっては就業規則に「休職制度は本採用後の社員のみ対象」と明記しているケースもあります。この場合は、試用期間中の社員が制度を利用できない可能性があります。反対に、規程が不明確なまま適用を拒むと、社員側から「不当な取り扱いだ」と主張され、労使紛争に発展するリスクも考えられます。
試用期間は「社員を見極める期間」として設けられています。そのため試用期間は解雇が簡単だと誤解されがちですが、実際には法律の制約があり、休職を理由に安易に解雇すると、不当解雇と判断されるおそれがあります。
労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」と定められています。これは試用期間中の社員にも適用されます。
そのため「休職したから」「欠勤が多いから」といった単純な理由だけでは解雇は認められません。休職は病気やメンタル不調など本人の責任ではないことも多く、正当な理由を示せなければ解雇は無効と判断される可能性が高いのです。
試用期間中は「留保解約権(本採用を見送る権利)」が認められており、原則として本採用後よりも広い裁量が企業に認められています。ただし、どのような場合でも自由に解雇できるわけではなく、通常の解雇と同様に客観的な合理性と社会的に妥当といえる理由が必要です(三菱樹脂事件 最高裁判所昭和48年12月12日判決)。
解雇が有効と判断されやすいのは、次のようなケースです。
つまり、単に「休職をした」という事実だけでは足りず、「今後も復帰の見込みがなく、雇用を継続することが現実的でない」と判断される状況でなければ解雇は認められません。
さらに、解雇の正当性は休職理由そのものだけでなく、企業の対応姿勢も含めて判断されます。たとえば「事前に十分な調査を行ったか」「改善のチャンスを与えたか」「指導内容をきちんと記録しているか」といった点です。診断書や産業医の意見、勤務状況の客観的記録を整備していなければ、後に「解雇権の濫用」と判断されるリスクが高まります。
休職を理由とした解雇は問題になる可能性がありますが、試用期間の延長であれば認められるのでしょうか。
試用期間の有無や期間の長さについて、法律で明確な上限が定められているわけではありません。ただし、試用期間はあくまで「適格性を確認するための観察期間」であり、この目的を超えて労働者を長期にわたり不安定な立場に置くことは許されないと考えられています。
過去の裁判例でも、過度に長い試用期間は無効と判断されています。
ブラザー工業事件 名古屋地方裁判所昭和59年3月23日判決
6カ月~1年3カ月にわたり見習社員として雇用したうえで、6カ月~1年うちに行う試用社員登用試験を経て試用社員となり、その後、社員登用試験を経て初めて正社員になれるという中途採用制度につき、以下のように判断しました。
ただし、例外的に試用期間の延長が有効とさ れる場面もあります。
たとえば、勤務態度に問題があった社員に対し、即時解約ではなく猶予期間を与えることで再評価を行うケースです。労働者にとって生活の安定につながるため、合理的と判断される可能性があります。ただし、この場合も労働者本人の同意や黙示の合意が前提となります。
一方で、アルバイトやパート、嘱託社員から正社員へ転換する際に改めて試用期間を設けることは、原則として認められません。すでに一定の勤務実績があるにもかかわらず、再び「適格性の観察期間」として扱うことになり、労働者を不必要に不安定な立場に置くからです。有期契約から無期契約へ転換する場合も同様です。
試用期間中に体調不良で診断書が提出されることは珍しくありません。ただし、診断書の内容をそのまま受け入れるのではなく、企業として適切に対応することが重要です。
医師が発行する診断書には「休養が必要」や「就業可能」といった記載がありますが、その内容をそのまま鵜呑みにする必要はありません。診断書はあくまで医学的な意見であり、実際に職務を果たせるかどうかを最終的に判断するのは企業の役割です。
たとえば、診断書で「就業可能」とされていても、実際には長時間勤務やストレスの高い業務には耐えられない場合があります。逆に「休養が必要」と書かれていても、軽作業や短時間勤務であれば復職が可能なこともあります。
そのため、企業は診断書を一つの参考資料としつつ、業務内容や職場環境、過去の勤務状況などを踏まえて総合的に判断することが大切です。必要に応じて産業医の意見を取り入れることで、復職判断の客観性を高めることができます。
復職の可否を判断するとき、主治医と産業医の意見が一致しないことは珍しくありません。主治医は患者である社員の体調回復を第一に考えるため、本人の訴えを重視して「休養が必要」と判断することが多い傾向にあります。一方で産業医は、職場の状況や業務の実態を踏まえ「就業は可能」と評価する場合もあります。
このように視点が異なるため、診断内容が食い違うことが起こります。企業としては、どちらか一方の意見だけに依存せず、双方の見解を踏まえて総合的に判断することが重要です。その際には、職務内容の調整や勤務時間の短縮といった選択肢も検討することで、より現実的で納得性のある対応につながります。
診断書の内容だけでは、実際に業務へ復帰できるかどうか判断がつかないことがあります。特にメンタル不調の場合、医師の「就業可能」の記載だけで職場に戻すと、再び体調を崩して長期休職に至るケースも少なくありません。
このようなときに有効なのが、「出社テスト(試し出社)」です。短時間や軽作業からスタートし、徐々に勤務時間や業務内容を増やすことで、復職の適性を客観的に確認できます。社員にとっても段階的に職場へ慣れることができ、再発防止につながります。
また、主治医や産業医に追加の意見書を依頼するのも有効です。診断の裏付けや補足説明を得ることで、企業が復職判断を行う際の根拠が強化され、後のトラブル防止につながります。
休職中の社員から突然、退職代行業者を通じて退職の意思が伝えられることがあります。感情的に対応するとトラブルにつながるため、企業は冷静に法的な観点から判断することが大切です。
退職代行業者から連絡があった場合、まず確認すべきなのはその業者が適法に業務を行っているかどうかです。弁護士資格のない業者が、法律相談や労働条件の交渉を行うことは非弁行為(弁護士法違反)にあたり、法的に認められていません。
そのため、業者からの連絡を受けた際には、「依頼者本人の意思を伝えるだけなのか」「法律交渉まで踏み込んでいないか」を必ず確認することが重要です。不適切な業者に安易に応じると、後に法的トラブルに発展するおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
退職代行業者から連絡を受けたとしても、企業が最も重視すべきは社員本人の意思が明確かどうかです。業者を通じた伝達だけでは、本人の真意かどうかを判断できないことがあります。特に休職中は精神的に不安定な場合もあり、あとから「本当は退職するつもりはなかった」と主張されるリスクもあります。
そのため、可能であれば本人に直接確認する機会を設けることが望ましいです。電話やメールなどで本人に連絡を試み、確実に意思を確認してから手続きを進めるようにしましょう。
本人の退職意思を確実に確認するには、自筆の退職届を提出してもらうことが重要です。署名と日付を明記した書面を受け取っておけば、退職について本人の意思を示す明確な証拠となり、将来のトラブル防止にもつながります。
退職代行業者からの連絡は、法的な問題を含むことが少なくありません。業者の行為が非弁行為にあたるかどうか、本人の意思確認をどのように進めるかなど、判断が難しいケースも多いでしょう。こうした場面では、法務部や顧問弁護士に早めに相談することが重要です。
専門家に確認をとることで、企業側の対応が法的に正しいかどうかを検証でき、後のトラブルを予防できます。特に退職条件の精算や有給休暇の処理など、細かな労務対応にも法的リスクが潜んでいるため、第三者の目を入れることで安心して対応できるようになります。
人事担当者が独断で進めてしまうと、結果的に不当解雇や手続きの瑕疵を指摘される危険もあります。専門的な視点を取り入れながら、冷静かつ適切に対応する体制を整えることが大切です。
試用期間中の休職は、対応を誤ると解雇や延長などをめぐって労使トラブルに発展するおそれがあります。あらかじめ制度や体制を整えておくことで、リスクを大幅に減らすことが可能です。
試用期間中に休職が発生したときの取り扱いは、就業規則に明記しておくことが重要です。制度の対象に試用期間中の社員を含めるかどうか、延長が可能かどうかなどを曖昧にしておくと、トラブルの原因になります。あらかじめルールを明文化し、全社員に共有しておくことで、不要な争いを防げます。
就業規則に加えて、雇用契約書や労働条件通知書に休職制度の適用範囲を記載しておくことも有効です。契約時に書面で取り交わしていれば、あとから「聞いていない」と争われるリスクを下げられます。特に中小企業では、就業規則が簡易的なことも多いため、契約書に具体的に盛り込むことが安心につながります。
制度を定めていても、社員が内容を理解していなければ意味がありません。入社時のオリエンテーションなどで、試用期間の位置づけや休職制度の適用範囲を説明することが大切です。トラブルが起きたときに「知らなかった」と言われないよう、最初にきちんと説明しておくことが予防策になります。
休職トラブルの多くは、体調不良やメンタル不調の見逃しから始まります。定期的な健康診断や簡易的なストレスチェックを導入することで、社員の不調を早期に把握できます。問題が大きくなる前に対処できれば、休職や長期欠勤に発展するリスクを抑えられます。
復職判断や退職代行対応など、試用期間中の休職には専門的な判断が必要になる場面があります。産業医とは健康面、顧問弁護士とは法的側面について相談できる体制をあらかじめ整えておけば、現場の人事担当者が迷ったときも安心です。専門家の意見を取り入れることで、対応の客観性も高まります。
休職が起きたときに対応が場当たり的になると、社員ごとに扱いが異なり、不公平感やトラブルの原因になります。欠勤が続いたときの連絡手順、診断書の扱い、復職時の確認方法などをマニュアル化しておけば、誰が対応しても一貫性を保てます。
休職に至った背景や復職の見通しを理解するためには、本人との面談が欠かせません。形式的なやり取りではなく、体調や働き方の希望を丁寧に聞き取ることで、会社として適切な対応が取りやすくなります。面談記録を残しておけば、後のエビデンスとしても役立ちます。
休職や解雇に関するトラブルは裁判に発展する可能性があります。その際に重要となるのが、連絡記録や診断書、面談メモなどの客観的な証拠です。日々の対応をきちんと記録し、必要に応じて保管しておくことで、企業側の正当性を示せるようにしておきましょう。
制度を整えても、現場の人事担当者が正しく理解していなければ意味がありません。研修を通じて、試用期間中の休職対応や法的リスクの基礎知識を学ぶことで、判断の誤りを減らせます。対応力を高めておくことは、トラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法の一つです。
メンタル不調による休職が繰り返されると、業務への適応力に疑問が生じます。ただし「休職をしたこと」そのものを理由に本採用を拒否すると、不当な取り扱いとみなされるおそれがあります。勤務状況の記録や医師の診断書を踏まえ、業務に支障があるかどうか、改善の見込みがあるかを客観的に評価することが重要です。
数日や1週間程度の休職であっても、業務遂行への影響が大きい場合には本採用の判断に考慮して差し支えありません。ただし、合理的な評価基準を明確にしているかがポイントです。欠勤の有無だけでなく、勤務態度や業務遂行能力など複数の観点を総合的に見極める必要があります。
休職中は労務提供の義務がないため、業務そのものを依頼することはできません。ただし、健康保険の手続きや会社備品の返却など、労務管理上必要な最低限の連絡は可能です。連絡頻度や内容が過度になれば「休職中の不当な対応」とみなされるリスクがあるため、配慮した対応が求められます。
休職者への対応が「特別扱い」に見えると、周囲の社員から不満が出ることがあります。この場合は、就業規則に基づいて公平に対応していることを説明する姿勢が大切です。また、職場全体に負担が偏らないよう、業務の再分担やサポート体制を整えることも必要です。説明責任と環境調整の両方を意識することで、不満を和らげやすくなります。
試用期間中の休職は、解雇や延長の判断、診断書への対応、退職代行業者からの連絡など、さまざまなリスクを伴います。対応を誤れば、不当解雇や労働契約法違反とされ、企業に大きな不利益をもたらす可能性があります。
トラブルを防ぐためには、就業規則や雇用契約に明確なルールを定め、入社時に丁寧な説明を行うことが欠かせません。また、産業医や顧問弁護士と連携し、客観的な判断を積み重ねることも大切です。
それでも、ケースによっては判断が難しい場面があります。そのようなときは、労働問題に強い弁護士へ早めに相談することが最も確実なリスク回避策です。専門家の助言を受けながら対応することで、企業として適切な判断を行い、不要なトラブルを避けることができます。
「VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。