

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務
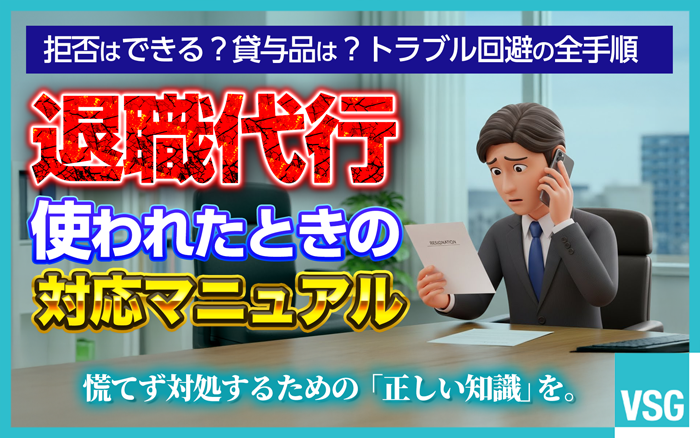
近年、「退職代行」という言葉を耳にする機会が増えました。退職を希望する従業員が、自分の代わりに専門の業者へ手続きを依頼し、会社と直接やり取りせずに退職を進める仕組みです。利用者が増える一方で、企業側には突然の連絡や引き継ぎの欠如など、予期せぬトラブルにつながるリスクがあります。
「退職代行から連絡が来たが、どう対応すればよいのか」「貸与品の返却や有給休暇の扱いはどうなるのか」など、実務上の疑問を持つ経営者や人事担当者も少なくありません。対応を誤れば労務トラブルや法的リスクにつながるため、正しい知識を備えて冷静に対応することが重要です。
この記事では、退職代行の仕組みや法律上の位置づけを整理し、会社側が取るべき対応手順や注意点、さらに退職代行を利用されないための予防策までをわかりやすく解説します。
目次
退職代行とは、従業員が会社を辞めたいと考えたときに、本人の代わりに専門の業者や弁護士が退職の意思を会社へ伝えるサービスです。近年、若手社員を中心に利用者が増えており、「上司に直接言い出しにくい」「人間関係がつらい」といった心理的な理由から依頼されるケースが多く見られます。企業にとっては突然の通知となることが多いため、適切な対応を理解しておく必要があります。
退職代行には、大きく分けて次の3つの形態があります。
弁護士が依頼を受けて会社とやり取りを行うケースです。弁護士には「代理権」が認められており、退職の意思表示に加えて、未払い残業代の請求や退職日・有給休暇の調整など、法的交渉まで対応可能です。パワハラなど法的トラブルに発展する可能性が高い場合や複雑な事情を含むケースでは、弁護士から連絡がくるケースが多いです。
合同労働組合(ユニオン)」が退職手続きを代行するケースです。労働組合には法律で団体交渉権が認められているため、退職条件や有給休暇の扱いなどについても交渉が可能です。会社としては正式な交渉相手として対応する必要があり、無視するとトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
一般企業が退職代行サービスを提供する形態です。利用しやすい料金設定が多く、即日対応を売りにしている業者もあります。ただし、法律上の「代理権」がないため、退職の意思を伝える以上の行為、つまり有給休暇の消化や金銭請求などの交渉を行うことはできません(非弁行為)。会社としては、退職の意思は受け止めつつも、手続きや条件の確認は本人と直接進めることが重要です。
退職代行を通じて伝えられた退職の意思を会社が拒否することはできません。労働者には憲法で職業選択の自由が保障されており、民法627条でも「期間の定めのない雇用契約は2週間前に通知すれば終了できる」と定められています。このため、意思表示の方法が本人から直接でなくても、退職自体を無効に扱うことは認められません。
ただし、民間業者の場合は代理権がないため、伝達内容が本人の真意かどうかを確認することは重要です。また、有期契約社員のように契約期間が定められている場合には、原則として途中での退職はできないため、労働契約法や契約内容に基づいた慎重な判断が必要となります。
企業としては「退職を拒否する」という発想よりも、本人の意思を尊重しつつ必要な手続きを進める姿勢が、後々のトラブルを防ぐうえで有効です。
退職代行から突然連絡を受けると、多くの企業が戸惑います。従業員と直接やり取りできないことで、退職手続きや引き継ぎが滞るのではないかと不安を感じる人事担当者も少なくありません。しかし、焦って不適切な対応をするとトラブルに発展しやすいため、落ち着いて一つずつ確認することが大切です。
最初に行うべきは、連絡してきた退職代行業者がどのような立場なのかを確認することです。弁護士や退職代行ユニオンであれば、法的に交渉権限があるため正式な対応が求められます。
一方、民間業者の場合は退職の意思を伝えることしかできないため、要求内容に応じるかどうかを慎重に判断する必要があります。業者の性質を見極めることが、その後の適切な対応につながります。
退職はあくまで本人の自由意思に基づくものです。民間業者が介入している場合は特に、従業員本人が本当に退職を望んでいるのかを確認することが重要です。電話や書面で本人と連絡を取り、意思を確認できれば、後日のトラブルを防ぐことができます。
退職代行から連絡を受けた際には、従業員の雇用形態を確認することが大切です。無期雇用の場合、民法627条により退職の意思表示から2週間で契約が終了するため、会社はこれを受け入れて手続きを進める必要があります。
一方で、有期雇用の場合は契約期間の満了までは原則として退職できません。ただし、民法628条に規定される「やむを得ない事由」がある場合は即時に契約を解除することも可能です。具体的には、パワハラや健康上の問題などがこれに該当する可能性があります。
したがって、会社としては単に「期間中は辞められない」と対応するのではなく、退職理由にこうした事情が含まれていないかを確認し、そのうえで適切な判断を行うことが重要です。
退職の意思が確認できたら、正式な退職届を提出してもらいましょう。加えて、社員証や制服、パソコンなどの貸与品の返却を依頼することも欠かせません。これらを放置すると社内管理上のリスクが残ってしまいます。返却が難しい場合には、返却期限や方法を明確に伝え、記録を残しておくと安心です。
退職代行が使われるケースでは、従業員が引き継ぎを拒むことも珍しくありません。会社にとっては業務継続が最優先となるため、可能であれば業務内容を整理した資料の提出を依頼するなど、最低限の引き継ぎを求めましょう。応じてもらえない場合に備えて、日頃から業務の属人化を避ける仕組みづくりも必要です。
在職中に知り得た顧客情報や営業ノウハウの流出を防ぐため、秘密保持誓約書や競業避止義務に関する書類を確認することも重要です。入社時にサイン済みの場合は内容を再確認し、未提出なら退職時に署名を求めることが望ましいです。
最終的には、退職届を正式に受理して退職手続きを完了させます。感情的な対応や強硬な引き留めは労務トラブルにつながりやすく、会社の信頼性を損なう結果にもなりかねません。法律に沿った冷静な処理を進めることで、不要な紛争を避けることができます。
退職代行業者からの突然の連絡に戸惑う企業も多いですが、対応を誤ると労務トラブルに発展する危険があります。ここでは、連絡を受けた際に会社側が特に注意すべきポイントを整理します。
民間の退職代行業者には法律上の代理権がなく、会社に伝えられるのは「退職の意思」だけです。有給休暇の取得や金銭請求といった交渉を持ちかけてくる場合もありますが、それに応じると非弁行為に関与するリスクがあります。 民間の退職代行業者が連絡してきた場合、必要な手続きや条件については従業員本人に確認する姿勢を徹底しましょう。
従業員には労働基準法で有給休暇の取得権利が認められています。退職代行を通じて退職する場合も同じで、会社が一方的に消化を認めない対応は法的に問題となります。退職日までに残日数を確認し、可能な範囲で消化させることが必要です。消化できない場合には、未消化分の買い取りを行うなど、法律に沿った処理を忘れないことが重要です。
突然の通知に動揺し、強い引き止めや感情的な反応をすると、会社に不当な圧力をかけられたと受け止められる可能性があります。最悪の場合、労務トラブルや損害賠償請求につながることもあります。冷静に受け止め、必要な書類や貸与品の返却、退職日や有給休暇の処理などを速やかに進めることが、会社にとっても最善の対応です。
退職代行を利用される背景には、会社との関係性が悪化し、本人が直接退職を伝えにくい状況があるケースが多く見られます。従業員が安心して働き続けられる環境を整えることが、退職代行の利用を防ぐ最大の対策です。ここでは、会社が実務で取り組める具体的なポイントを紹介します。
日々のコミュニケーションは、社員の不満や不安を早期に把握するうえで欠かせません。上司や同僚との信頼関係があれば、退職の意思も直接伝えやすくなります。定期的な面談や雑談の場を設けることで、職場の雰囲気を良好に保つことができます。
従業員が問題を抱えても、誰にも相談できない状況では退職代行を使う可能性が高まります。社内に相談窓口を設け、匿名で意見を伝えられる仕組みを整えることで、従業員の声を早めに吸い上げ、改善につなげることが可能です。
昇給や昇進の基準が不透明だと、不公平感からモチベーション低下や離職につながります。評価制度を明確にし、成果や努力が正当に反映される仕組みを整えることで、社員は会社への信頼感を持ちやすくなります。
パワハラやセクハラといったハラスメントが横行する職場では、社員は直接声を上げにくく、退職代行を利用して会社を去る傾向があります。社内研修や規程の明確化を通じてハラスメントを防止し、安全で働きやすい環境を築くことが大切です。
テレワークや時差出勤、休暇制度の拡充など、柔軟な働き方を導入することで社員の満足度は高まります。さらに福利厚生を充実させることで、社員が会社に対して安心感や愛着を持ち、突然の退職を考えにくくなります。
退職代行を使われる背景には、上司のマネジメント不足が関与するケースもあります。管理職研修を通じて、部下への適切な指導や相談対応のスキルを磨くことで、離職リスクを下げられます。
退職代行を通じて伝えられた退職の意思を会社が拒否することはできません。労働者には職業選択の自由があり、意思表示が本人から直接でなくても、法的には有効とされます。民間業者であっても退職の意思を伝えること自体は可能なため、会社は連絡を無視せず、必要な手続きを進めることが求められます。ただし本人確認は重要であり、退職届や書面の提出を必ず求めるようにしましょう。
退職時に返却が必要な社員証、PC、制服などの貸与品が戻らない場合、まずは本人に返却を依頼し、そのやり取りを記録として残しておくことが大切です。それでも返却がない場合には、損害賠償請求の対象となる可能性があります。ただし、給与の未払い分と相殺するなど一方的な処理は労働基準法違反にあたる可能性があるため、対応は慎重に進める必要があります。
有給休暇は労働基準法で認められた権利であり、退職に際しても原則として取得が可能です。会社の都合で消化を拒否することはできません。業務の都合で消化が難しい場合には、未消化分を買い取る形で対応する必要があります。退職代行を通じて申し出があったとしても、権利行使として認める姿勢をとりましょう。
退職日は、本人の意思表示と雇用契約の内容によって決まります。無期雇用であれば、民法627条に基づき退職の意思表示から2週間後に終了するのが原則です。有期雇用では契約満了日が基本ですが、民法628条にある「やむを得ない事由」があれば即時退職も認められます。会社が一方的に退職日を指定することはできないため、契約内容と法律に沿って判断しましょう。
退職代行を利用した場合でも、退職の意思はあくまで従業員本人によるものであるため、基本的には「自己都合退職」となります。会社側が解雇したわけではないので、失業給付などの取り扱いも自己都合の基準に従います。ただし、パワハラや安全配慮義務違反など会社に重大な問題がある場合には、会社都合退職と認められる可能性もあるため、背景事情を把握することが重要です。
退職代行は、従業員が会社に直接退職を伝えにくい状況で利用されるケースが多く、企業にとっては突然の通知や不十分な引き継ぎなど、思わぬ混乱を招くことがあります。対応を誤れば、不当労働行為や未払い残業代請求といった法的トラブルにつながる可能性もあるため、冷静で正確な処理が欠かせません。
会社側が取るべき基本姿勢は、従業員本人の意思を尊重しつつ、法律や契約内容に沿って必要な手続きを進めることです。民間業者と交渉をしない、有給休暇を適切に扱う、感情的な対応を避けるなど、基本的なルールを守ることでリスクは大きく減らせます。
「VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。