

東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。
労働問題は、一歩対応を誤れば損害賠償だけでなく、企業の信用失墜や従業員の士気低下、ひいては経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。
私は、野村證券をはじめとする金融機関で10年以上にわたり、リテール営業からコンサルティング、金融庁との折衝やリスク管理まで、多方面の業務に従事してまいりました。これらの経験から、企業の数字と法務は密接にリンクしており、労働問題を「点」ではなく「経営の一部」として捉えることの重要性を痛感しております。
経営者側の立場に立ち、財務分析や資金調達の観点も含めた戦略的なアドバイスを行うことが私の強みです。単に紛争を解決するだけでなく、組織の持続的な発展を見据えた強固なガバナンス構築のお手伝いをいたします。経営者の皆様の良き相談相手として、誠実かつ論理的にサポートさせていただきます。
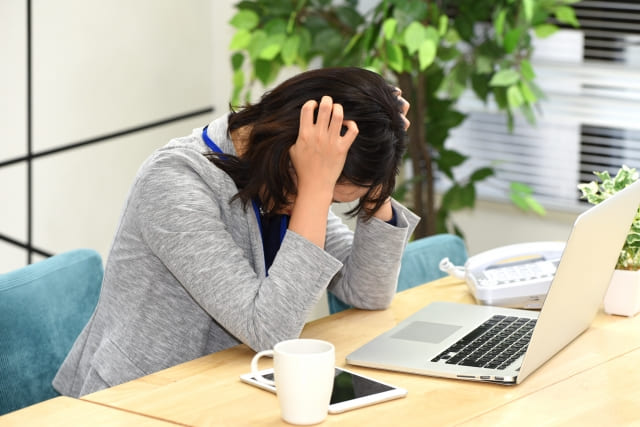
この記事でわかること
2022年4月からすべての企業にパワハラ防止措置が義務化されたことにより、ハラスメント問題は世間の注目を集め、一層厳しい目で見られるようになりました。
こうした背景もあり、パワハラの会社責任が認定された場合の具体的なリスクに不安を感じることもあるのではないでしょうか。
実際に、パワハラは加害者と被害者の個人間の問題にとどまらず、企業全体に深刻な損害が生じる可能性があります。
本記事では、会社がパワハラで責任を問われた場合に想定されるリスクや判例、適切な対処法、さらに防止策について解説します。
目次
企業が社内のパワハラに適切な対応をしなかった場合、次のような責任に問われる可能性があります。
ここでは、それぞれの責任について詳しく解説します。
使用者責任とは、従業員が業務に関連して第三者に損害を与えた場合に、その行為やその行為の結果について会社も責任を負うというものです。
これは「会社は従業員の行為によって利益を得ているため、その行為がもたらす損害にも責任を負うべき」という考えに基づいています。
たとえば、職場のパワハラが原因で従業員が精神疾患を発症した場合、加害者本人だけでなく会社も損害賠償責任を問われる可能性があります。
会社が問題を把握していながら放置した場合は、過失が認められやすく責任も重くなります。
一方で、会社が十分な防止策を講じていた場合は責任が軽減されることもあります。
また、業務と無関係な従業員の私的行為で生じた損害に対しては、責任を問われる可能性が低くなります。
不法行為とは、故意または過失により、他人の権利や利益を侵害する行為です。
パワハラが事業の執行や、代表者本人、または代表者と同視できる立場の者によって行われた場合は、会社が不法行為責任を負う可能性があります。
たとえば、会社の方針や指示に基づき特定の従業員を意図的に孤立させた場合は、会社そのものの不法行為と判断される可能性が高まります。
パワハラと認定されれば、会社は損害賠償などの責任を負います。
債務不履行責任とは、契約上の義務を果たさなかった場合に負う責任です。
この場合は労働契約を指し、会社は労働契約法により、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。
たとえば以下のような場合には、会社が安全配慮義務を怠ったとして債務不履行責任を問われます。
従業員がパワハラによって負傷・病気を発症した場合、それが業務に起因するものと認められれば労災に該当します。
被害者は労災保険から金銭を受け取ることができるようになります。
この際、会社に安全配慮義務違反などがあった場合、会社は損害賠償や労災保険では補償されない部分について、支払いの義務があります。
具体的には、慰謝料や休業補償給付の一部、逸失利益などです。
パワハラが企業にもたらすリスクには、次のようなものがあります。
ここでは、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
職場でパワハラが横行していると、健全な職場環境は維持できません。
被害者本人だけでなく、周囲の従業員も不安や不信感を抱くため、全体のモチベーションや業務への集中力が低下します。
その結果として、離職者が増加し、新しい人材の定着が難しくなるなど、人手不足が慢性化する可能性があります。
残された従業員が長時間労働によって疲労を蓄積させた場合、さらなる健康被害が発生し、悪循環から抜け出せなくなる恐れがあります。
会社はパワハラの被害者から、損害賠償請求を受ける可能性があります。
特に以下のような重大な結果に繋がった場合は、損害賠償請求額が数千万円規模に及ぶ可能性もあります。
また、示談や裁判などの交渉やトラブルにおいても、弁護士費用や訴訟対応のための時間や人件費などのコストも増加します。
パワハラの結果による被害が大きく、トラブルが悪化するほど、企業経営に深刻なダメージが生じます。
近年、世間がパワハラ行為に向ける目は一層厳しくなっており、企業の姿勢や対応不足は瞬時に批判の対象となります。
パワハラが認定されれば「パワハラを放置する企業」という悪いイメージが定着してしまい、企業の社会的評価は大きく低下します。
訴訟に発展すれば報道などで広く知られるため、取引先との関係悪化や採用活動への悪影響を招く可能性もあるでしょう。
信用失墜は企業内だけの問題に留まらず、長期的かつ広範囲にわたり、企業経営の基盤を揺るがす深刻なリスクとなります。
会社のパワハラ責任が問われる場面は、大きく分けて次の2つです。
ここでは、それぞれの場面での会社の対処法について解説します。
従業員からのパワハラ被害の訴えは、社内の相談窓口への申し出から労働審判や訴訟まで、様々な形があります。
それぞれの段階や個別の事情によって、会社が取らねばならない対応や留意点は異なりますが、共通して重要なことは、速やかかつ公正に事実関係を調査することです。
感情的な対応や一方的な対応は状況を悪化させて、結果として企業が担う賠償範囲を拡大する恐れがあるため、避けましょう。
ただ、被害者の訴えや損害賠償請求に対して、必ずしもそのまま応じることが最善とは限りません。
会社は、事実確認や証拠の収集などの現場対応と同時に、法的リスクの整理を行う必要があります。
そのため、会社の立場や将来的な影響を踏まえ、最も適切な解決策を判断できる弁護士にできるだけ早く相談することが望ましいでしょう。
パワハラ被害者が労働基準監督署などの行政機関に相談した場合、企業のパワハラ防止措置や対応状況が調査されることがあります。
必要な措置が講じられていないと判断されれば、是正勧告や指導が行われ、改善報告を求められることがあります。
この場合、行政の求める改善措置を正確に理解し、改善計画を策定することが重要です。
対応を誤ると、再度の指導、被害者から更にパワハラ行為の責任を追及される可能性があります。
そのため、是正勧告や指導を受けた時点で弁護士に同席・助言を依頼し、適法かつ効果的な対応方針を立てて、対策をしましょう。
ここでは、実際にパワハラ行為による会社の責任が問われた裁判例を見てみましょう。
本件は、アパレル店で働くアルバイト店員が、同じ店舗で働いていた準社員2名から継続的な嫌がらせやパワハラ行為を受けたとして、両準社員と会社に対して損害賠償請求をした事案です。
被害者であるアルバイト店員は、同じ店舗で準社員として勤務する2名から、以下の嫌がらせを受けたと主張しました。
被害者はこれらの行為をパワハラだと訴え、それぞれに対して以下の損害賠償請求を行いました。
裁判所は、準社員2名による行為をパワハラとして認定し、それが業務の執行に関連した行為であると判断しました。
そのため、会社にも使用者責任を認め、両準社員と連帯して原告への慰謝料の支払いを命じました。
本件は、事業廃止に伴う整理解雇の無効を争うとともに、慰謝料および休業損害の支払いを求めた事案です。
慰謝料・休業損害の支払いを求める根拠は、労働者が会社および代表取締役らによる嫌がらせ(いじめ)行為により精神的苦痛を受けたことです
労働者は、以下の事象に対して会社が適切な対応を取らなかったと主張しました。
裁判所は、代表取締役社長および専務が、労働者を孤立させ、退職に追い込むことを目的とする一連の嫌がらせ行為を認識しながら、防止措置を講じず、むしろその一部を業務命令として実行していたと認定しました。
その結果、2名の代表取締役個人の不法行為責任が認められました。
2名には会社とともに、労働者の受けた精神的苦痛に対する慰謝料150万円のほか、欠勤日数に対応する休業損害の支払いが命じられました。
2022年4月から、すべての企業にパワハラ防止措置を講じることが義務付けられました。
会社が講じなければならない防止対策は、具体的には次の通りです。
ここでは、それぞれの措置について解説します。
企業は、事業主が「パワハラは許さない」という姿勢を明確に示し、従業員に周知・啓蒙することが義務づけられています。
具体的には、就業規則などにパワハラ禁止や、懲戒対象となる旨を明記すること、社内ポスターやインタらネットで方針を発信することが挙げられます。
また、管理職や一般社員を対象に、パワハラの定義や防止策を理解させるための研修を実施することも重要です。
会社は、パワハラに関する相談を受け付ける窓口を設け、従業員に周知する義務があります。
窓口担当者はパワハラ防止に関する知識を持ち、適切な対応を取れるようにしておくことが求められます。
窓口は必ずしも社内設置に限られておらず、小規模事業所などでは外部の専門機関や顧問弁護士、社労士などを活用する方法もあります。
特に、社内の人間関係から相談が難しい場合、外部窓口の存在は安心感を与え、相談のハードルを下げる効果があります。
パワハラ相談を受けた場合、会社は以下のような適切な措置を講じなければなりません。
これらの対応を怠れば、パワハラの会社責任が認定された場合に、法的責任が重くなる可能性があります。
調査では被害者、加害者、関係者へのヒアリング、証拠資料の収集を行い、その間は被害者の心身のケアも必要です。
また、調査や対応にあたってはプライバシーを保護し、相談や協力を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。
パワハラが認定された場合だけでなく、認定されなかった場合でも、会社には再発防止策を講じる義務があります。
具体的には、以下の対策が考えられます。
こうした措置を取らなければ、同様の問題が繰り返され、適切な措置を講じなかったとして、会社責任が問われる可能性があります。

パワハラ問題が深刻化すると、企業は大きな不利益を被ります。
そのため、以下のポイントを押さえ、パワハラを未然に防ぐ会社づくりが重要です。
ここでは、それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
風通しの悪い職場ではパワハラが発生しやすく、被害者が相談することが難しいため事態が悪化しやすくなります。
定期的な面談や意見交換の場を設ける、部署間の交流を活性化するなど、従業員が安心して声を上げられる環境づくりが重要です。
こうした体制を整えることで、問題が小さいうちに把握し、迅速に対応できるようになります。
パワハラには明確な定義があり、厚生労働省はパワハラの典型的な6類型を示しています。
しかし、現場で働く従業員には抽象的に感じられる場合もあるため、自社の業務内容や職場特性に応じた具体例を加え、再定義することが有効です。
たとえば、命に関わる業務では、緊急時に大声で注意を促すことは必要な行為です。
しかし、その後に「こんなこともできないならここでは勤められない」といった人格を否定する発言をすれば、パワハラに該当する可能性があります。
こうした境界線を明確にし、全社員に共有することが防止策につながります。
パワハラ防止のためには、就業規則や服務規程にパワハラ行為を行った従業員への処分内容を明記し、周知徹底することが必要です。
処分規定が明確になれば、従業員はパワハラが懲戒対象となる重大な行為であると認識でき、抑止効果が高まります。
パワハラの会社の責任が認められると、加害者だけではなく、会社も様々な法的責任を負うことになり、経営にも大きな痛手を被ります。
そのため、単なる法律の義務としてパワハラ防止策を実行するのではなく「従業員と会社を守る」という意志でパワハラを防止しましょう。
また、パワハラは未然に防ぐための工夫が重要です。
自社で十分な防止措置や相談窓口の設置が難しいと感じる場合は、会社のパワハラ問題対応に実績のある弁護士などに相談、連携をするのがよいでしょう