

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務
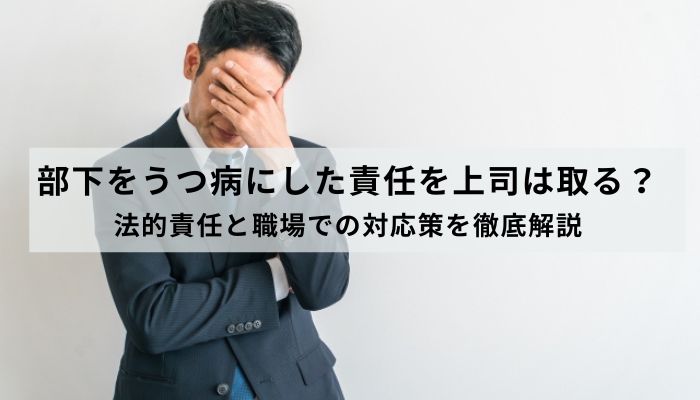
この記事でわかること
部下がうつ病になってしまった場合、上司として責任を問われないか不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
上司の指導方法や業務の与え方などの対応によっては、部下のうつ病に対し一定の法的責任を問われるケースは実際にあります。
一方で、早期に部下のメンタルヘルス不調に気づき、うつ病の発症を防ぐために適切な対応を行っていれば、上司の責任が問われない場合もあります。
この記事では、部下をうつ病にした際に上司が負う法的責任、うつ病の原因となりうる職場要因、予防・対応のポイントをわかりやすく解説します。
目次
上司が部下をうつ病にした場合、ケースによっては責任を取る必要があります。責任を取る・取らないケースについて見ていきましょう。
部下のうつ病の原因が、自身の言動や職場環境にあると認められる場合、上司が一定の責任を負う可能性は高くなります。
上司には、業務の指示や評価だけでなく、部下のメンタル面も含む健康状態に配慮するマネジメント責任があるためです。
具体的には、次のようなケースが考えられます。
このような場合、上司の行為と部下のうつ病との間に因果関係が認められやすくなり、責任が問われます。
うつ病の発症には、以下を含む様々な要因が複雑に関係しています。
そのため「部下がうつ病になった=上司の責任」と短絡的に結びつける行為は適切ではありません。
次の例のように、
職場の状況とは無関係な理由で部下がうつ病を発症したケースでは、上司の責任が問われる可能性は低いでしょう。
また、上司が部下のメンタル不調にいち早く気づき、適切な対応や支援を行っていた場合は、うつ病発症の責任を問われる可能性が低くなります。
部下を指導・管理する立場にある上司は、会社の業務執行において一定の権限を委ねられた存在です。
そのため、部下をうつ病にした場合、上司は会社とともに以下の責任を問われる恐れがあります。
それぞれの責任について詳しく解説します。
使用者責任は、従業員が業務に関連して第三者に損害を与えた行為や、その行為がもたらした結果に対して、使用者(会社)が負う法的責任です。
会社は従業員の行為によって利益を得ているため、行為によって生じた損害についても責任を負うとの考えに基づいているためです。
たとえば、職場内のハラスメント行為が原因で部下がうつ病を発症した場合、行為者だけではなく会社および上司も使用者責任を問われる可能性があります。
問題を知りながら放置していたなど、適切な監督体制を敷いていなかったと認定された場合には、より大きな法的責任を負うでしょう。
一方で、上司が適切な監督や指導を行っていたなど、不法行為を回避する努力が十分にされていた場合は、責任が軽減される場合もあります。
安全配慮義務とは、使用者が労働契約を結んだ従業員に対し、業務を安全かつ健康に遂行できるように配慮する義務をいいます。
この義務は、物理的な安全だけではなく、心理的・精神的な健康に対する配慮も含まれています。
具体的には、次のような配慮が求められます。
労働者が過度なストレスや精神的苦痛を感じる状況を放置した場合、上司が直接的な原因でなくとも安全配慮義務違反を問われる可能性が高くなります。
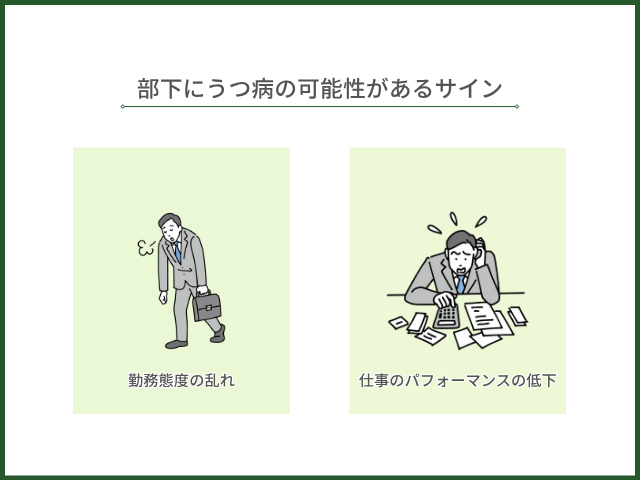
うつ病などのメンタルヘルス疾患には初期サインや兆候が現れる場合があります。
上司がいち早く気づけば、症状の深刻化防止が可能です。
そのためにも、以下で紹介するうつ病の可能性がある具体的なサインについて確認しておきましょう。
メンタルヘルス不調に陥ると自己管理が難しくなるため、身なりや日常の動作などに気を配れなくなります。
結果的に、いつもの勤務態度にも変化が現れるようになるでしょう。
部下に以下の様子が見受けられる場合には、メンタル不調の可能性が高いため、注意が必要です。
部下の勤務態度に変化があった場合は、早めの声かけや状況の確認が求められます。
メンタル不調に陥ると、集中力や判断力、意欲が低下するため、これまで問題なくこなしていた業務の遂行が難しくなる場合があります。
その結果、仕事のパフォーマンスが低下するため、部下に次の変化が見られた場合は注意しましょう。
これらの変化は、単なる疲労や一時的な不調かどうかの見極めが難しいため、見過ごされがちなポイントです。
部下の仕事に対するパフォーマンスが落ちたと感じたときは、継続性があるかどうかに注目して判断をしましょう。
職場の状況や上司との関係性などは、うつ病の発症に大きな影響を与えます。
たとえば、上司による次の行為は、うつ病を引き起こしかねません。
以下では、なぜうつ病を引き起こすのかを詳しく解説します。
職場での過度なプレッシャーは、部下の精神的なゆとりを奪い、うつ病の引き金になりかねません。
具体的に以下の就業環境下では、大きなプレッシャーがかかります。
自分の限界を言い出せない従業員も少なくありません。
表面上は問題がないように見えても、部下の内面では深刻な疲弊が進んでいるケースもあります。
マイクロマネジメントとは、上司が部下の仕事に対して、過度に干渉し、細かく管理・指示する行為を指します。
具体的には、上司による部下への、次の行動が該当します。
このような状況下は、常に監視されているような強い緊張感を与えるため、部下がストレスを抱える原因となります。
長期間続くと、精神的な疲労が蓄積され、うつ病を発症させる原因となるでしょう。
部下にうつ病の兆候が見られるとき、上司の対応やサポートは症状を左右する重要な要因です。
部下にうつ病の可能性があるときは、以下の対策をとりましょう。
それぞれの対応の例を見ていきましょう。
うつ病を引き起こす要因となる職場内の問題を洗い出しましょうたとえば、業務量が過剰になっている場合は、タスクの見直しや業務の再分配が必要です。
部下が人間関係のストレスを抱えていれば、異動や配置転換、当事者間の物理的な接触を減らす工夫などが考えられます。
長時間労働や休日出勤が常態化している場合や過剰なノルマが社風になっている場合では、それ自体が従業員のメンタルに悪影響を与える原因です。
メンタル不調を訴える従業員の職場環境だけではなく、職場全体の改善も視野に入れて取り組みましょう。
うつ病が疑われる部下に対し、体調などのヒアリングを行い、本人にとって無理のない状況をつくるための適切な指示を出す必要があります。
たとえば、部下が人との接触を負担に感じている場合は、接客や多くのコミュニケーションを要する作業を避けるなど、業務の見直しが考えられます。
職場の人間関係やハラスメントが原因である場合は、当事者との接触を減らすための工夫(配置転換や異動など)をしましょう。
体調が中々改善しない場合は、会社の規定に基づいた一定期間の休職を提案する方法も有効です。
メンタルヘルス不調による休職で一定期間職場を離れた従業員に対しての復職支援も重要です。
すぐに元のペースで働かせてしまうと本人にプレッシャーを与えてしまい、不調が再発する危険性があります。
本人の意向や体調を十分に確認し、段階的に本来の業務に戻れるように復職プランを整えましょう。
このとき、社内の健康管理担当者や産業医との連携も大切です。
専門スタッフであれば、本人の体調などに合わせたリハビリ的な勤務(短時間勤務、軽作業など)を提案できます。
上司から同僚やチーム全体にも復職者に対する理解を促し、安心して復職できる環境づくりを進めましょう。
上司や会社が従業員のうつ病についての対応を誤ると、労災や訴訟などのトラブルに発展するリスクがあります。
問題を深刻化させないためには、無理に社内だけで解決しようとせず早い段階での労務問題に強い弁護士への相談が重要です。
職場の問題や労務トラブルに強い弁護士に相談をすれば、うつ病の従業員に対し、企業の法的リスクを踏まえた対応を依頼できます。
部下のうつ病への対応にお悩みの方は、労務問題や社内トラブル解決に実績のあるVSGの弁護士にいつでもご相談ください。
ここからは、部下のうつ病を防ぐために、上司が日ごろから意識したい行動を紹介します。
部下のメンタルヘルス不調のサインや兆候は、平常時の状態を知らなければ気づきません。
そのため、上司が日ごろから部下の様子に注意を払い、異変にいち早く気づけるかが重要です。
たとえば、形式的な報告・連絡・相談だけではなく、カジュアルな雑談や日常的な挨拶を通じたコミュニケーションの積み重ねを心がけましょう。
本人の様子だけではなく、周囲との人間関係や職場内の空気感にも気を配ると、メンタルヘルス不調の早期発見や予防につながります。
部下が悩みを抱えたときに気軽に相談できるような、コミュニケーションの取りやすい環境づくりを心がける点も重要です。
部下に不安やストレスがあった際、上司に話しかけづらい雰囲気があると問題が表面化せず、メンタルヘルスの悪化が進行するリスクがあります。
日頃から部下が話しかけやすい雰囲気や、雑談しやすい時間・場面を意識的に設ける習慣づくりが大切です。
たとえば、定期的な1on1ミーティングやカジュアルなランチミーティングを設ける方法が挙げられます。
役職者が席のある部屋のドアを開け、気軽に相談できる雰囲気を作るオープンドアの姿勢も効果的でしょう。
上司との間に心理的なハードルがなければ、部下は早い段階で不調を打ち明けやすくなり、適切な対応を講じやすくなります。
2022年4月から、すべての企業にハラスメント防止措置が義務付けられました。
職場のハラスメント問題は注目を集めており、世間の目も一層厳しくなっています。
価値観や表現に対する受け取り方の違いにより、上司にハラスメントの意図がなくとも、部下を精神的に追い詰めてしまう可能性はあります。
一方で、こうした背景からハラスメントを過剰に恐れて部下とのコミュニケーションを避けてしまい、上司が適切な指導を行えないケースも少なくありません。
上記の状況を避けるためにも、ハラスメントの定義や判断基準について正しい知識を持ち、適切な指導・対話を行う必要があります。
部下がうつ病を発症した場合、原因が周囲の言動や職場環境にあると認められれば、上司や管理職が法的責任を問われる可能性があります。
訴訟や損害賠償請求などトラブルが深刻化するケースもあるでしょう。特に、ハラスメントや長時間労働、メンタル不調の放置などがあった場合は注意が必要です。
一方で、上司や会社が不調の早期発見に至り、適切に対応していた場合は、責任を軽減できる可能性があります。
部下が発するうつ病のサインを見逃さないためには、日頃からの目配りや雑談・挨拶といったカジュアルなコミュニケーションが大切です。
上司として予防の姿勢を持ち、健全な職場環境の維持に努めましょう。
部下のうつ病による休職・退職でトラブルになりそうなときは、早めに弁護士にご相談ください。
VSG弁護士法人では、企業側の立場から適切な対応策のアドバイス・代理交渉を行っています。