
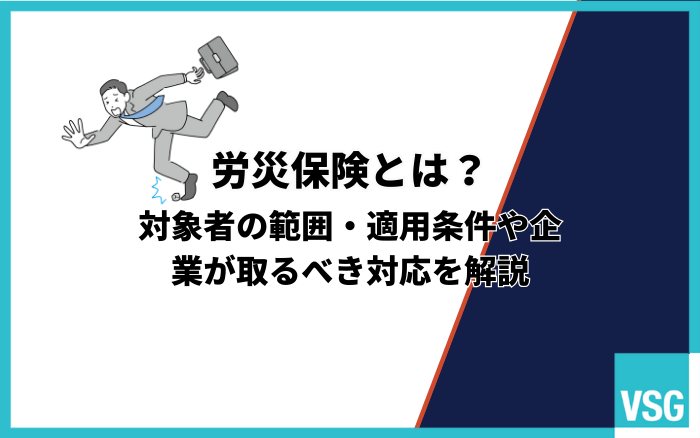
この記事でわかること
労働者災害補償保険(労災保険)[注1]は、労働者を一人でも雇えば原則として強制的に加入する制度です。
対象者は原則自社の労働者で、派遣労働者は派遣元で適用され、通常適用外の事業主なども特別加入で対象となるケースがあります。
業務災害は業務遂行性と業務起因性、通勤災害は通勤行為からの逸脱や中断の有無で判断されます。
労災事故発生時の初動対応から届出・再発防止までの一連の対応は、会社の重要な責務です。
この記事では労災保険の基本と会社の取る必要のある対応をくわしく解説します。
[注1]労働者災害補償保険法/e-Gov
労働者災害補償保険法
目次
労災保険は、労働者の業務や通勤を原因とした負傷・疾病・障害・死亡に対し、国が給付を行う公的保険制度です。[注2]
保険料は労働者の負担はなく、全額を事業主が支払うしくみで、事業単位で適用されます。
主な給付は、療養(補償)等給付・休業(補償)等給付・障害(補償)等給付・遺族(補償)等給付などです。
労災保険料の支払い方法や計算方法についてより詳細を知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
[注2]労災保険制度の概要について教えてください
労災保険は、原則雇用形態を問わず、自社で雇用するすべての労働者が加入対象です。
そのため、派遣労働者は派遣元で労災保険が適用されます。
代表取締役などの役員は通常適用対象外ですが、労働者性が高いと判断されれば適用対象です。
請負や一人親方、また役員などでも特別加入[注3]により労災保険が適用される場合があります。
[注3]労災保険への特別加入
会社との雇用契約に基づき指揮命令を受けて労務を提供する者は、すべて労災保険の対象です。
雇用形態や週の所定労働時間、雇用期間の長短にかかわらず適用されます。
そのため、正社員だけではなく、契約社員やパート、アルバイトなども労災保険に加入します。
派遣労働者は、派遣先ではなく派遣元の事業主が労災保険を適用・管理する責任を負います。
請負契約者や一人親方、特定作業従事者などは原則対象外ですが、特別加入によって適用されるケースがあります。[注3]
日雇い労働者やスポットワークなど1日あるいは短時間のみであっても、雇用実態があれば労災保険の対象です。
役員や個人事業主、フリーランスは原則労災保険の対象外です。
しかし、役員であっても勤務実態に労働者性が認められる場合は、労災保険に特別加入できます。
フリーランスは、要件を満たした場合に特別加入できるケースがあります[注3]。
たとえば、建設業の一人親方や企業から業務委託を受けて働く者(特定フリーランス事業)などが対象です。
労災保険の適用対象となる災害は、業務災害と複数業務要因災害、通勤災害の3種類です。
業務災害は業務遂行性と業務起因性が判断ポイントとなり、複数事業での就業が要因の場合は複数業務要因災害となります。
通勤災害は住居と就業場所間の合理的な経路・方法の範囲内であるか、逸脱や中断の有無で判断されます。
業務災害とは、仕事が原因で労働者が怪我や病気、障害、死亡に至る場合を指します。
判断の軸は「業務遂行性」と「業務起因性」の2つです。
業務遂行性は使用者の指揮命令下にあったかの確認で、業務起因性とは業務との因果関係があるかどうかの判断です。
就業時間中であっても業務に関連のない私的行為や故意・重大な逸脱があった場合は、原則業務災害とは認められません。
【業務災害に該当する例】
仕事の書類運搬中に転倒して怪我をした
出張先で交通事故に遭い負傷し、障害が残った
上司からの継続的なパワハラでうつ病になった
【業務災害に該当しない例】
フォークリフトで遊んでいたら落下した
休憩時間に外出中、自転車と衝突して怪我をした
勤務中に持病による発作で死亡した
なお、複数の事業場での就業が原因の場合は「複数業務要因災害」と判断されます。
通勤災害とは、労働者が通勤中の事故などにより怪我や病気、障害、死亡に至る場合を指します。
判断のポイントは、通勤経路と方法の合理性、通勤行為からの大きな逸脱や中断の有無です。
通勤の途中で、生活用品の購入や散髪、人工透析など必要最小限の日常生活行為を行う場合、その行為時間を除けば通勤性は維持されます。
一方、通勤経路から大きく逸脱した私的行為や趣味・遊興目的の中断は原則認められません。
【通勤災害に該当する例】
会社の最寄り駅構内で人と接触して転倒、負傷した
副業先への移動中に交通事故で負傷し障害が残った
通常の通勤経路を離れて日用品の買い出しをし、再び通勤経路に戻ったところ自転車に衝突し負傷した
【通勤災害に該当しない例】
就業後に同僚と4時間以上外食をした後帰宅経路に戻ったところ、交通事故に遭い負傷した
通勤前の日課であるランニング中に転倒し負傷した
就業後にコンサートに行き、その帰宅途中に事故に遭って障害が残った

労災事故発生時は、まずは事故状況を把握し、必要に応じて救急や安全確保、場合によっては弁護士への相談も検討します。
その後、事故内容の記録・原因調査を行い、被災者の労災申請手続きに対しても適切な支援を行います。
事後対応として労働基準監督署への報告、再発防止策まで確実な実施が重要です。
労災事故発生時は、すみやかに事故の日時・場所・目撃者・被害状況などを記録します。
ヒアリングを行う場合は5W1Hを意識し、写真や防犯カメラ映像など他の証拠との整合性を確認して、実態を正確に把握しましょう。
事故の原因に会社の安全配慮義務違反が認められると、損害賠償リスクに発展する可能性もあります。
調査段階から慎重さや丁寧な記録が求められます。
労基署への報告内容は、会社の安全配慮義務責任などの判断に影響する可能性があります。
そのため、記録や証拠が揃い次第、すみやかに弁護士へ対応方針を相談しましょう。
過失相殺や使用者責任、安全配慮義務に関する論点を整理しておくと、後の労基署調査にも備えられます。
労災事故の対応方針についてお悩みの企業様は、VSG弁護士法人へお気軽にご相談ください。
被災者が行う労災保険給付の請求について、会社は事業主証明欄の記載や必要書類の準備を支援する義務があります。
社内担当者が「療養(補償)等給付」(様式第5号)や「休業(補償)等給付」(様式第8号)など申請内容を確認して、必要書類の準備を進めます。
被災労働者が自力申請が困難な場合は、社内担当者が提出期限を把握したうえで申請を確実に行えるようにサポートしましょう。
事業場内の火災や爆発など、労働安全衛生規則第96条[注4]に規定する事故である場合、労基署へ「労災事故報告書」を提出しなければなりません。
報告書の提出とあわせて、社内担当者は労基署の臨検や調査に備えて関係資料を整理しましょう。
調査に対する不誠実な対応や虚偽報告は、行政指導や刑事責任に発展する可能性があるため、注意が必要です。
[注4]労働安全衛生規則/e-gov
労働安全衛生規則
労災事故発生後は、労基署へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません[注5]。
2025年1月1日より、電子申請での提出が義務化されました。
提出期限は休業日数が4日以上または死亡の場合は遅滞なく、4日未満の場合は事故発生日の四半期の翌月末日までです。
たとえば、1~3月に発生した休業4日未満の事故の場合、4月末日までに届出します。
報告しなかったり虚偽の報告をした場合「労災かくし」となり、刑事責任や刑法上の業務上過失致死傷罪などを問われる恐れがあります。
[注5]労働者死傷病報告
事故原因を踏まえ、担当部署が期限と責任者を明確にした上で、改善措置や安全教育・設備補強などの再発防止策を策定します。
専門性を有する事項は、適宜専門家の助言も受けながら内容を構築すると効果的です。
策定後は全社員への周知まで確実に実施してください。
対応を怠ると安全配慮義務違反と判断される恐れがあるため、一度実施して終わりにせず、実施状況を継続的に点検する体制整備が重要です。
労災保険給付は会社の過失有無に関係なく、医療費や休業補償などを国が支給する制度です。
しかし、安全配慮義務違反が認められた場合には、会社が慰謝料などの民事賠償責任を負う可能性があります。
社内見舞金は会社が任意で支払う金銭であり、労災給付と同一目的の支給は調整対象となり得るため、支給目的や社内規定の整備が重要です。
労災保険給付は、被災労働者の状況に応じて各種給付が受けられます。
怪我や病気の治療費を全額補償する「療養(補償)等給付」が代表例です。
休業時の賃金補償には「休業(補償)等給付」があり、給与基礎日額(平均賃金)の60%に加えて特別支給金としてさらに20%が支給されます。
その他に、障害が残った場合、死亡時の遺族への補償や葬祭料、介護費用も対象です。
請求時は所定様式と添付書類を確認しましょう。
| 給付名 | 対象事由 | 支給内容・割合 | 請求様式 |
|---|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 治療 | ・治療にかかる費用補償 ・「現物給付」と「費用の支給」の2種類 ・原則は現物給付 | ・様式第5号、第16号の3 ・費用の支給は様式第7号、第16号の5 |
| 休業(補償)等給付 | 休業 | ・休業時の賃金補償 ・1日あたり平均賃金の60%相当+特別支給金20% ・休業4日目以降から支給 | 様式第8号、第16号の6 |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病 | ・療養開始後1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級に該当した場合 ・傷病等級に応じた日数分の平均賃金額 ・年金形式で支給 | ・労基署の職権により手続きされる ・様式第16号の2 |
| 障害(補償)等給付 | 障害 | ・傷病が治ゆ(症状固定)した際に、障害が残った場合 ・障害等級に応じた日数分の平均賃金額 ・等級に応じて年金あるいは一時金の支給 | 様式第10号、第16号の7 |
| 遺族(補償)等給付 | 死亡 | ・被災者が死亡して遺族がいる場合 ・遺族の人数などに応じた日数分の平均賃金額 ・年金形式で支給 | 様式第12号、第16号の8 |
| 葬祭料 | 死亡 | ・葬祭を行った場合 ・「31万5,000円+平均賃金30日分」あるいは「平均賃金60日分」 いずれか多い額 | 様式第16号、第16号の10 |
| 介護(補償)等給付 | 特定の障害についての介護 | 介護の必要度・状況に応じて変動 | 様式第16号の2の2 |
| 二次健康診断等給付 | 健康診断 | ・脳・心疾患発症予防のための特定保健指導 ・原則現物支給 | 第16号の10の2 |
[注6]労災保険給付の概要
労災給付[注7]が行われても、会社の補償義務がすべてなくなるわけではありません。
業務災害における休業4日目までの賃金補償など、労災で補償されない部分は原則として会社が補償します。
また、安全配慮義務違反が認められた場合は、慰謝料や過失利益などの民事上の損害賠償責任が発生する可能性もあります。
労災給付との調整や使用者賠償責任保険などの活用は事案により異なるため、必要に応じて専門家に相談しましょう。
[注7]労災保険給付の概要
労災保険は原則としてすべての労働者に強制適用される公的保険です。
業務災害は業務遂行性と業務起因性、通勤災害は通勤行為からの逸脱の範囲、中断の有無を確認します。
会社は事故発生時の初動対応手順を整備し、申請支援や再発防止策を徹底して行い、所轄の労基署への届出を怠らないようにしましょう。
労災保険の適用や事故対応など、具体的な対応方針でお悩みの企業様は、VSG弁護士法人へお気軽にご相談ください。