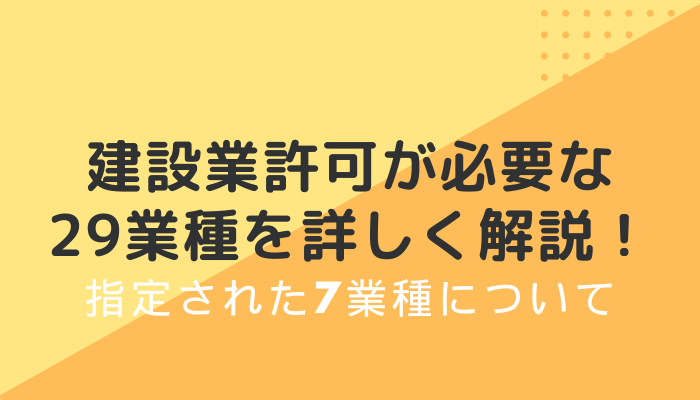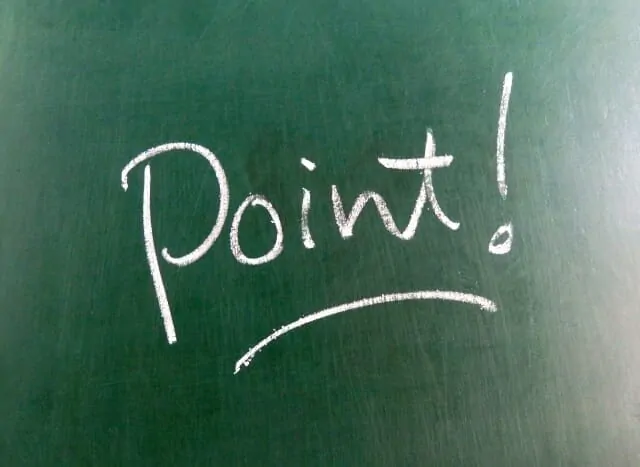この記事でわかること
- 発注された下請は建設業許可なしで工事を請けられるのか
- 下請に発注できる上限金額とは
- 建設業許可なしで下請を請け負う業者に対するペナルティはあるのか
建設工事を請け負う場合、原則として元請業者だけでなく下請業者も建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可の制度は、適正な施工の確保と発注者の保護が目的であり、専門工事を行う下請業者にもその役割があるためです。
ただし、軽微な工事も含めすべての施工で建設業許可の取得が必要になると、関係者の利便性を損なう可能性があるでしょう。
1件あたりの請負金額500万円未満であれば、軽微な工事として下請会社が建設業許可を取得していない場合でも発注できます。
ここでは、下請業者が建設業許可を取得せずに請負工事を施工できるケースや、違反したときのペナルティなどを解説します。
発注された下請は建設業許可なしでも大丈夫?
下請業者は、建設業許可を取得していなくても施工できるケースがあります。
ただし、建設業許可を取得せずに施工できる工事は、施工内容が制限されています。
建設業許可なしでできる工事
ここからは、建設業許可を取得せずに施工できる工事の要件を確認していきましょう。
付帯工事
付帯工事とは、主たる建設工事にともなって必要となる従たる工事をいいます。
建設現場では、一つの業種だけではなく、複数の業種による工事で建物などを完成させるのが一般的です。
大規模な工事ほど、すべての業種で建設業許可を取得するもしくは許可を取得した業者を探すのが難しいケースもあるでしょう。
そのため、建設業許可を受けた主たる工事を請け負う場合、従たる工事には建設業許可の取得が不要とされています。
従たる工事は、独立した施工目的とならず、主たる工事の目的を達成するために付帯する施工でなければなりません。
たとえば、建物の配線工事を行うために壁を剥がす内装工事などが該当します。
従たる工事の費用が主たる工事の費用を上回る場合も、従たる工事と認められない可能性が高くなるため注意しましょう。
軽微な工事
建設業法には、以下のような軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要だと定められています。
- 1件あたりの工事請負金額が税込500万円未満の工事
- 建築一式工事について請負金額が税込1,500万円未満の工事
- 木造住宅工事について延べ床面積が150㎡未満の工事
建築一式工事とは、土木工事・建築工事の2つです。
建設会社が建築一式工事の許可を取得して、工事全体の企画や指導などを行います。
それ以外の業種は専門工事と呼ばれ、27種類に分類されています。
建設業許可なしで下請を請け負う業者に対するペナルティ
建設業許可を取得せずに下請工事を行った場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
- 営業停止処分
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- (法人のみ)1億円以下の罰金
- 建設業許可を5年間受けられなくなる
ペナルティを受けると、国土交通省のHPに公開される場合があります。
課されるペナルティは一つとは限らないため、営業停止処分を受け、さらに懲役と罰金の両方を課される可能性もあります。
また、建設業法に違反すると建設業許可の欠格要件に該当するため、最低5年間は新たな許可を取得できません。
ペナルティを無視して請負工事を行った場合、最終的には許可取消処分となり、事業の継続が困難になるため注意しましょう。
建設業許可なしで下請が請け負うとバレる?
無許可の下請業者が摘発される場合、同業者からの通報や、行政機関による調査などをきっかけにバレるケースが多いようです。
行政機関による調査では、契約内容だけでなく工事の実態が建設業法に違反していないかを調べられます。
たとえば請負金額800万円の工事を、軽微な工事となる400万円ずつの契約に分割しても、工事内容を調査すれば同一とバレます。
材料費を注文者が負担して、請負金額を500万円以下に調整するケースもあるでしょう。
建設業法では、注文者が材料費や運送費を負担する場合、その市場価格などを請負金額に加えて計算します。
受注者側に材料費の負担がない場合、注文者側にも材料費について調査が行われ、購入履歴などからバレる可能性が高いでしょう。
下請業者も建設業許可を取得するメリット
下請業者として現在は建設業許可を取得していなくても、建設業許可を取得すると以下のようなメリットがあります。
- 受注できる工事の金額に制限がなくなる
- 法令順守を重視する元請業者から受注できる
- 自社をブランド化する
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
受注できる工事の金額に制限がなくなる
建設業許可を取得する最大のメリットは、受注できる工事の金額に上限がなくなる点です。
建設業許可がない状態では、最大でも500万円までの工事しか受注できません。
建設業許可を取得した場合、上限額の制限がなく自社の業種に合った工事を受注できるため、売上高を大幅に伸ばせる可能性があります。
法令順守を重視する元請業者から受注できる
これまで元請業者は下請業者の建設業許可の有無を把握するのみで、不要な場合にまで取得を求めませんでした。
しかし、法令順守(コンプライアンス)が求められる中で、下請業者により厳しい条件を求める状況になりつつあります。
元請業者は、本来法律的には必要のない下請業者に対しても建設業許可を求めるようになりました。
建設業許可を取得していない下請業者は、将来的に元請業者の現場で仕事ができなくなるかもしれません。
元請業者からすると、下請業者が無許可で工事を行っていた場合、自社に大きな影響が及ぶためです。
少しでもリスクを軽減するため、下請業者には建設業許可の取得を求めています。
この流れはさらに加速すると予想され、大手ゼネコンの現場には建設業許可がなければ入れなくなるかもしれません。
自社をブランド化する
下請業者として建設業許可を取得していれば、元請業者からの仕事をいくらでも受けられるメリットがあります。
建設業許可のない業者だけが下請業者となっている場合、元請業者は工事の金額を見ながら多くの業者に発注しなければなりません。
建設業許可を取得していれば、まとめてひとつの業者に発注できます。
仕事を一括して任せられる下請業者は元請業者にとって頼りになる存在となるため、自社の価値を高められるでしょう。
まとめ
建設業許可は、原則として元請業者だけでなく下請業者にも取得が求められます。
無許可のまま請負工事を行うと、罰金だけでなく懲役や営業停止処分などが課せられる可能性があるため注意しましょう。
事業継続が困難になるリスクを考えると、無許可の請負工事は丁重に断り、信頼できる業者を紹介するなどの対応が望ましいです。
工事内容や請負金額によっては、建設業許可が不要なケースもあります。
ただし、建設業許可が不要なケースでも、元請業者の法令順守の動きを考えると取得するメリットは大きいでしょう。
建設業許可を取得するには、専門家である行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士に依頼した場合、審査に合格するための適切なアドバイスをもらえるため、取得できる可能性が高くなるでしょう。