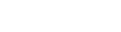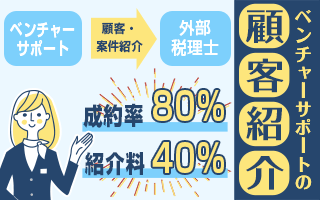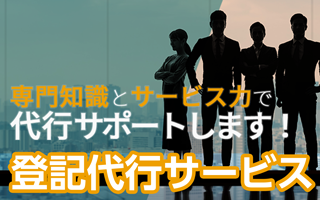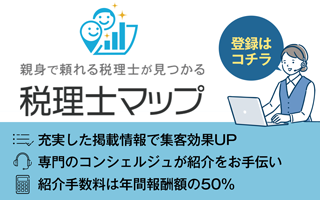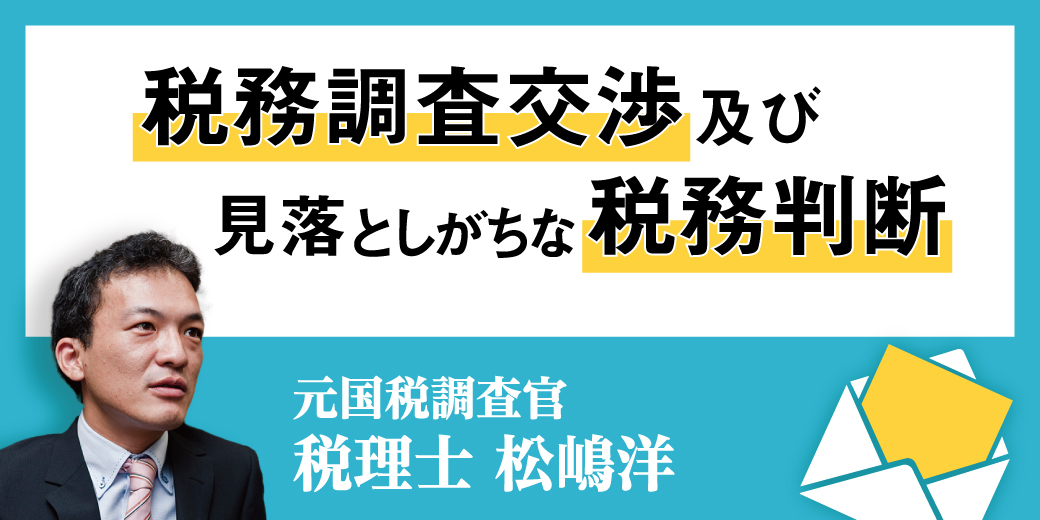
元国税調査官・税理士の松嶋です。
今回のテーマは「休業法人の役員退職金の支給」です。
先日、役員一人の法人が休業するにあたり、その役員に対する役員退職金の損金算入が認められるかという質問がありました。
役員退職金は役員の退職に伴って支給されるものを言いますので、退職に当たれば支給は可能ですが、この退職の意義は以下とされています。
筆者としては、所得税法三〇条の「退職」という観念は、雇用契約~の終了というような私法上の法律関係に即した観念として理解すべきではなく、雇用関係ないしそれに準ずる関係の終了ないしはそれらの関係からの離脱を意味するところの社会的観念として理解すべきであると考えておきたい
税務上の退職とは、あくまでも「雇用関係等からの離脱」を意味します。
このため、離脱していなければ退職に当たらない訳ですが、休業については、この離脱に当たらないことは明白と考えられます。
休業したとしても、法人は存在している訳で、役員のいない法人などあり得ないからです。
もちろん、実際に法人が消滅するようなケースにおいては、雇用関係等からの離脱がありますので、役員退職金の損金算入は認められると考えられます。
実務的には、解散ケースについては、以下の判決や質疑事例を基に、解散段階で退職金を支給することがほとんどです。
- 法人税は、法人の組織的継続的営業に基く所得に課税するものでその損益の計算は原則として収支すべき権利確定の時期を以て損益発生の時期とするいわやる発生主義によるべきであり、一般に退職金のごときも亦その支給義務の確定した日の属する事業年度の損金に算入するのが相当である。
- 法人税法第7条第4項が、解散の日をもって事業年度を区別したのは、解散を前提とした行為である限り解散前に損益が確定しあるいは更に現実に収支の行われたものまでこれを解散後の事業年度に帰属せしめようとする趣旨ではなく、解散の行為は残余財産の確定を目的とするものであるが解散前においても解散を前提とする行為を法が禁ずるものではなく、解散前の行為が後に行われた解散を前提とした行為なりや否やの区別が不明確なことに顧み、ただ解散後に発生した損益を前の事業年度と別個に取扱おうとするにあるものと解される。
- 法人が解散した日の決議をもって同日退職した役員従業員に対し、支給することを定めた退職金は、いわゆる発生主義の原則に従って、その解散の日の属する事業年度の損金に算入すべきものである。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm
【照会要旨】
法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与については、法人税法上退職給与として取り扱われますか。
【回答要旨】
退職給与として取り扱われます。
(理由)
法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所得税基本通達30-2(6))ので、法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法第34条
所得税基本通達30-2(6)
本題に戻りますが、解散など法人が消滅することを前提として休業することもあれば、そうではない事由でも休業することはあります。
このような場合には、やはり退職金は認められないと考えるべきですが、それと矛盾する以下の解説があります。
法人税・地方税 個人事業への切替えに伴い休業する法人に係る税務問題
【東京税理士界 平成29年2月1日第721号掲載】
【事例】
A社(3月決算・青色申告法人)は、昭和60年設立の有限会社(会社法上の特例有限会社)で、自宅を本店所在地として登記している。従業員は雇用しておらず、取締役である代表者甲のみが業務に従事している(登記上も取締役は甲のみ)。
A社の現在の業績(赤字決算が続いており、納税は毎期住民税均等割のみ。)及び将来の見通し(好転する見込みがない。)、また最近、社会保険への加入要請が強まっていることに鑑み、法人としての活動を休止し、個人事業に切り替えることを検討している。
具体的には、国税当局・地方税当局に対して、A社名で平成29年3月31日をもって「休業」する旨の異動届出書を提出し、また、国税当局に対して、給与支払事務所等の廃止届をA社名で、同時に、同年4月1日から個人事業を開始する旨の届出書を甲個人名で提出することを予定している。
本来であれば、A社は、解散・清算の手続きを行い、清算結了させるべきであるが、登記費用がかかること、また、将来、甲の親族がA社を別の事業で再活用する可能性もあることから、登記上の手続きを行わず、平成29年3月期の法人税・地方税申告書の提出と住民税均等割の納付を最後に、その後の事業年度においては、申告・納付を行わない予定である。
また、平成29年3月期に代表者甲に対して退職金を支給することも検討している。
この場合、休業するA社に税務上どのような問題が想定されるであろうか。
【回答】
(1) 事業活動をA社から甲個人に切り替えるのであるから、A社が所有する資産を適正な時価により甲に譲渡するとともに、A社に帰属する負債について的確に引き継ぎ、事業の移転を明確にする必要がある。資産・負債の譲渡・引継ぎ等が適切になされなければ、引き続きA社における事業とみなされ、A社に課税所得が認定されるおそれがある。
(2) 法人税法・地方税法に「休業」という概念はなく、法人が法的に存続する限り、確定申告書を提出する義務がある。休業後の各事業年度において、正当な理由なく確定申告を行わない場合には申告義務違反となり、罰則がある。また、確定申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、青色申告承認の取消事由に該当する。
将来、甲の親族がA社を再活用する際には、取り消されている可能性がある。
(3) 住民税均等割は、人的及び物的設備があり、事業の継続性があると認められる事務所等がある場合に課税される。人的設備又は物的設備がないこと、事業を行っていないことのいずれかに該当しない場合には、均等割の納付義務がある。
(4) 休業しただけでは、登記上、代表者甲の取締役としての地位に変更がない。退職金を支給するのであれば、解散登記により、甲の地位を取締役から清算人に変更させる必要がある。ただし、取締役としての職務が終了し、事実上退職したと同様の事情にあることを明確にすれば、解散登記を行わなくても、退職金の損金性が認められる可能性はある。
【検討】
(1) 資産・負債の譲渡・引継ぎが的確になされない場合の問題点
いわゆる「個人成り」であることから、まず、個人に対し、法人の資産及び負債につき、譲渡及び引継ぎ等を的確に行うとともに、事業主体・事業損益の帰属を明確に区分する必要がある。社内的には、臨時株主総会を開催して、法人としての業務を休止し、代表者甲個人に事業を移管する旨の決議を行い、譲渡及び引継ぎ等を行う資産及び負債の明細を明らかにする。その上で、適正な時価に基づき、これら資産及び負債の譲渡等を実行する必要がある。事業を引き継ぐ甲個人においても、事業開始に当たり、これらの資産及び負債を帳簿上明確にしておくことが必要である。
例えば、個人事業に切り替えた後の売上高をすべて甲個人の事業所得に係る収入金額として確定申告した場合であっても、取引先との間で従前どおりの関係を維持するため、請求書の発行者をA社のままとし、法人名義の預金口座を入金口座とすることは避けるべきである。
入金額を直ちに個人口座に振り替えたとしても、入金額はA社の売上高と認定される一方で、法人の個人口座への資金移動は代表者甲に対する給与又は貸付金と認定されることも考えられる。後述する均等割の納付義務の判定、役員退職金の損金性判断に際しても、こうした個人成りに伴う手続き、事業主体・事業損益の個人へ帰属が的確かつ明確になされているかどうかがポイントとなる。
(2) 休業後の各事業年度において確定申告を行わないことの問題点法人税法において、休業という概念は存在しない。
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき、当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額、所得の金額について計算した法人税の額等を記載した申告書を提出する義務がある(法法74(1))。
したがって、A社が休業後の各事業年度において、確定申告書の提出を行わないということは、同条同項の義務に反することになり、罰則が科される可能性もある(法法160)。
地方税法においても、法人税と同様に申告書の提出義務が課されている(地法53(1)=道府県民税、72の25(1)等=事業税、321の8(1)=市町村民税)が、罰則の適用は、納付すべき税額の全部又は一部を免れた場合に限定される(地法62(3)、72の49の3(3)、324(5))。
また、確定申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、青色申告の承認の取消事由に該当する。将来、甲の親族がA社を再活用する際には、青色申告の承認が取り消されている可能性がある(法法127(1)四)。
(3) 休業後の各事業年度における住民税均等割の納付義務
法人住民税の均等割は、都道府県内・市区町村内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)及び寮等を有する法人に対して課される(地法24(1)三・四=道府県民税、294(1)三・四=市町村民税、734(2)三=都民税)。
ここで、事務所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう〔地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)及び同(市町村税関係)第1章一般的事項六(1)〕。
すなわち、本店所在地における均等割の納税義務は、登記上法人が存在することで直ちに生ずるものではなく、①人的設備の存在、②物的設備の存在、③事業の継続性の3要件全てを満たす場合に生ずる。したがって、3要件のいずれかを欠く場合には均等割の納付義務はない。この点を慎重に検証する必要がある。
①人的設備の存在
人的設備とは、事業を遂行するために設置される人的資源をいう。この人的資源には、従業員のみならず、役員も含まれる。休業後においても、登記上代表者甲は、取締役としての地位にあるため、本店所在地における人的設備の存在を完全に否定することはできない。
②物的設備の存在
物的設備とは、事業を遂行するために設置される物的資源をいう。休業に際して、A社の資産及び負債の全てを甲個人に譲渡及び引き継がせた場合には、帳簿上物的設備は存在しないこととなる。しかしながら、代表者甲の自宅を本店所在地として登記している場合には、自宅が存在する限り、物的設備の存在を完全に否定することはできない。
③事業の継続性
A社の休業と個人事業への切り替えに伴い、A社としての事業の継続性は、途切れることとなる。人的設備の存在、物的設備の存在を完全に否定できないことを考えると、事業の継続性が途切れた事実の存在が極めて重要になる。この点を明確にするため、(1)の手続きを丁寧に進める必要がある。
(4) 休業時に支給する役員退職金の損金性
退職給与とは、退職の事実に起因して支給するものであり、役員に対する退職給与については、株主総会の決議等により、その支給額が具体的に確定した日又は支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理した場合に、損金算入が認められる(法基通9-2-28)。
法人の休業に際して、解散登記を行わない場合には、A社におけるただ一人の取締役である代表者甲は、登記上、取締役の地位に置かれ続けることになる。すなわち、形式的には、退任しておらず、分掌変更が行われたわけでも、清算人に選任されたわけでもない。
したがって、法人の休業に際して、甲に退職金を支給するのであれば、解散登記を行い、甲の地位を取締役から清算人に変更させる必要がある〔法基通9-2-32、所基通30-2(6)〕。
ただし、法人の休業に伴い、代表者甲の取締役としての職務が終了し、役員給与の支給も終了する場合、甲は、事実上退職したと同様の事情にあるということができる。こうした実質面に着目すれば、解散登記を行わなくても、休業時に甲に支給する退職金の損金性が認められる可能性はある。
このためには、退職金支給を決議する総会議事録で、退職金の支給事由(「休業に伴い、取締役としての職務が終了するため」)を明確にしておく必要がある。
(注)
内容は、平成28年12月16日現在の法令等に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決支援の一環として掲載しています。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見(参考意見)ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任において行ってください。
【東京税理士会 会員相談室提供】
上記を前提とすると、
「総会議事録で、退職金の支給事由(「休業に伴い、取締役としての職務が終了するため」)を明確に」することで解散を待たない休業でも退職金の支給が認められると結論づけられます。
しかし、この取扱いは雇用関係等からの離脱には当たらないと考えるべきであるため、本来は認められるものではありません。
最終的には国税との交渉、ということになりますが、少しでも税額が減るように努力するべきでしょう。
下記でも情報を発信していますので、ご参考にしてください。
元国税調査官・税理士松嶋洋のFacebookページ
税務調査対策ノウハウPDF
元国税調査官だから話せる税務調査対策ノウハウPDFを、完全に無料で公開しています。
松嶋税務セカンドオピニオン&税務調査対策ノウハウPDF
松嶋税務セカンドオピニオン
税理士先生からの税務相談を1時間5万円(税抜)で受けています。
同一テーマなら追加料金なく相談可能ですので、安心してご相談ください。
松嶋税務セカンドオピニオン
「税務調査交渉及び、見落としがちな税務判断」についての注意事項
- 記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。
本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。 - 掲載中の文章等の著作権は著者である合同会社アクトオーシャンに帰属し、無断転用・ 転写・複製を禁止致します。