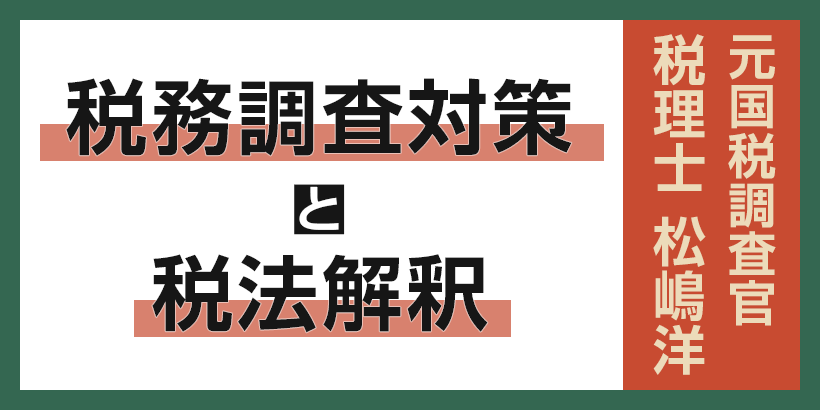
元国税調査官・税理士の松嶋です。
税務雑誌等から注目すべき税務記事を紹介します。
今回はT&A master899からです。
「生計一」の解釈は所得税と相続税の小規模宅地の特例の判定では違う。このように判断された事例があるようですが、これはショックすぎる判決です。
具体的には、所得税法56条の生計一親族に対する経費の支払いと、特定事業用宅地等の生計一の解釈について。前者は同一の財布と言えるかが問題になりますが、後者は生計一親族の事業用宅地に対して相続税を課税されると担税力の問題があることを踏まえ、特例対象宅地の上で営まれていた生計一親族の事業によって、その親族の生計だけではなく、被相続人の生計が維持されていたという関係がなければならない、こんなとんでもない判断がなされているようです。
条文解釈で趣旨解釈も必要な場合はありますが、実際にここまで踏み込んで小規模宅地の特例を解釈している実務などないはずで、実際のところこんなことまで判断する必要は個人的にはないと思います。一例として、被相続人が年金暮らしで余った土地を同居の息子に貸して、同居の息子が事業をやっていれば、その土地に税金掛けると担税力ないので特定事業用宅地でいいはずでしょう。事実関係をもっと検討する必要がありますが、違和感が大きい判断です。何より、小規模宅地の特例は租税特別措置法の規定で、文理解釈第一だ、などといって納税者に不利な判断をした、違和感がある判例も多くあります。
それにしても、相続税と所得税で同じ用語でも意味が違う、なら、多くの大学者が言っている「借用概念論」は全くのフェイクニュースであることが明白であると考えます。にもかかわらず、この誤った解釈方法が幅を利かせる場合もありますので困るのですが。
中には、「租税法学者の全ての論文を読んでいるので、税法に詳しい」とお考えになる方もいらっしゃいますが、何ら拘束力のない学者の論文を読むよりも、じっくりと法律を読んだ方がいいかと思います。















