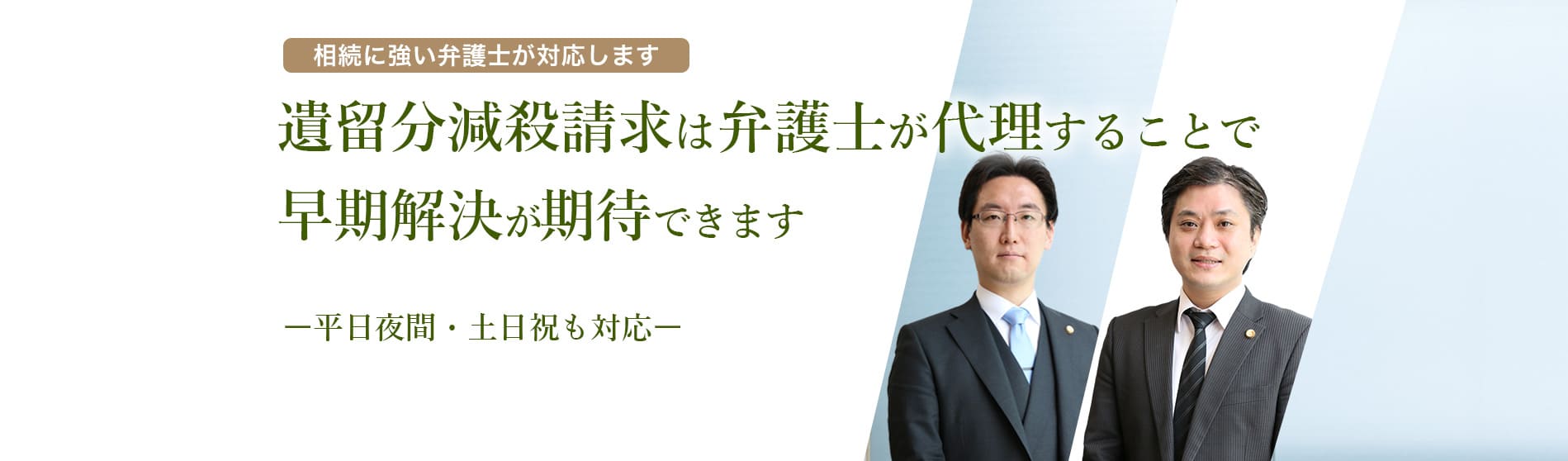- 遺言書の内容に不当を感じる
- 主張する遺留分を最大限にしたい
- 遺留分減殺請求の手続きを一任したい
- 早期の解決を図りたい
こういったお悩みをお持ちの方は、電話無料相談をご利用ください。


資料請求・無料相談はこちら
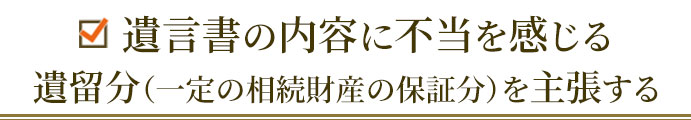
「私の遺産はすべて愛人に相続する」
遺言書を開封したらとんでもない記載があったなんてことも考えられます。不当な遺言書が出てきた場合には最低限の権利の主張をすることができます。この最低限の権利を「遺留分」といいます。
「遺留分」というのは、相続人の中で一定範囲の人たちに一定の相続財産の取り分を保障するという制度のことです。相続人は血縁という観点から見て被相続人に近いためある程度の権利を持たせることが妥当であること、また、被相続人の亡き後にその人たちの生活を守るという意味もあります。遺留分が認められるのは被相続人から見て関係の近い人たちということになりますが、具体的には法定相続人の中の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)に与えられています。兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。相続人がいれば「遺留分減殺請求」といって、被相続人の死後に一定金額の取り戻し請求をすることができます。
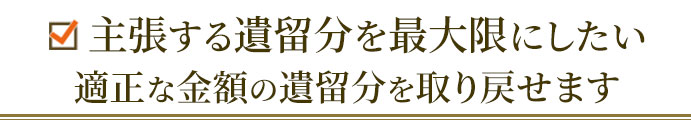
特に不動産が相続財産に含まれる場合には不動産評価額で遺留分算定額が大幅に変わってきます。
弊社ではグループ内の税理士との連携、弊社関連会社の不動産会社と連携して主張できる遺留分を適切に算定します。

遺留分減殺請求では遺言書等で相続人とされた人を相手として話し合いを行いますが、相手が話し合いに応じない場合や主張が食い違う場合には家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。
遺留分減殺請求の手続きの流れ
-
内容証明郵便の発送
遺留分減殺請求権は遺留分の侵害を知ってから原則1年となります。
まずは、内容証明郵便で確実に遺留分を行使します。 -
相手の相続人へ協議申し入れ
相手方相続人とまずは遺留分の支払い等について協議を行い、双方合意できる条件が整えば、若いが成立します。なるべくこの時点で解決できればよいですが、協議が整わない場合は調停申し立てとなります。 -
家庭裁判所への遺留分減殺調停
家庭裁判所に調停の申し立てを行い、裁判所主導のもと合意、解決を図ります。
調停には当事者の出席がしなくても代理人の弁護士で進めることができます。 -
遺留分減殺訴訟
調停が不調に終わった場合の遺留分減殺訴訟は、家庭裁判所ではなく地方裁判所で行う手続きです。
訴訟によりお互いの主張が出尽くしたら、最終的に判決という形で裁判所は事件の解決を行います。
裁判所の判決には強制力がありますから、一方または双方が不同意であったとしても財産の差し押さえなどの形で強制的に判決内容が実現されることになります。
なお、訴訟の途中で和解を行うことも可能です。

手続きの流れ
1 法律相談の予約

まずはお電話にて法律相談のご予約をお取りください。
法律相談をしたからといって、そのまま依頼しないといけないということはありませんので、お気軽にご相談ください。
また何から相談すればよいのかわからないという方も、弁護士に相談することで物事が整理されて、
ご相談だけで解決することもあります。
※遺産分割につきましては、お電話でのご相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。
2 弁護士との法律相談
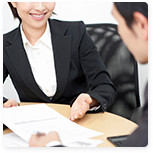
弁護士が面談を通して詳しい事情や状況をお伺いします。
その上で、依頼者の立場に立って依頼者にとっての最善策をご提案します。
なお、面談時間を有効にご活用いただくために、事前に相談内容などをメモにおまとめいただいたり、
遺言書などの資料をお持ちいただけるとスムーズに進みます。
法律相談で解決した場合は、これで終了となります。
3 弁護士への業務依頼

弁護士に具体的な業務依頼をお考えの場合、弁護士から今後取り得る解決策、その見通し、
必要な費用などを具体的にご説明します。その上で、正式に依頼するかどうかを決定してください。
時間をかけて家族とご相談の上、後日に回答をしていただくことも可能です。
その上で内容に十分ご納得いただければ、委任契約を締結します。
4 弁護士が活動開始
委任契約後は弁護士が直ちに活動を開始します。進捗状況をこまめに依頼者と報告し、 依頼者のご意見をお伺いしながら案件の対応を進めていきます。
まずはお気軽にご相談ください!


資料請求・無料相談はこちら